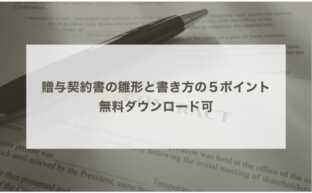「ピアノ教室を長年営んできた私。将来死んだときは、このグランドピアノを愛弟子の一人に譲り、いつまでも愛用してもらいたいわ」
「趣味で集めた庭の盆栽がたくさんあるのだが、俺が死んだら誰が手入れをしてくれるのかな。捨てるのはもったいないし・・・。そうだ、盆栽教室の先生に全部あげちゃおう!」
こういったケースで有用な法制度が、今回取り上げる「死因贈与」です。
死因贈与は、その名の通り、「死亡を原因とする贈与」のことをいいます。
死因贈与を上手に活用すれば、遺言と同じように、自分の希望通りに遺産を分配することができます。
この記事では、
- 死因贈与が使える場面や手順、遺贈との共通点・相違点
などを詳しく解説しています。
「自分の財産を家族にだけ譲るのはちょっと…。お世話になったあの人に、少しでも分けてあげたい」「介護をしてくれた人に少しでも分けて感謝を伝えたい」など
そのような意思を実現したい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
遺贈について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
1、死因贈与とは?どんなときに使うの?

死因贈与は「死因贈与契約」、つまり贈与契約の一種です。
通常の贈与契約は、AとBの間で「Aの財産をBにあげる」と約束し、その約束をA、Bが生きている間に実行します。
他方、死因贈与契約は、「Aが死んだら、Aの車をBにあげる」というように、財産の贈与者(=財産を譲り渡す側)が死んだときに契約の効力が発生し、その効果として財産の権利が受贈者(=財産を譲り受ける側)に移転するという契約なのです。
死因贈与は、主に以下のようなケースで使います。
(1)相続人以外に相続させたいとき
死因贈与は、相続人以外に財産を相続させたい場合に使うことができます。
「相続人以外に遺産を渡したいなら、遺言でも可能では?」と思うかもしれません。
もちろん可能です。
遺言でも「遺贈」によって、相続人以外に財産を渡すことができます。
遺贈と死因贈与には似ている点が多くありますので、後ほど説明します。
(2)被相続人が現に使っているものを譲るとき
生前に何かを贈与する場合、一般的にはそれを現に使っていないことが多いです。
いま住んでいる家を他人に生前贈与して自分がその家から出て行くということは通常考えにくいでしょう。
それに対して、現在住んでいる家を死因贈与によって他人に譲り渡すということはよくある方法です。
このように、被相続人が現在使っているものを将来的に誰かに譲りたいときに死因贈与を活用します。
(3)「あげる代わりに、条件がある」そんなときは負担付死因贈与契約を使う
先に見たように、死因贈与は契約です。
契約には、内容が合法であるかぎり、さまざまな条件を付けることができます。
〈条件の例〉
「私が死んだらこの車を君にあげよう。ただし、ローンがたくさん残っているので、私の代わりに君が全額負担してね」
「私の死後、この家の所有権を譲ります。その代わり、私が死ぬまでの間、この家に同居して家事手伝いをしてくれませんか?」
|
このように、「贈与する人が亡くなったら何らかの財産を相手に譲るが、その代わりに相手は、一定の条件を負担する」という契約を、「負担付き死因贈与契約」と言います。
「相続人以外の第三者に自分の財産あげたいが、タダであげるのはちょっと……」といった場合は、負担付死因贈与契約を活用すると良いでしょう。
2、似て非なる制度「遺贈」との共通点は?

死因贈与とよく似ている制度が「遺贈」です。
遺贈とは、遺言によって自分の財産を他者に与える行為です。死因贈与とよく似ていますが、遺言で相続人以外に財産を譲り渡したいときには「遺贈」を使います。
遺贈と死因贈与には、共通点が4つあります。
(1)死亡と同時に権利が移転する
遺贈も死因贈与も、遺言や契約で指定した財産の権利が、死亡と同時に相手方へ移転します。
遺贈や死因贈与契約では、遺産分割協議などは一切不要で、被相続人が死亡した瞬間に、特定の財産が特定の人(受遺者、受贈者)のものになるのです。
(2)遺留分侵害額請求の対象となる
遺贈や死因贈与契約によって特定の財産の権利が移転した場合、遺留分の問題が生じます。
遺留分とは、民法が兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障する相続割合のことです。遺留分の割合は、相続人が直系尊属(両親や祖父母)だけであれば法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。
遺贈や死因贈与契約の結果として、法定相続人の遺留分を侵害した場合は、その相続人は財産を譲り受けた相手方に対して、「私の遺留分相当額を払え!」と遺留分侵害額請求をすることが可能です。
遺留分侵害額請求の詳細については、こちらの記事をご参照ください。
(3)相続税の対象となる
遺贈で財産をもらった人は、その金額が大きい場合、相続税を課税されることがあります。
「遺贈なんだから、贈与税じゃないの?」と思うかもしれませんが、遺贈は遺言によって財産を譲り受ける行為であること、遺言は遺言者(被相続人)が死亡したときに効力が発生することから、贈与税ではなく相続税の対象となります。
死因贈与契約も同様です。
被相続人の死亡を原因として権利を取得する点では遺贈と同じですので、相続税の対象となります。
なお、相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から起算して10か月以内に納付しなければなりません。
(4)撤回ができる
遺言は、本人が亡くなるまで何度でも書き直すことができます(民法1022条)。となれば、当然、遺贈も撤回できます。
「お世話になってたお隣のAさんに私の車をあげようと思って遺言に書いたけど……Aさんが私の悪口を言っていたと知ったので、遺贈はやめたい!」
そんな時は、前の遺言を撤回して、新しく遺言を書き直せばいいわけです。
死因贈与は遺贈のルールに従うものとされているので(民法第554条)、同じく撤回できます。
ただし、注意したいのは「負担付き死因贈与」のケースです。
前述したように、負担付き死因贈与は、贈与する人が亡くなったら何らかの財産を相手に譲るが、その代わりに相手は、贈与者が亡くなるまでの間、一定の条件を負担するという契約です。
受贈者が、この負担を全部(または大半)履行していたのに、贈与者が「やっぱり、やーめた!」と撤回してしまったら、負担を履行した受贈者が著しい不利益を被ります。
たとえば、「私が死んだら、ガレージに置いてある自動車は君のものだ。ただし、あちこち塗装がはげていて見苦しいので、私が死ぬまでに、キレイに塗り直しておいてくれ」といった負担付き死因贈与契約が結ばれたとしましょう。
受贈者が、その自動車の塗装を塗り直して新車同様にリペアしたところ、贈与者が、「すまん。あの自動車を譲って欲しいと言ってきた人がいるので、やっぱり君にあげるのは取りやめだ」などということになったら、受贈者は大損することになります。
このように、負担付き死因贈与にかぎっては、受贈者が負担の全部(または大半)を履行した後は、贈与者はもはや撤回できなくなるのです。
3、似て非なる制度「遺贈」との相違点は?

ここまで説明してきたように、遺贈と死因贈与契約には多くの共通点がありますが、異なる点もあります。
(1)当事者間の合意の必要性
遺贈は、遺言者が遺言を書くことで、特定の第三者に財産を譲り渡すことを宣言する行為です。
このような一方的な行為のことを、法律では「単独行為」と言い、契約とは違って相手方の同意がなくても有効に成立します。
他方、死因贈与は、単独行為ではなく「契約」ですので、有効に成立するには当事者間の合意が必要です。
(2)目的財産が不動産の場合にかかる税金の額
遺贈や死因贈与で不動産を譲り受けた場合、受贈者には、相続税のほか、不動産取得税や登録免許税(所有権移転登記の手数料)が課税されます。
以下の通り、死因贈与は遺贈よりもこれらの税率が高く設定されています。
〈不動産取得税の税率〉 l 遺贈・・・受贈者が法定相続人の場合は非課税、法定相続人以外の場合で土地・住宅用の建物の場合は3%、住宅以外の建物の場合は4 % l 死因贈与・・・土地・住宅用の建物の場合は3%、住宅以外の建物の場合は4% 〈登録免許税の税率〉 l 遺贈・・・受贈者が法定相続人の場合は0.4%、法定相続人以外の場合は2% l 死因贈与・・・一律2% |
遺贈と死因贈与は共通点も多いため、どちらを選択するか迷うものですが、財産を譲りたい相手が法定相続人であれば、税負担だけを考慮するなら遺贈のほうがお得になります。
(3)遺贈には「遺言書」が必要
遺贈は「遺言による贈与」ですので、遺言書が必要です。
他方、死因贈与は贈与者と受贈者による契約ですので、当事者が合意すれば口約束でも成立します。
これは、贈与契約の法的性質が、当事者の合意だけで(口約束だけで)成立する「諾成契約(だくせいけいやく)」であるからです。
ただし、死後に契約の有無や効力が問題となる可能性がありますので、実際にされる際には口頭ではなく契約書を必ず作成しておきましょう。
4、死因贈与の手順

最後に、死因贈与の手順をまとめます。
(1)相手方との合意
贈与者が死亡することを条件に、特定の財産を受贈者に譲り渡すことを約束します。
ただし、負担付き死因贈与の場合は、贈与者が死亡しただけでは贈与の効果が発生せず、契約で定めた一定の負担を受贈者が履行することが必要です。
(2)契約書の作成(証拠のため)
前述の通り、死因贈与は口頭でも可能ですが、将来トラブルになった場合に備えて、契約書を作成しておきます。
(3)不動産の場合は仮登記を
死因贈与で不動産を贈与する場合は、仮登記をつけておくと良いでしょう。
仮登記とは、登記の優先順位をあらかじめ確保するために行う登記です。
死因贈与による不動産の所有権移転は、贈与者の承諾があれば、この仮登記をすることが可能です。
たとえば「Aさんが死んだら俺(B)に家をくれると言っていたけど、あの人すぐに心変わりするから、いまいち信用できない……」といった心配も、仮登記をしておけば安心です。
もしAが本当に気が変わって他人に家を売ってしまったとしても、B名義の仮登記をつけておけば、将来Aが死んで死因贈与の効果が発生したときに本登記とすることで、Aが家を売却した人に対して所有権を主張できます。
まとめ〜相続の方法を決める際は弁護士に相談を
死因贈与のポイントについて解説してきましたが、ご自分の将来の相続に役立ちそうな情報はありましたか?
遺産相続において大切なことは、「自分の財産を誰に、どれだけあげたいか」という願望をただ叶えるだけでなく、遺留分のことや税金のことなども考慮し、後々もめないような相続にすることです。
そのためには、生前贈与、遺言、遺贈、死因贈与といった様々な法制度を組み合わせることも必要です。事前の対策が非常に重要です。
また、財産を承継する側の希望や気持ちも考慮しておくとさらによいでしょう。相続において複数の法制度と当事者の気持ちを総合的に検討しながら最善策をとるために、法律のプロである弁護士と税金のプロである税理士に相談されることをおすすめします。
現在では弁護士と税理士に同時に相談できるワンストップ型の事務所も増えています。ぜひ一度ご相談ください。