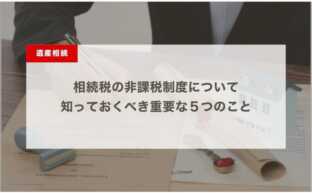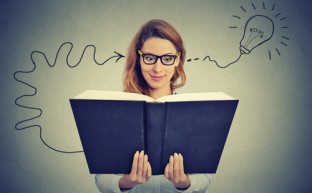相続税の申告にかかわることは、人生のうちでそう何度もあることではありませんから、「何から始めてよいのやらさっぱり…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税は「遺産額-基礎控除」の金額が1円以上ある場合に課税される税金です。
平成27年の相続税法の改正により、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたため、「お金持ちだけに課税される税金」とは言えなくなっています。
この記事では、
- 相続税の申告期限の基礎知識
- 相続税の申告手続きについての基本的な考え方やおおまかな手続きの流れ
- 相続税の課税対象となる財産
について解説いたします。ご参考になれば幸いです。
相続税に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、相続税の申告をする前に|まずは申告期限が過ぎてないかを確認

相続税の申告には期限があります。
具体的には、「相続が発生したことを知った日の翌日から数えて10か月以内」に、税務署に対して申告書を提出し、納税を完了しなくてはなりません。
申告期限を過ぎてしまうと追徴課税(後でくわしく解説します)を課せられてしまう可能性がありますので注意しておきましょう。
なお、「相続の発生を知った日」がいつか?は「普通であれば知り得た日」を意味しますので、「実際に亡くなった日」=「相続の発生を知った日」として扱われるのが実際のところです。
(1)相続税の申告には期限あり
上で見た「相続税の申告期限」は、原則として延長してもらうことができません。
また、申告とは「税務署に申告書類を提出すること」をいいますが、当然ながら期間中に納税(税務署や金融機関の窓口でお金を実際に支払うこと)まで完了しなくてはなりません。
相続税は現金で納める必要があることにも注意しておきましょう。
遺産の多くを土地や建物といった財産が占めている相続では、「遺産はたくさんあるけれど、現金は意外に少なくて、相続人が自腹を切って相続税を納税する」というケースが少なくありませんので、注意が必要です。
相続税の申告期限について、くわしくはこちらの記事もご確認ください。
(2)期限経過したらどうなる?
もし、相続税の申告期限までに申告と納税を完了できなかった場合、どのような扱いになるでしょうか。
結論からいうと、相続税の申告と納税を期限までに完了できない場合、次の2つの不利益を受ける可能性があります。
- 追徴課税
- 税軽減特例が使えなくなる
以下で順番に解説いたします。
①追徴課税
相続税の申告期限が過ぎた後も何もせずに放置してしまったという場合、多くのケースで税務署による税務調査が行われます。
これは文字通り「税金をルール通りにきちんと納めているかどうか、税務署の職員がチェックしに来る」というものです。
そして、税務調査の結果として申告漏れ、納付漏れがあることが発覚した場合には、状況に応じて次のような追徴課税(本来納める税金にプラスしてお金を納めること)を求められてしまいます。
【表】
| 追徴課税の種類 | どのような場合にかかる? | 税率等 |
| 無申告加算税 | 期限までに申告書を提出しなかった場合に課税されます | 50万円以内の部分は15% 50万円超の部分は20% |
| 過少申告加算税 | 期限内に申告書を提出したけれど、金額が足りなかったという場合に課税されます | 通常10% 追加納税分が本税額を超える場合や、50万円を超える場合は15% |
| 重加算税 | 無申告や過少申告がある場合で、財産の隠匿など状況が悪質な場合 なお、重加算税が課税される場合は無申告加算税や過少申告加算税はかかりません | 過少申告加算税に代えて課せられる場合35% 無申告加算税に代えて課される場合40% |
| 延滞税 | 申告期限を過ぎて申告納付を行った場合に日割り計算で納付 | 納期限から2か月以内は2.6%(平成30年) それ以降の分は8.9%(平成30年) |
これらはきちんと手続きをしておけば納める義務のない税金ですから、相続税の申告は期限までに完了しておくようにしましょう。
②税軽減特例が使えない
相続税の申告を期限までに完了しない場合、本来は利用できるはずの「税軽減特例」が利用できなくなってしまいます。
税軽減特例とは、ごく簡単にいえば「税金が安くなるお得な制度」のことですが、これらの多くは相続税の申告を期限までに完了することが条件となっているためです。
相続税の申告期限を過ぎると利用できなくなる税軽減特例としては、次のようなものがあります。
- 小規模宅地等の特例:遺産に宅地が含まれる場合、その相続税評価額を最大8割引きにしてもらえるというものです
- 相続税の配偶者控除:亡くなった人が相続人の配偶者であった場合、遺産額1億6,000万円までは相続税がかからないというものです
なお、2つ目の配偶者控除については「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を期限までに提出しておくと、相続税の申告が期限後になったとしても配偶者控除の適用を受けることは可能です。
(3)申告期限が過ぎそうなときはすぐに税理士等専門家へ相談を!
相続税の申告期限が迫ってきているけれど、相続人同士の話し合いがうまくいかず、遺産分割もまだ完了していない…。
相続税の申告は初めてなので、何から始めていいかわからない…。
このようにお悩みの方にとって、強い味方になってくれるのが税理士や弁護士といった専門家です。
特に、遺産分割協議については相続人(遺族)同士の話し合いでは利害が対立してしまってなかなか進められないということも多いでしょう。
当事者同士ではなかなか言いにくいことでも、他人である専門家に第三者の立場で話し合いに立ち会ってもらうことでスムーズに進められるケースが少なくありません。
また、すでに申告期限がぎりぎりで専門家に相談しても間に合いそうにない…という場合には、とりあえず概算額で相続税を納税しておき、後から正確な金額に修正する(差額は返金されます)という形も選択できます。
遺産分割協議や調停については弁護士が、相続税の申告手続きについては税理士が手続きの多くを代行してくれますから、相談を検討してみてください。
2、相続税申告の手順-自分で申告することも可能!

上でも見たように、相続税の申告については、相続手続きを専門にしている税理士に代行してもらうことが可能です。
一方で、遺産の金額がそれほど大きくないケースや、相続人が1人だけであるようなケースでは自力で相続税の申告を行う人も多いです。
ご自身で相続税申告の手続きをされる場合には下記が参考になりますので、良ければご覧ください。
相続全体の手続きの流れとしてはこちらをご覧ください。
相続税申告の手順を一覧にすると、次のようになります。
- 相続財産の総額を集計してリスト化する
- 相続人を確定する
- 相続税がかかるのか確認する
- 各相続人の相続税を計算
- 必要書類の手配
- 申告書を作成
それぞれの手順について順番に解説しましょう。
(1)相続財産はいくら?相続財産の総額を集計してリスト化しよう
相続税は相続財産の金額に応じて課税されるものですので、まずは相続する財産がいくらあるのか?を確定する必要があります。
この時、「相続税を計算するときの財産の評価額」は、少し特殊な計算方法(評価方法)を用いないといけないことに注意しておきましょう。
例えば、土地や建物といった不動産や、株式といった財産は、「いつの時点の価格を基準にするのか?」によって大きく値段が変わります。
以下では相続税の計算を行う場合の財産の評価方法について解説します。
①現金
相続が発生した時点(故人が亡くなった日)での残高が相続税評価額となります。
②預貯金
現金と同様、相続が発生した日の預金残高が相続税評価額です。
③有価証券(公社債・国債・上場株式・投資信託など)
相続が発生した日から見て、直近の取引所終値が相続税評価額となるのが原則ですが、次のうちもっとも低い金額を相続税評価額とすることができます。
- 相続が発生した日の属する月の、日ごとの最終価格の平均額
- 相続が発生した日の属する月の前月の、日ごとの最終価格の平均額
- 相続が発生した日の属する月の前々月の、日ごとの最終価格の平均額
例えば、2月20日に相続が発生したとすると、1.は2月1日~19日の終値平均額、2.は1月1日~1月31日の終値平均額、3.は12月1日~31日の終値平均額、といった具合です。
これらを計算してもっとも低い金額を相続税評価額とすることができます。
④不動産(家屋(貸家含む)・(賃宅地・貸家建付地も含む)・借地権・農地山林
土地や建物といった「不動産」は、相続税評価額の計算方法が複雑なので注意が必要です。
- 土地の相続税評価
まず、土地の相続税評価額は、路線価方式という方式で計算するのが原則です。
路線価方式とは、その名の通り「路線価(国が決めている土地の値段)」に応じて土地の相続税評価額を計算する方法で、具体的には以下の計算式で求めます。
路線価方式による土地の相続税評価額=1㎡あたりの路線価×地積
1㎡あたりの路線価は国税庁のホームページで、地積は毎年贈られてくる固定資産税の納付書に記載されています。
なお、宅地(住宅を建てるために使っている土地)については、「小規模宅地等の特例」という税軽減措置を受けることが可能です(土地の相続税評価額が最大80%割引される、非常に効果の大きい軽減措置です)。
- 建物の相続税評価
建物に関しては、固定資産税評価額(固定資産税の納付書に記載されている金額)がそのまま相続税評価額となります。
固定資産税の納付書は不動産の所有者(その年の1月1日時点で判断されます)に対して毎年4月ごろに届きますので、大切に保管しておきましょう。
- 借地権など「土地に関する権利」の相続税評価
これは「自分の土地」であった場合の路線価価格に、借地権割合をかけ算した金額が相続税評価額となります。
※借地権割合は、土地ごとに国税庁のホームページに記載されています。
⑤ゴルフ会員権・リゾート会員権などの権利
ゴルフ会員権・リゾート会員権などの「施設を利用する権利」は、相続発生の日の時価×70%で計算を行うのが原則となります。
※預託金等が直ちに現金化できるかどうか、取引価値があるかどうかによって計算方法が微妙に異なることがありますので、くわしくは専門家にお尋ねください。
⑥貴金属・宝石・書画・骨董・車などの貴重品
宝石類や骨董品類は、相続が発生した時点での時価で評価されます。
買取業者や査定業者に査定額を出してもらうことでこれらの財産の時価を知ることができます。
⑦債権
亡くなった人が他人に対して持っていた債権(お金を払うように請求できる権利)は、「債権元本の金額+利息」の金額で相続税評価額を計算します。
亡くなった人が会社の経営者などであった場合に、経営する会社に対して個人で貸し付けているお金などがある場合には、それらも相続財産に含める必要があります。
⑧特許権・著作権
特許を他人に使わせることによって将来的に受け取れるであろう収益の金額を、基準年利率を使って現在価値に割引した金額が相続税評価額となります。
※専門家でも算出が難しい項目になりますので、必ず税理士等のプロに相談してください。
⑨3年以内の生前贈与(贈与税払っていない)
故人の生前に贈与を受けている人がいる場合、その贈与を受けた財産の価額は相続財産に含めなくてはなりません。
なお、贈与された財産の価額は、「贈与した時点」での時価で評価する点に注意が必要です。
⑩墓、仏具等
墓や仏具には相続税は課税されません。
⑪香典
香典には相続税は課税されません。
⑫保険金・退職金
亡くなった人が生命保険に加入していた場合、相続の発生によって遺族に対して生命保険金が支払われます。
なお、生命保険金は亡くなった人の死亡を原因として支払われるものですから、厳密にいえば「遺産」ではありません(亡くなった人が所有していた財産ではありません)。
しかし、これらは相続税の計算上は「遺産」として扱われる点に注意しておきましょう(こうした扱いがされる財産を「みなし相続財産」といいます)
みなし相続財産についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
⑬非課税財産
上で見たお墓や仏壇仏具は相続税が課税されませんが、法律上特別に「相続税を課税しない」という扱いになっているものをまとめて「非課税財産」と呼んでいます。
非課税財産には、お墓や仏壇仏具の他に交通事故による損害賠償を受ける権利、公益目的で使われることが明らかなものなどがあります。
非課税財産についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
⑭債務や葬儀費用
故人のお通夜や告別式を行うために葬儀会社に支払った費用、参列者に出した飲食費用、さらには遠方から来て下さった方に対しての心づけなどは、支払いをした分だけ遺産総額から差し引きしてもらうことができます。
ただし、一般常識で考えて大きすぎる金額の心づけなどは認められませんので注意しておきましょう。
また、亡くなった人が他人に対して負っていた債務は、「マイナスの遺産」として、遺産の総額から差し引きすることが可能です。
(2)相続人は誰?相続人を確定する
相続税は遺産を相続する人が負担するものですので、「誰が相続人となるのか?」を確定しておく必要があります。
法律上の相続人に関するルールについて確認しておきましょう。
①相続人は誰なのか
相続人となるのは亡くなった人の親族ですが、亡くなった人が遺言を残しているような場合にはその内容が優先されます。
遺言がない場合には、「配偶者と親族」が相続人となりますが、親族は次の順位に従って相続人となります。
(遺言ではなく、法律のルールに従って相続人となる人のことを「法定相続人」と呼びます)
- 第一順位:亡くなった人の直系卑属(子供や孫)
- 第二順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)
- 第三順位:亡くなった人の兄弟姉妹
なお、同順位の人が2人以上いる場合は、それらの人たちは共同で相続人となります。
例えば、亡くなった人に配偶者・子供が3人(長男・次男・三男)・父親の合計5人がいるという場合、配偶者と3人の子供は相続人となりますが、父親は相続人となりません。
法定相続人についてはこちらのページで詳細をご確認ください。
②正確に確定するために
相続人が誰になるか?は相続手続きを進めるうえで最も重要な問題ですから、手続きを進める最初の段階で確定しておかなくてはなりません。
相続人が誰かを正確に確定するためには、亡くなった人の戸籍謄本を参考にするのが適切です。
なお、戸籍謄本は結婚や養子縁組、転籍などによって変更が生じる場合がありますから、亡くなった人の「出生~死亡」までの情報が連続しているかどうかがとても大切です。
具体的には「改製」という記載があるところで新しい戸籍謄本が作成されていることになりますから、取得した戸籍謄本の他に戸籍が存在しているのではないか?と詳細にチェックしていくことが大切になります。
相続人の調査は場合によっては非常に複雑な作業になることがあり、時間もかかる可能性があります。
不安がある方は相続問題を専門としている専門家(弁護士や税理士)に相談するようにしましょう。
(3)相続税がかかるのか確認する
この記事の冒頭でも少し触れましたが、相続税は「遺産額-基礎控除」の金額が1円以上ある場合に課税される税金です。
基礎控除とは、次の計算式で計算します。
相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、亡くなった人に長男・次男・三男の3人の法定相続人がいるという場合には、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円ということになります。
そのため、もし遺産の金額が4,800万円を超えない場合には、そもそも相続税はかからないということになるのです。
相続税の基礎控除についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
なお、遺産は現金や不動産といった「プラスの遺産」だけではなく、借金などの「マイナスの遺産」も含まれることに注意が必要です。
マイナスの遺産の方がたくさんあって、そもそも遺産を相続するメリットが何もない…という場合には、限定承認や相続放棄といった方法も選択できますから、検討してみてください。
限定承認や相続放棄についてくわしくはこちらで解説しています。
(4)相続税がかかる場合は各相続人の相続税を計算
上で見た「遺産額-相続税の基礎控除」の金額がプラスになる場合には、相続税が課税されることになります。
「遺産額-基礎控除」で計算した金額のことを、相続税の計算上「課税遺産総額」と呼びます。
課税遺産総額を算出した後は、次のような流れで実際に納めるべき相続税の計算を行います。
- 法定相続分で遺産分割を行ったものと仮定して、「相続税の速算表」から、相続税の総額を計算する
- 相続税の総額から、相続人それぞれが実際に納めるべき相続税の金額を計算する
相続税の計算方法は、具体例で実際に計算をしてみた方が分かりやすいので、次の項目で具体的なケースを見ながら税額を計算してみましょう。
①事例を使って計算してみよう
例えば、次のような事例をもとに、実際に相続税の金額を計算してみます。
- 相続人は亡くなった人の妻・長男(20歳)・次男(15歳)の3名
- 遺産は現預金1億円・宅地2億円・建物1億円の合計4億円
- 借金が4,000万円ある
- 香典として合計100万円を受け取った
- 葬儀費用として200万円を支払った
- 墓を生前に購入済(費用100万円)
- 受け取った生命保険金1,500万円
- 亡くなった人の勤務先から受け取った退職金が1,500万円
- 長男が生前に現金1,000万円を受け取っていた(その際、贈与税は払っていない)
- 宅地は小規模宅地等の特例によって80%相続税評価額を割引してもらえるとする
ⅰ)相続税の対象となる遺産の金額(正味の遺産額)を求めます
まずは相続税の対象となる遺産の金額を計算します。
その際、次の6点が重要です。
- 借金についてはプラスの遺産から差し引きできます
- 香典やお墓の購入費用は相続税の計算に含める必要がありません
- 葬儀のための費用は遺産総額から差し引きできます
- 宅地は相続税の計算上「小規模宅地等の特例」によって最大80%を相続税評価額から割引してもらえます
- 相続発生から3年以内に行なわれた生前贈与がある場合にはその贈与財産の価額も遺産に含めないと行けません(ただし、贈与時に贈与税を払っている場合は必要ありません)
- 生命保険金や退職金は相続財産に含めます
これらを考慮したうえで「正味の遺産額」を実際に計算すると、以下のようになります。
正味の遺産額=現預金1億円+宅地2億円×(100%-80%)+建物1億円-借金4,000万円+生前贈与1,000万円-葬儀費用200万円+生命保険金1,500万円+退職金1,500万円=2億3,800万円
生前贈与について贈与を受けたときに贈与税を払っていた場合には、以下のようになります。
正味の遺産額=現預金1億円+宅地2億円×(100%-80%)+建物1億円-借金4,000万円-葬儀費用200万円+生命保険金1,500万円+退職金1,500万円=2億2,800万円
ⅱ)基礎控除を差し引きして「課税遺産総額」を求めます
次に、相続税の基礎控除を差し引きして「課税遺産総額」を求めます。
この場合法定相続人は妻・長男・次男の3名ですので、基礎控除は次のように計算します。
- 基礎控除=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
また、生命保険金と退職金については別建てで基礎控除(非課税限度額:法定相続人1名につき500万円です)を差し引きしてもらうことができます。
- 生命保険金の非課税限度額=500万円×3人=1,500万円
- 退職金の非課税限度額=500万円×3人=1,500万円
結果的に、課税遺産総額は以下のように計算できます。
- 課税遺産総額=2億3,800万円-4,800万円-1,500万円-1,500万円=1億6,000万円
ⅲ)「相続税の総額」を求めるため、法定相続分で分割したと仮定して各人の遺産額を計算します
課税遺産総額を、法定相続分(法律で決まっている相続割合)に応じて分割したと仮定し、相続税の総額(相続人全員で負担する必要がある合計額)を計算します。
この場合は次の割合に応じて遺産を分割することになります。
- 亡くなった人の妻:2分の1
- 亡くなった人の長男:2分の1×2分の1=4分の1
- 亡くなった人の次男:2分の1×2分の1=4分の1
課税遺産総額は1億6,000万円でしたので、相続人各自の相続分(課税価格)は以下のようになります。
- 妻:1億6,000万円×2分の1=8,000万円
- 長男:1億6,000万円×4分の1=4,000万円
- 次男:1億6,000万円×4分の1=4,000万円
ⅳ)相続税の速算表から相続税の総額を求める
ここで、次のような「相続税の速算表」というものを使って、実際に相続税の総額を計算します。
【表】
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上で見た各人の課税価格から、相続税の金額を計算すると以下のようになります。
- 妻(課税価格8,000万円):8,000万円×30%-700万円=1,700万円
- 長男(課税価格4,000万円):4,000万円×20%-200万円=600万円
- 次男(課税価格4,000万円):4,000万円×20%-200万円=600万円
- 相続税の総額=1,700万円+600万円+600万円=2,900万円
ⅴ)実際に相続した金額から各人の納税額を求めます
相続税は「実際に相続した遺産の割合に応じて負担する税金」です。
例えば「遺産を3分の1だけ相続したなら、相続税も3分の1だけ負担する」ということになります。
(誰がどれだけの割合の遺産を相続するか?は遺言がある場合には遺言書の内容に従って、遺言がない場合には遺産分割協議という話し合いで決めます)
上のケースで、例えば妻は4分の3、長男と次男はそれぞれ8分の1ずつ相続したとすると、各人の相続額(課税遺産額)は以下のようになります。
- 妻:1億6,000万円×4分の3=1億2,000万円
- 長男:1億6,000万円×8分の1=2,000万円
- 次男:1億6,000万円×8分の1=2,000万円
相続税(トータルは2,900万円)についても同じ割合で計算しますので、次のようになります。
- 妻の相続税:2,900万円×4分の3=2,175万円
- 長男の相続税:2,900万円×8分の1=362万5,000円
- 次男の相続税:2,900万円×8分の1=362万5,000円
ⅵ)利用できる税軽減制度を加味する
ここで、それぞれの人の状況に応じて「税軽減制度」を利用することができます。
このケースでは、亡くなった人の妻は「配偶者控除」、未成年の子(次男)は「未成年者控除」を適用してもらうことが可能です。
- 配偶者控除:相続額1億6,000万円までは相続税非課税となります。
- 未成年者控除:「20歳に達するまでの年数×10万円」だけ税額が差し引きされます。
よって、最終的に負担する税額は以下のようになります。
- 妻の相続税:配偶者控除により0円
- 長男の相続税:362万5,000円
- 次男の相続税:未成年者控除50万円((20歳-15歳)×10万円)により312万5,000円
②相続税がゼロなら申告不要?
上のような計算手続きで相続税の計算を行った結果、相続税がゼロになるという場合、相続税の申告手続きは原則として行う必要がありません。
ただし、「非課税の特例(配偶者控除や小規模宅地等の特例等)を利用した結果として、相続税がゼロになった」という場合には、相続税の申告が必要となることに注意しておきましょう。
【表】
| 相続税がゼロになる理由 | 相続税の申告 |
| 「遺産額-基礎控除」の金額がマイナス | 不要です |
| 配偶者控除によって相続税がゼロ | 必要です |
| 小規模宅地等の特例によって相続税がゼロ | 必要です |
(5)必要書類の手配
相続税の申告にあたっては、次のような書類を取得する必要があります。
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書(検認済証明書)
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続財産の評価額を計算するための書類
取得や発行のために時間がかかるものもありますから、なるべく早いタイミングで集めておくようにしましょう。
以下では、各書類の取得先や注意点について解説します。
①亡くなった人の戸籍謄本
亡くなった人の出生~死亡に至るまでの経緯がわかる戸籍謄本を取得しなくてはなりません。
戸籍謄本は亡くなった人の本籍地の市町村の役所で取得できます。
なお、戸籍謄本はいくつか記載事項を選択できますので、取得する際には「その戸籍を何に使うのか?」を窓口の人に伝えると適したものを発行してくれます。
②亡くなった人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
亡くなった人が1人で世帯を持っていた場合には市町村の役所で「住民票の除票」を取得します。
亡くなった人を含めて世帯が2人以上であった場合には、遺族の人が住民票を取得すれば足りますが、その際には「亡くなった人の情報が含まれた住民票が欲しい」ということを窓口で伝える必要があります。
(もし伝えなかった場合、死亡者は除外された形で住民票が発行されてしまいます)
戸籍の附票は亡くなった人の本籍地で戸籍の原本と一緒に保管されているものです。
戸籍附票には戸籍が作成されてから、亡くなるまでの住所地などの情報がくわしく記載されています(取得手続きは本籍地のある市役所で行う必要があります)
③相続人全員の戸籍謄本
相続人と亡くなった人の血縁関係を証明し、現在も存命であることを証明するために必要です。
戸籍謄本はそれぞれの人の住所地にある市町村の役所で取得できます。
④遺言書(検認済証明書)
亡くなった人が遺言を残している場合には、その遺言は勝手に開封してはならず、家庭裁判所に「検認の申立て」をして開封してもらう必要があります。
検認の手続きが完了したら、家庭裁判所が「検認済証明書」を発行してくれます。
なお、遺言が公正証書の形で作成されている場合には、検認の手続きは必要ありません。
⑤遺産分割協議書(遺言書がない場合)
亡くなった人が遺言を残していない場合、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、合意した内容を書面にまとめた遺産分割協議書を作成します。
必然的に、相続税の申告は遺産分割協議が完了していることが条件となります。
遺産分割協議が完了していないと利用できない税軽減制度もありますから、できるだけ早いタイミングで遺産分割協議は完了しておくのが望ましいでしょう。
⑥相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書には相続人全員の実印(印鑑証明を取得している印鑑)を押印しなくてはなりませんので、その実印に関する印鑑証明書の添付が必要です。
印鑑証明は市町村の役所で取得するのが原則ですが、マイナンバーカードや住基カードをお持ちの方はコンビニでも発行してもらうことが可能です。
⑦相続財産の評価額を計算するための書類
遺産に不動産や株式など、「どのような基準で評価するかによって財産の金額が変わるもの」については、それぞれの評価額を算出するための書類が必要となります。
↓これらについては以下の記事でくわしく解説していますので、良ければご覧ください。
(6)申告書を作成
相続税の金額が計算できて、必要書類もそろったら、いよいよ相続税の申告書を作成します。
(相続税の申告書には相続税の計算過程が書かれていますので、申告書を作成しながら相続税の計算をしていくのもおすすめです)
相続税の申告書には第1表~第15表まであり、「第1表をどのような根拠に基づいて作成したのか?」を具体的に説明するのが第2表~第15表ということになります。
当然ながら第1表と第2表~第15表の内容は合致していないといけませんから、注意しておきましょう。
「第2表~第15表をまず確定してから、第1表にその内容を転記する」という形で作成するのが良いでしょう。
なお、実際に相続税の申告書を見ていただくとわかるかと思いますが、非常に細かい文字で詳細な内容を記載していく必要があります。
もし申告書の内容に誤りがあった場合には税務署の職員からお尋ねが来たりしますので、自分で作成するのは難しそう…と感じる方は、無理せず税理士などの専門家に依頼するようにしましょう。
3、相続問題については弁護士・税理士へお任せください

遺産相続をめぐっては、期限までにきちんと手続きを完了したと思っても、後からトラブルが発生してしまうことが珍しくありません。
例えば、こういったケースが考えられます。
- 遺言書の内容通りに遺産分割したら、後から不満を持つ親族に遺留分を請求された…。
- 遺産分割協議が完了した後になってから別の財産が出てきた。
- 亡くなった人に、実は隠し子がいることが発覚した…。
- 相続人の中の一部に、故人の生前に贈与を受けている人がいて不公平がある
- 相続税の申告書に間違いがあり、後から税務調査に入られてしまった…。
特に、遺産が多くある富裕層の方の遺産相続においては、相続税の負担金額も大きくなり、遺産を巡って親族同士の感情的な対立が生じてしまう可能性もあります。
相続問題について不安がある…という場合には、遺産相続手続きを専門とする弁護士や税理士に相談してみてください。
誰がどれだけの遺産を相続するのか?については弁護士が、相続税をいくら納める必要があるのか?については税理士が相談に乗ってくれます。
4、相続問題を依頼する弁護士・税理士の探し方

相続問題に関する専門家を選ぶ際には、必ず「遺産相続の問題を専門分野として扱っている専門家」を選ぶようにしましょう。
相談する専門家がどのような分野を得意にしているのか?は各法律事務所や税理士事務所のホームページなどで確認することができます。
お医者さんに外科・内科・皮膚科・精神科…というようにいろんな専門分野があるように、弁護士や税理士にもそれぞれ専門分野があるので注意しておきましょう。
また、初回の相談は無料で受け付けてくれる場合が多いですから、実際に相談してみて相性を判断するのも重要といえます。
まとめ
今回は、相続税申告の基本的な流れや、実際に手続きを行う際の注意点について解説いたしました。
ほとんどの人にとって、遺産相続は人生で1回か2回かかわることがあるかといった特別な機会となるでしょう。
申告期限をすぎないように手続きを進めていくとともに、必要に応じて専門家の支援を受けることを検討してみてください。