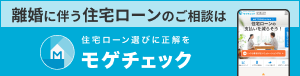年収600万円の配偶者と離婚してひとり親になる場合、養育費の相場は0歳から14歳までの子2人までなら1人につき5万円から6万円が相場です。
これは家庭裁判所および弁護士が「年収別の標準的な暮らし向きと親子で共有するのに必要」と考える金額水準であり、決して高すぎるわけではありません。むしろ、進学プランや健康状態に応じて増額の余地があるくらいです。
世間一般に、年収600万円前後は「十分子育てできる収入水準」ですが、あれこれと理由をつけて子育て費用を負担しない元夫・元妻は珍しくありません。養育費相場だけでなく、その計算根拠や増減に至る事情も頭に入れておき、必要な額を確実に支払ってもらえるようにしましょう。
養育費の不払いに対処するために知っておきたいことは以下の関連記事をご覧ください。
離婚後の支出などに関して詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、年収600万円の元配偶者からもらえる養育費の相場

個別の事情を加味する前の養育費相場は、裁判所が公開する標準算定表にまとめられています。使用する際は、リンクにある表1~表9の中から、子の数と年齢層に対応したものを選びましょう。
ここで想定するのは、年収600万円の夫と離婚してシングルマザーになろうとする専業主婦の例です。上記表の解説を兼ね、個別事情を考慮する前の養育費相場を確認してみましょう。
(1)子1人の場合
子どもが1人の場合は、標準算定表にある表1または表2で養育費相場を確認できます。
縦軸で夫(=養育費の支払義務者)の年収、横軸で妻(=養育費の請求権者)の年収をそれぞれ取って確認すると、金額の相場は以下の通りとなります。
▼0歳~14歳の場合(表1)
6万円~8万円
▼15歳以上の場合(表2)
8万円~10万円
(2)子2人の場合
子どもが2人なら、標準算定表にある表3・表4・表5のいずれかで養育費相場を確認できます。
同じく、縦軸は夫・横軸は妻の年収をそれぞれ取ると、年齢の構成に応じて以下の通りとなります。
▼2人とも0歳~14歳の場合(表3)
10万円~12万円
▼15歳以上の子+0歳~14歳の子の場合(表4)
12万円~14万円
▼2人とも15歳以上の場合(表5)
12万円~14万円
(3)子3人の場合
子が3人なら、標準算定表にある表6から表9のいずれかで養育費相場を確認できます。
縦横の軸で年収を取り、同じようにチェックしてみましょう。
▼3人とも0歳~14歳の場合(表6)
12万円~14万円
▼15歳以上の子1人+0歳~14歳の子2人の場合(表7)
14万円~16万円
▼15歳以上の子2人+0歳~14歳の子1人の場合(表8)
14万円~16万円
▼3人とも15歳以上の場合(表9)
14万円~16万円
(4)子が4人以上の場合
子が4人以上の場合の算定表は用意されていないため、自分で計算してみる他ありません。
方法の詳細とその考え方は「養育費の相場の調べ方」で示しますが、ここでは4人の子のうち15歳以上の子は1人だけと想定し、会社員の夫に請求できるものとして計算します。
A.夫の収入のうち養育費の基礎となる部分
600万円×41%=246万円
B.Aのうち子の生活費に充てられる部分
14歳以下の子
=246万円÷(100+62×3+85×1)×62≒41万円
15歳以上の子
=246万円÷(100+62×3+85×1)×85≒56万円
子4人分の合計(年間)
=41万円×3+56万円=179万円
→親権者の年収はゼロのため、上記を元に養育費を算出
C.1か月あたりの養育費
179万円÷12か月≒14.9万円
(5)統計で見る養育費の相場
ここで紹介した養育費相場は理論値に過ぎず、実際に支払われる額は協議・調停の成り行きしだいです。
参考までに、厚労省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告を見てみましょう。
調査内容に養育費の金額は含まれていないものの、母子世帯の年間収入の状況から、子育て費用としてもらっている額をある程度まで分析できます。
▼母子世帯の平成27年の年間収入
平均収入:243万円
うち就労収入:200万円
平均世帯人数:3.31人
以上のデータから単純計算すると、養育費を含む平均就労外収入は43万円、世帯に含まれる子の平均人数は2.31人です。
必ずしも正確ではありませんが、シングルマザーが実家・元夫・自治体等からもらっている額は、子1人あたり年間およそ18万円(1か月あたり1.5万円)となります。
全額元夫から支払われた養育費だと考えてみても、相場には到底及びません。
ひとり親世帯にとって重要なのは「元配偶者に請求する額」だけではありません。
そもそも支払いに応じさせられるか、子の将来のためどこまで金額を増やせそうか、これらも重要だと分かります。
2、養育費の相場の調べ方│年収600万円ならこう計算する

実際にもらえる養育費を判断する上で、正確な計算方法の理解は欠かせません。
標準算定表を作成した裁判官から成る司法研究会は、以下1~3の順で適正額を割り出すとしています。
▼養育費算定の大枠(標準算定方式の内容)
- 夫婦各々の「基礎収入」を調べる
- 支払義務者につき「基礎収入に占める子の生活費」を調べる
- 1の比率を考慮し、2を按分する
計算方法のベースにあるのは、未成熟子を持つ親はいつでも自分と同水準の暮らしをさせるべきとする「生活保持義務」です。
以降、子の健やかな成長に欠かせない金額をどう調べるのか、順を負って詳しく紹介します。
(1)基礎収入の調べ方
基礎収入とは、給与明細や確定申告書に基づく「総収入」から「必要な経費」を差し引いた額を指しています。
経費には所得税・社会保険料・通勤にかかる費用等が含まれますが、実際にかかっている費用をそのまま採用するわけではありません。
大まかに以下の3費目に分け、統計から得られる一般的な金額を当てはめます。
経費の内訳 | 範囲 | 概要 |
公租公課 | 所得税・住民税・社会保険料 | 法律で決められた割合に基づく理論値を採用 (相場は総収入の8%~35%) |
職業費 | 通勤交通費やスーツ代等 | 家計調査年報(リンク)の年間収入階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出から平均数値を採用※ (相場は総収入の13%~18%)
|
特別経費 | 住居関係費と火災・地震・損害・医療保険料 | 実費を控除 (相場は総収入の14%~20%) |
計算で最終的に得られる「総収入に占める基礎収入の割合」は、所得水準と働き方に合わせ、概ね一定範囲に収まると考えられています。
実際の離婚協議・調停では、養育費の減額を狙った経費水増しが考えられますが、基準がある以上、支払義務者の言い分は通らないでしょう。
日弁連の研究はさらに一歩進み、所得水準に応じた基礎収入割合の相場を細かく評価しています。
左記の資料によれば、年収600万円の基礎収入の相場は次の通りです。
▼給与所得者(サラリーマン)の基礎収入例
600万円×41%=246万円
▼事業所得者(会社経営者やフリーランス)の基礎収入例
600万円×53%=318万円
【参考】年収100万円のパート主婦(主夫)の基礎収入例
100万円×50%=50万円
(2)子の生活費の調べ方
子の生活費に関しては、やはり現在の実費をそのまま採用するのではなく、親子の「生活費指数」を用います。
支払義務者=別居親の基礎収入を「親子同居を続ける場合の生活費指数の合計」として、子の指数分の金額を割り出す方法です。
指数は年齢別に定められており、最新の指定は下記の通りです。
いずれも公立学校の教育費を含んでおり、生活保護費の給付基準をベースとしています。
▼生活費指数
親:100
子(~14歳):62
子(15歳~):85
仮に、年収600万円台の会社員男性と離婚し、14歳以下の子2人を女手ひとつで育てる……と想定してみましょう。
元夫の基礎収入が日弁連の相場通り(=246万円)なら、うち子の生活費は次のようになると計算できます。
子1人あたりの生活費
=246万円÷(100+62×2)×62
≒68万円
子全体の生活費
68万円×2
=136万円
(3)養育費計算の最終ステップ【収入比率に応じた按分】
子を養う義務は両親にあります。養育費の請求権者=同居親にも収入があるのなら、子の生活費は出来る範囲で負担すべきです。
以上の考え方に基づき、養育費の最終調整は、子の生活費を両親の基礎収入比率に公平に分配する方法で行います。基本の計算式は以下の通りです。
▼養育費調整のための計算式
子の生活費×(支払義務者の基礎収入÷元夫婦の基礎収入の合算)
=年間の養育費
ここでもう一度、14歳以下の子2人を抱えて年収600万円の会社員男性と別れる例を考えてみましょう。
元夫からもらうべき養育費の額は、年間で概ね以下のようになります。
【例1】もらう側が専業主婦の場合
→136万円
計算式:136万円×{246万円÷(246万円+0万円)}
【例2】もらう側が年収100万円の兼業主婦の場合
→113万円
計算式:136万円×{246万円÷(246万円+100万円×50%)}
3、養育費が相場より増減する理由【年収600万円の場合】

最終的に認められる養育費の金額には、子の進学予定・離婚後の生活の変化……といった個別の事情が反映されます。事情によって増える場合もあれば、反対に減らされる場合もあるのです。
もっとも、年収600万円であれば、経済苦を理由とする減額主張は通らないと考えられます。
全世帯平均所得約552万円・児童のいる世帯で約745万円(令和元年国民生活基礎調査の概況より)であることを考えると、世間一般には平均的~やや高所得と言えるからです。
それでは、養育費の増減に関わる要素とは何でしょうか。まずは増額事由から検討します。
(1)増額事由
支払義務者の年収が600万円前後である場合、主な増額事由は「子の状況」です。
一般的な子育て費用にこだわることなく、高額化する合理的な理由があれば、健やかな成長に必要な金額が認められるのです。
典型的な養育費の増額事由としては、以下の①・②の2つが考えられます。
①教育費がかかる【塾代・私立学校の授業料等】
塾や私立学校に通うための教育費や学費は、離婚前にそれらに通わせることについて同意していた場合、養育費にプラスして負担してもらえるのが原則です。
進学予定の合理性を巡って意見が対立する時は、支払う側の収入・学歴・地位などから判断します。
実際のところ、合理性に関してそれほど厳密な判断は行われません。
離婚前から両親揃って子の教育計画を容認する姿勢を見せていただけでも、養育費の増額は実現可能な場合が多いです。
②医療費がかかる【事故・障がい・病気等】
怪我や病気、あるいは障がいのために医療支援を必要とする子に関しても、かかる費用を養育費として分担してもらえます。
離婚協議や調停でよくあるのは、別居が長期化したせいで子の医療費の現状を理解してもらえないケースです。
確実に増額できるよう、事前に診療明細や医師の意見書を揃え、具体的な金額を証明できるようにしたいところです。
(2)減額事由
離婚した夫婦に増収が見られない限り、年収600万円の元夫(元妻)の負担する養育費が減る理由として「新たにもうけた子の存在」が考えられます。
生活保持義務に基づいて親の基礎収入で暮らせるのは、何も最初の結婚でもうけた子だけとは限りません。
ここで紹介する関係の子にも養育費が発生し、結果として元配偶者の子のもらえる分が少なくなってしまう場合があるのです。
①再婚相手との間に子をもうけた
再婚して生まれた実子には、離婚した相手との子と同等の養育費をもらう権利が生じます。
再婚相手の連れ子は例外ですが、支払義務者と養子縁組して戸籍上の繋がりが出来ると、実子と同じく養育費請求権が認められます。
②不倫相手or離婚後の恋人との間の子を認知した
法律上、結婚しないまま生まれた子でも、認知届を出せば父親の実子扱いとなります。
したがって、不倫相手や養育費支払い中の恋人との間に子が生まれても、養育費の減額事由になり得ます。
4、年収600万円の夫と養育費を取り決める時のポイント

養育費相場と実際の子育て費用は、言うまでもなく必ずしも一致するとは限りません。
成長するまでいくらかかるのか、正確に分かるのは親である元夫婦だけです。
最も重要なのは、大人になるまで確実に支払ってもらえることです。離婚協議では以下のポイントを踏まえ、別れた後も協力して育児できるようにしましょう。
(1)子育て費用を試算しておく
まずやっておきたいのは、子が成熟するまでにかかる費用の試算です。
試算方法は自由ですが、衣食住にかかる費用・教育費・お小遣い・学資保険等の掛金の4費目に分けて金額を出すとスムーズです。
判断が難しければ、気兼ねなくファイナンシャルプランナーや自治体窓口を頼りましょう。
理想を言えば、子育て費用の試算結果は夫婦で共有しておきたいところです。
請求する養育費の金額の根拠を明らかにしておけば、支払義務者が抱きがちな「余分に請求されているのではないか」との疑いを晴らせます。
請求権者にとっても、子の成長にかかる費用が予想外に増えた時、経緯を知る支払義務者との間で増額相談をスムーズに進められるメリットがあります。
(2)公正証書で約束させる【協議離婚の場合】
養育費の請求で一番大切なのは、確実に約束した金額を支払ってもらえるかどうかです。
支払いの合意を取り付けた時は、なるべく「離婚給付等契約公正証書」を作って内容を載せるようにしましょう。
財産分与や親権等、夫婦関係の解消で必要な約束事を全て盛り込んだ書類です。
公正証書とは一定の事項(契約の成立など)について、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。
公正証書を作成したい時は、書面の原案を持って公証役場を訪ね、本人確認書類を提示して依頼する必要があります。
完成した書面はそのまま公証役場預かりとなり、内容に誤りや不正がないと保証されつつ、トラブル発生時には訴訟の判決と同等の効力を発揮します。
養育費の取り決めに関しては、作成する公正証書に「強制執行認諾文言」を付しておくと万全です。
分かりやすく言い換えるなら、支払義務者に「約束を破った時はただちに差押え等を始めても構わない」と同意してもらい、その一文を書面に記載します。
上記の文言があれば、判決(=債務名義)などを得なくても、万一の時すぐに元配偶者の銀行口座や給与等を押さえられます。
養育費の速やかな回収に繋がるのは当然、不払い自体を未然に防ぐ効果も期待できます。
(3)協議が調わない場合は調停・審判へ
ほとんどの夫婦は家庭での話し合いだけで離婚の合意に至っていますが、養育費の面でどうしても折り合いがつかなければ、躊躇わずに離婚調停に臨みましょう。
家庭裁判所での話し合いに不安があれば、弁護士にサポートしてもらえます。
調停してもなお対立が続く場合は、裁判所に公平な結論を出してもらう「審判」に進み、時間はかかるものの訴訟で決着をつけることも可能です。
(4)面会交流でモチベーションを維持する
養育費を支払う側特有の心理として、離れて暮らす以上、子育ての実感が湧きにくいと言わざるを得ません。
日が経つにつれて段々と支払いが“無駄”と思うようになり、途中で送金がなくなるリスクがあります。
そうした先々のトラブルを見越して、定期的に子とコミュニケーションをとる機会を設けておきましょう。
離婚する時に面会交流の頻度や内容を決めておき、それを誠実に履行することで、養育費負担の意欲低下を防げます。
5、養育費の金額に影響を与えない要素【年収600万円の場合】

年収600万円と決して収入が低くない状況でも、あれこれと理由をつけて養育費の支払いを渋られるケースは珍しくありません。
特に揚げ足を取られやすいのは、請求権者側の就労によるものでない収入です。
結論として、以下のような収入・資産は、基本的に養育費の計算に含めなくて良いものと考えられます。
(1)財産分与の状況
離婚の際の財産分与は、同時に話し合う養育費に何ら影響しません。
前者はあくまでも夫婦が互いに負う義務(民法第798条)、後者は親が子に対して負う義務(民法第877条第1項)とのように、切り離して考えなくてはならないのです。
(2)支払義務者の減収
仮に「収入が減って養育費の支払いが苦しい」と言われても、ただちに減額に応じる必要はありません。
養育費の判断で着眼点となっているのは、年収600万円を維持できるかどうかではなく、支払義務者の生活レベルです。
減収の幅が小さく、別居親自身の暮らしぶりに変化がないのなら、養育費を減らす理由は見当たりません。(「家事抗告審からみた家事審判」58 巻7号20頁)。
(3)公的給付・実家の援助
ひとり親世帯には、児童手当の他にさまざまな公的給付制度があります。実家に余力があれば、孫のためにいくらか援助してくれるでしょう。
こうした経済的支援を理由に「十分な収入がある」として養育費の減額を言い出される場合があるものの、やはり応じる必要はありません。
それぞれの支援の性格を押さえれば、相手の言い分は間違っていると分かります。
①公的な子育て支援金
児童手当・児童扶養手当・市区町村が独自で給付する就学支援金等の制度は、個別にひとり親の収入を補う目的のものではありません。
政策として平等に育児を応援するための給付であり、養育費や就労収入とは別にもらっていいものです。
②生活保護費
生活保護とは、養育費・就労収入・実家からの経済的支援等を最大限得た上で、なお足りない時に補ってもらう制度です。養育費をもらってから生活保護費を計算するのが正しい順番で、その逆にはなり得ません。
③実家からの援助
実家の経済的支援は、相手の都合しだいです。好意と老後資金の余力の範囲で行われ、孫が成人するまで援助してくれる保証はどこにもありません。
祖父母世代の仕送りをひとり親の収入とみなすのは、いささか無理があります。
まとめ
ひとり親世帯がもらえる養育費は、両親の年収に応じて変化します。
元配偶者の年収が600万円だと、その半額前後が親子の生活費にあたる「基礎収入」です。
これを親子の生活費指数で分割してみると、概ね子1人あたり6万円から8万円程度となり、ひとり親になる側に就労収入がなければ満額もらえます。
最後に改めて、子の数に応じた養育費の相場を整理します。実際には進学プラン等や健康状況に応じて金額の加算があるため、離婚する夫婦ごとにしっかり話し合って決めましょう。
- 子1人の場合…6万円~10万円
- 子2人の場合…10万円~14万円
- 子3人の場合…12万円~16万円
- 子4人以上の場合…標準算定方式に沿って個別に計算