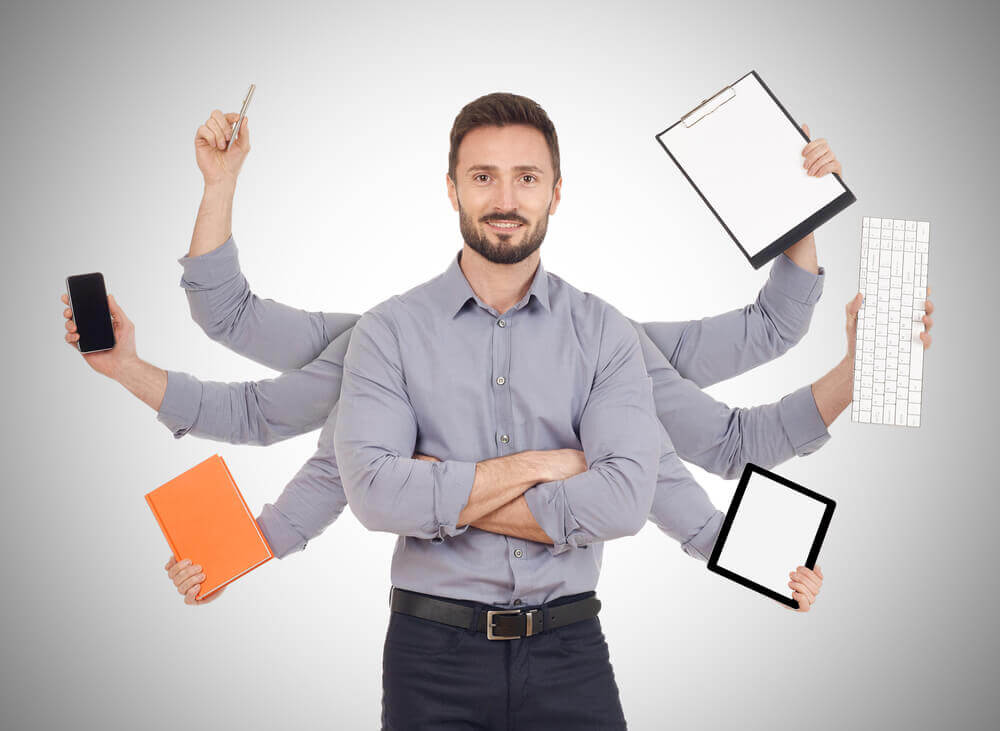後見人とは一体どういう人のことを指しているかご存知ですか?
- 親が認知症になったら財産管理はどうしたらいい?
- 親の介護問題が待ったなし…いったい何から始めたらいい?
- 将来の遺産相続に向けて今からやっておくべきことは?
こうしたお悩みをお持ちの方におすすめの方法が「後見人制度」の活用です。
後見人制度とは、簡単にいえば「認知症や病気になってしまった本人の代わりに、財産の管理をできるようにする制度」のことをいいます。
例えば、親が認知症になる前に子供である自分を後見人にしておいてもらい、実際に認知症になってしまったときは自分が財産の管理を代行できるようにしておく、といった活用方法が考えられます。 (後見人に選任してもらうためには、家庭裁判所に申し立てを行います)
今回は、
- 後見人制度とはどういうものか
- 親族の後見人になるにはどういう手続きをする必要があるのか
- 成年後見人の権利と義務は
といった内容について具体的に解説いたします。
後見人制度は、高齢化社会の到来にともない今後利用が増えていくでしょう。
この記事が、親の介護や相続問題にお悩みの方の参考になれば幸いです。
相続に関して詳しく知りたい方は以下リンクからページに飛ぶことで詳しく知ることができます。
目次
1、後見人とは?
後見人とは、判断能力が不十分な人に代わって契約などの法律行為をする人のことで、法律上は次の2種類の後見人があります。
- 未成年後見人
- 成年後見人
それぞれの意味について、順番に見ていきましょう。
(1)未成年後見人
未成年後見人とは、親権者がいないときに選任される未成年者の「保護者」です。
保護者たる未成年後見人は、未成年者の行為に対して以下の権利を有します。
- 包括的な代理権(その結果が未成年者本人に帰属する行為を本人のためになすことができる権利)
- 同意権(未成年者本人の行為に事前同意をする権利)
- 取消権(未成年者本人が事前に未成年後見人の同意を得ずにした行為を取り消す権利)
- 追認権(未成年者本人が事前に未成年後見人の同意を得ずにした行為を後から認める権利)
簡単にいえば、未成年者は保護者(親権者=親や未成年後見人)の同意がなければ何もできない、というわけです。
この制度の趣旨は、未成年者の保護です。 未成年者は法律上、正常な判断力が不足する者と位置づけられているため、これを補う者として「保護者」が必要というわけです。
(2)成年後見人等
成人であっても単独で判断することが難しい人について、その判断を手伝う制度が成年後見制度です。
単独で判断が難しい人たちを類型化し、その類型ごとに、その判断を手伝う人を定型化しています。
単独で判断が難しい人たちとは、次の3つに類型化されています。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
このうちの「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(知的障害の方、認知症の方など。「成年被後見人」といいます。)を後見する者として定められているのが「成年後見人」です。(判断能力が著しく不十分である者を保佐する者は「保佐人」、判断能力が不十分である者を補助する者は「補助人」と呼ばれます)
成年後見人は、このような方(成年被後見人)の行為に対して以下の権利を有します。(保佐人、補助人の権限は異なります)
- 包括的な代理権(その結果が本人に帰属する行為を本人のためになすことができる権利)
- 取消権(本人が事前に成年後見人の同意を得ずにした行為を取り消す権利)
- 追認権(本人が事前に成年後見人の同意を得ずにした行為を後から認める権利)
成年後見人は未成年後見人では有していた「同意権」はありません。なぜでしょう?
それは、事前に同意を与えて単独で行為をできるとしても、判断力を欠く「常況」にある成年被後見人にとっては逆にその保護にはならないからです。
つまり、成年被後見人は自分一人では基本的には法律行為等をできず、成年後見人がほぼ全ての行為を代わって行うということになります。
この記事では、成年後見人に焦点に絞り、以下、解説していきます。
2、成年後見人の権限に制限はあるの?
「成年後見人がほぼ全ての行為を代わって行う」とお伝えしました。
こうなると、成年後見人が悪いこともできてしまいます。
たとえば成年被後見人の財産を自分のために使ってしまうなどです。
これでは本人のために作られた成年後見制度は本末転倒!
そこで、次のようなルールが規定されています。
(1)日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない(民法第9条但書)
電気料金を支払うといったような行為については、成年後見人は取り消すことができません。
このような行為まで取り消すことができてしまうと、電気会社等としては、取り消しを懸念して電気を供給しない等という判断に至ってしまう可能性があります。
日常生活に関する行為について、その行為の相手が取り消しを懸念して相手にしてくれないとなると、成年被後見人の生活が大きく制約されてしまいます。
そのため、日常生活に関する行為については取り消すことができないとされているのです。
(2)取り消しは本人もできる(民法第120条第1項)
取り消しは成年被後見人本人もできます。
本人が勝手に取り消した、という場合でも、その取り消しは有効です。
(3)居住用不動産の処分を代理するときは、家庭裁判所の許可が必要(民法第859条の3)
居住用不動産の処分については、成年後見人による間違った判断がされた場合の本人にとってのダメージは大きなものとなります。
そのため、第三者である家庭裁判所がその処分の意味や利益について判断し、許可を出さなければすることができないとなっているのです。
(4)成年被後見人単独で一定の有効な行為ができる
成年被後見人は、単独でなし得るものが全くないことはありません。
以下の3つの行為は単独でなしても有効です。
- 婚姻 結婚は本人の意思でできます。成年後見人が取り消すことはできません。
- 認知 認知も本人の意思でできます。成年後見人が取り消すことはできません。
- 遺言 遺言は、医師2名以上の立会いが必要となりますが、本人の意思でできます。成年後見人が取り消すことはできません。
(5)利益相反行為はできない(民法第860条、826条)
利益相反行為とは、代理権を行使する場面で問題になります。
成年後見人自身としての立場と、本人の代理人としての立場の利益が相反することになる行為はできない、ということです。
たとえば、本人Aさんの成年後見人であるBさんが、本人AさんからAさんの不動産を買う、という契約をしようとするとき、売主のAさんの利益を考えると値段はなるべく高くしたいはずであり、買主のBさんの利益を考えると値段はなるべく安くしたいはずです。
そのため、BさんがAさんの代理人になって売買をした場合、Aさんの利益よりも自分の利益を優先してしまいBさんの利益を害することが考えられます。
このようなことから、成年後見人は、利益相反行為をすることはできません。
(6)代理権の濫用は無効
「濫用」とは、権利に基づく行使ではあるものの、不適切な行使である場合です。
たとえば、認知症の親の金銭をむやみに第三者へ贈与するようなケースでは、親の金銭の処理についての代理権はあるけれども不適切な行為であるとして、代理権濫用として結局無効とされる可能性があります。
あくまでも「本人のため」の権利行使が必要です。
3、成年後見人の仕事とは?
成年後見人は、預貯金や不動産の管理など、主に成年被後見人の財産に関して行動します。
では以下のことは成年後見人にどのような責任があるのでしょうか。
(1)介護や食事の世話
成年後見人がすべきことは、管理行為や契約締結などの「法律行為」です。
そのため、介護や食事の世話を直接行う義務はありません。
ただし、本人の生活を支援することは求められており、医療に関する契約を締結したり、病院の処遇をチェックしたりすることが必要です。
(2)手術の同意
成年後見人としては、本人に代わって手術の同意をする権利はありません。
ただ、医療機関は家族の同意をもって手術を可能とする運用をとっているところが多いので、家族としての同意を求められることはあるかもしれません。
そのため、成年後見人の一存で手術を決定するのではなく、他の家族の意見を聞くなど、本人と他の家族・親族の意見を考えながら行動すると良いでしょう。
(3)高齢者の成年後見人になる場合は公的サービスを理解して
高齢者の成年後見人になる場合は、理解しておかなければならない公的サービスがいくつかあります。
しっかりと理解して積極的に活用してください。
- 年金制度:老齢年金、遺族年金など、さまざまな年金制度があります。どんな受給資格があるのか確認しておきましょう。
- 医療保険制度 :後期高齢者医療制度、高額医療費制度など、医療の出費で損をすることがないよう、確認しておきましょう。
- 介護保険制度 :介護保険や高額介護サービス費等、払い戻しなどを受けることができる制度です。介護はサービスを利用すると出費がかさみますので、必ず確認しておきましょう。
4、成年後見人は誰がどうやってなるの?
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対して「この人に成年後見人をつけたい、後見人にはこの人を選任してください」と、申立てを行う必要があります。
申立てを受けた家庭裁判所は本人の希望や家庭事情などを考慮したうえで、最終的に「後見開始の審判」を出します。
後見開始の審判が出された時点で、これらの審判を受けた本人が行う契約などの法律行為は制限されることとなります。
以下では、後見開始の審判が出されるまでの手続きの流れについて、くわしく見ておきましょう。
(1)成年後見人の申立て
成年後見開始の申立てでは、以下の内容を申立書に記載します。
- 申立人
- 本人
- 成年後見人候補者
- 申立ての理由
申し立てをすることができるのは、本人の他は以下の人となります。
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人(※被保佐人→成年被後見人に切り替える場合)
- 保佐監督人
- 補助人(※被補助人→成年被後見人に切り替える場合)
- 補助監督人
- 検察官
なお、上の一覧でいう「四親等内の親族」とは、本人から見ていとこにあたる人や、大叔父や大叔母よりも血縁的に近い親族の人を指します。(一般的な意味でいう「親族」に当たる人であれば、問題なく申立人となれるといえます)
(2)家庭裁判所が審理
後見開始の申立てが行われると、家庭裁判所は本人の事理弁識能力や家庭事情、財産の状況などについて審理を行います。
そして成年後見人を誰にするかも審理されます。
成年後見人は、破産手続きを行っている人や、過去に別件で後見人を解任されたことがある人、過去に本人と訴訟で争ったことがある人などは欠格者としてなることができません(なお、未成年者は後見人はなれません) 。
(3)家庭裁判所が審判(選任)
審理がつくされた段階で、家庭裁判所はもっとも適切と思われる成年後見人を選任します。
申立の際に成年後見人の候補者をあげていますが、必ずしもこの候補者がなるわけではなく、本人の利益を考えて家庭裁判所が誰にするかを判断し、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。
なお、成年後見人は本人よりも年齢的に若い人が選任される傾向がありますので、高齢の配偶者などは選任してもらえない可能性があることに注意しておきましょう。
(4)子などの親族がなった場合は後見監督人がつくことがある
成年後見人の選任に当たっては、さらにその人を監督する立場の「後見監督人」が選任されることがあります。
特に、本人の親族が後見人などになった場合には、こうした監督人がつく可能性が高いでしょう。
後見監督人が選任される場合、後見人となる人は後見監督人に対して定期的に報告を行う義務を負います。
成年後見人に選任された人には広範な権限が与えられますが、成年後見制度は基本的に本人の財産が侵害されないように保護するための制度ですから、成年後見人が本人の財産を自由に処分できるわけではないことを理解しておきましょう。
(5)後見人登記
成年後見人の選任が行われたら、その内容は法務局で登記されます。
登記されるのは、どの種別の成年後見制度を利用しているのかといったことや、家庭裁判所による審判の日時、成年後見人となる人の住所氏名などです。
5、成年後見人になっても財産の使い込みはできない!その仕組みとは
成年後見人の権限に制限がかかることはわかりましたが、誰にも見つからなければこんな制限などあまり意味はありません。
では財産の使い込みができない実際の仕組みはどのようになっているのでしょうか?
(1)家裁への定期的な「報告」
まず、成年後見人になった直後に、成年被後見人の財産及び収支予定を全て家裁に報告しなければなりません。
そしてその後も年1回のペースで報告が必要なのです。
このように、家庭裁判所による厳しいチェックにより財産を使い込むことは困難です。
(2)後見監督人への「報告」
親族が成年後見人になった場合は、その後見人を監督する「後見監督人」が選任されることがあります。
この後見監督人がついた場合は、家裁への報告とは別に、この監督人への報告も随時なされなければなりません。
事後的な報告のみならず、事前の許可が必要なケースもあります。
このように、後見監督人による厳しいチェックにより財産を使い込むことは困難だといえるでしょう。
6、成年後見人は報酬はもらえるの? 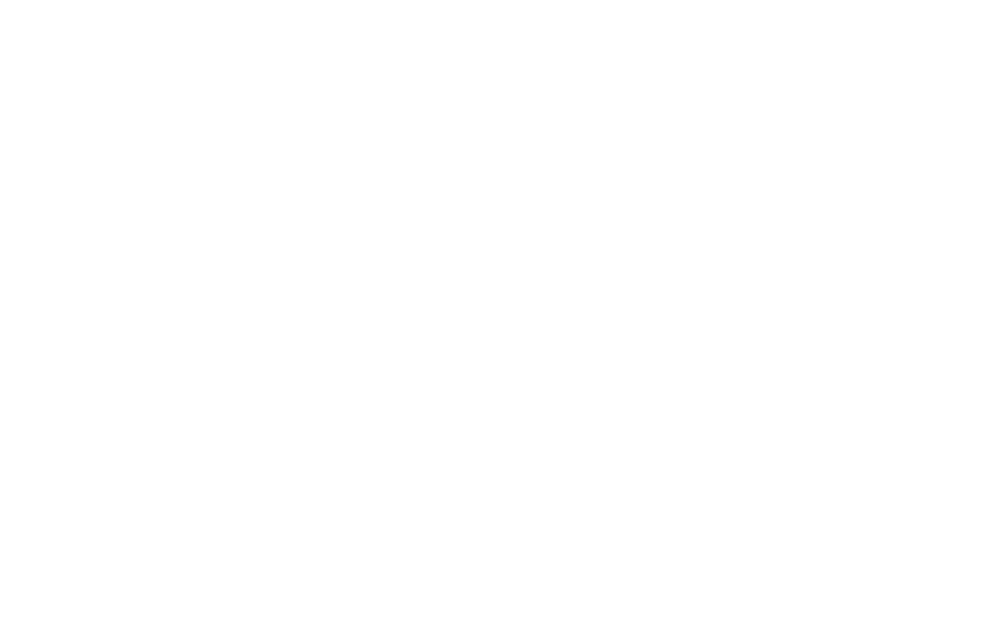
成年後見人は、以上の通り、やるべきことが増えるばかりで本当に大変な仕事です。
そのため、報酬をもらえることになっています。
報酬は無制限に成年後見人が決定できるものではなく、やはり家庭裁判所にその額の判断を仰ぐことになっています。
東京家庭裁判所では、報酬の目安を「月額2万円」と公表しています。
これは基本的な後見人としての仕事を行なった場合であり、複雑な管理が必要になるなどの特別な事情があれば、付加報酬が発生する場合もあります。
7、成年後見制度は誰に相談すればいい?
成年後見制度について不安や疑問点がある方は、下記のような相談窓口を利用しましょう。
成年後見制度は本人や親族の生活状況に大きな影響を与える選択肢ですから、利用にあたっては専門家のアドバイスを受けるようにしてください。
(1)自治体
市町村や都道府県などの自治体では、成年後見制度の利用に関する相談を受け付ける窓口が準備されています。
また、各自治体では「成年後見制度利用支援事業」という事業を設定しており、成年後見制度を利用するために必要な費用の補助などを行っています。
(2)弁護士・司法書士
弁護士や司法書士といった法律の専門家も、成年後見制度の利用に関するアドバイスを受け付けています。
成年後見制度の利用は多くのケースで遺産相続と密接な関係がありますから、必要な相続対策の一環として成年後見制度の活用が提案されるということもあるでしょう。
専門家はより広範な視野に立って成年後見制度の活用法やアドバイスをしてくれますから、ぜひ相談してみてください。
まとめ
今回は、成年後見制度の内容について解説いたしました。
成年後見制度は認知症などになってしまった親族の財産を守るために有効な方法です。
同居の親族がなるにはスピーディな対応が可能になるメリットはありますが、成年後見人になった親族は複雑な事務作業を背負うことになってしまいます。
このような場合は、ぜひ信頼できる専門家に委託する方法もご検討ください。