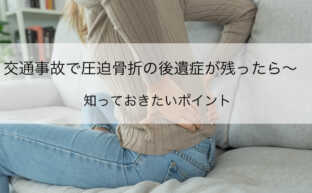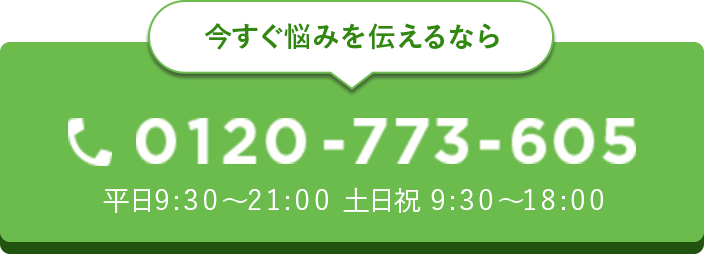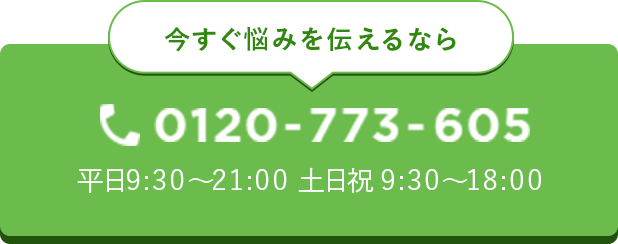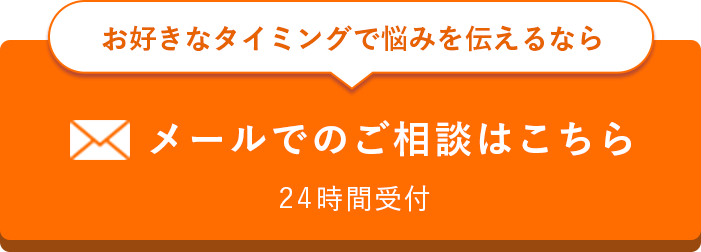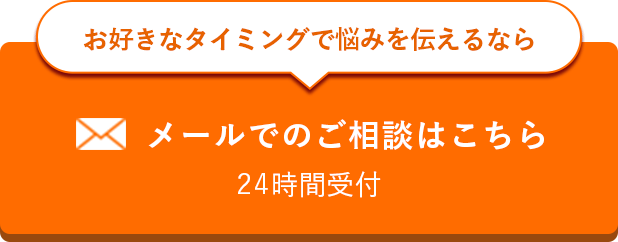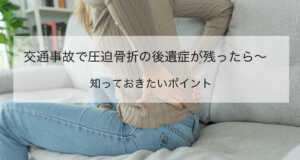
交通事故で腰椎や胸椎、頚椎などを圧迫骨折すると、治療を受けても後遺症が残ってしまうことがあります。
- 骨が変形したままになった
- 痛みなどの神経症状が残った
- 体を動かしにくくなってしまった
などの後遺症が残る場合には、障害の程度に見合った賠償金を請求すべきです。
ただ、後遺症で賠償金を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
- 実際に残った後遺症が何級の後遺障害に該当するのか
- その等級に見合う賠償金額はいくらか
などを巡って保険会社と意見が食い違うケースも少なくないので注意が必要です。
そこで今回は
- 圧迫骨折の後遺症で後遺障害等級は何級になる?
- 圧迫骨折で適正な後遺障害等級を獲得する方法
- 圧迫骨折の後遺症で保険会社と示談交渉する際の注意点
などについて、交通事故における後遺症の問題で解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
この記事が、交通事故による圧迫骨折の後遺症の賠償金が気になる方の手助けとなれば幸いです。
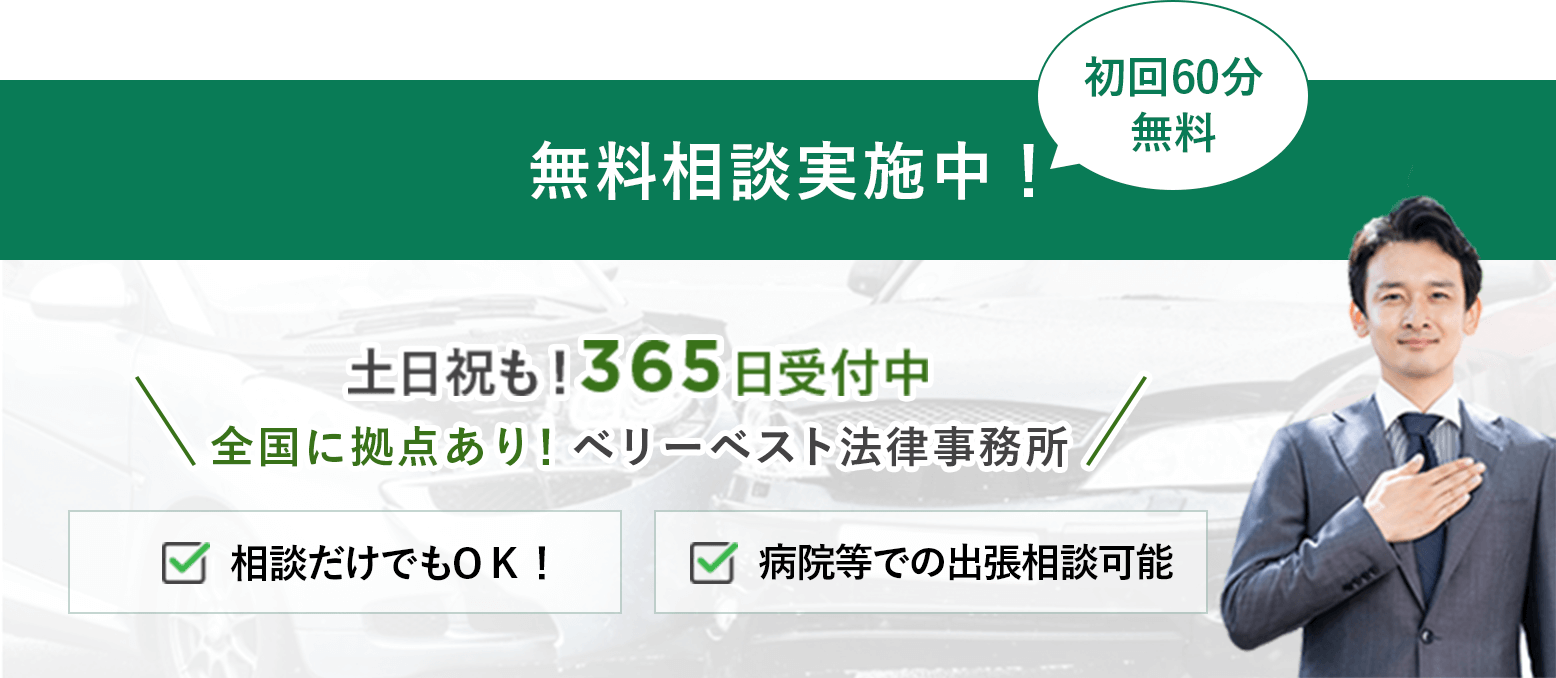

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、交通事故で後遺症が残りやすい「圧迫骨折」とは

損害賠償の問題を考える前に、まずは圧迫骨折とはどのようなものか、症状や発症原因、治療法などを知っておきましょう。
(1)骨が押しつぶされること
圧迫骨折とは、骨が2つに折れるのではなく、骨に強い力が加わって押しつぶされてしまう形の骨折のことです。
押しつぶされてしまった骨は元の形には戻らないことも多いので、交通事故で圧迫骨折をすると後遺症の賠償問題に発展しやすくなるのです。
(2)発症しやすい部位
圧迫骨折は体のさまざまな箇所で発生する可能性がありますが、特に発症しやすいのは、脊椎を構成している骨の中で、平べったい形をしている骨です。
脊椎とは簡単にいうと背骨のことで、
- 頚椎
- 胸椎
- 腰椎
- 仙骨
- 尾骨
で構成されています。
交通事故でも、これらの部位に強い力が加わった場合に圧迫骨折が生じやすくなっています。
(3)発症する原因
圧迫骨折は、平べったい骨に強い力が加わることで発症しやすいといえます。
その原因として、交通事故の他にも転倒した場合や、高いところから転落した場合を挙げることができます。
高齢者や骨粗鬆症などで骨がもろくなっている方の場合は、比較的弱い力でも圧迫骨折を発症することがあります。
(4)症状
圧迫骨折を発症すると、まず損傷した部位が強く痛みます。
骨が損傷しているので、じっとしていても痛みがありますが、その部位を動かすとさらに強い痛みが生じます。
さらに、骨が変形したことによって脊柱の中を通っている神経に影響を及ぼすこともあります。その場合には、
- 手足のしびれ
- 麻痺
- 排泄機能障害
などが生じることもあります。
(5)治療方法
圧迫骨折の治療方法としては、骨折した部位をできる限り動かさないようにして痛みが治まるのを待つ保存的療法が中心的です。
受傷直後はコルセットで患部を固定したり、鎮痛剤が処方されたりすることも多いです。
骨折の程度がひどい場合や、神経に重大な影響を及ぼしている場合には手術が行われることもあります。
(6)治療期間の目安
圧迫骨折の場合、神経に影響がなければ、概ね3ヶ月ほどで骨折した骨が結合し、痛みも軽くなると言われています。
ただし、それで治療が終了するとは限らず、リハビリが必要となることもあります。
後遺症が残る場合は、症状固定の診断を受けるまでに3ヶ月~6ヶ月程度の期間は必要になると考えておきましょう。
2、圧迫骨折で後遺症が残ったら後遺傷害等級認定は受けられる?

それでは、圧迫骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定は受けられるのでしょうか。
圧迫骨折の後遺症にはいくつかの種類がありますので、症状ごとにみていきましょう。
(1)そもそも後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、交通事故によるケガで後遺症が残った場合に、公平かつ適正な賠償金が支払われるように、専門機関の審査によって14段階に分けられた後遺障害等級の何級に該当するのかを認定してもらうことをいいます。
後遺症とは、ケガや病気で治療を受けても完治せずに残ってしまう症状のことです。
後遺症には症状が重いケースから軽いケースまでさまざまなものがあり、なかには損害賠償の対象とならない軽いものもあります。
損害賠償の対象となるケースでも、症状の内容や程度に応じて適正な賠償金額は異なってきます。
そこで、同程度の症状が残った被害者は同水準の賠償金を受け取れるように、14段階の後遺障害等級が定められていて、専門機関の審査によって何級に該当するのか、あるいは後遺障害に該当しないのかが認定されるのです。
訴訟によって後遺障害等級を立証することも可能ですが、通常、まずは「損害保険料率算出機構」という機関で後遺障害等級の認定を受け、その結果に基づいて保険会社と示談交渉を行います。
基本的には、交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けなければ後遺症に関する賠償金は受け取れないと考えておきましょう。
(2)変形障害がある場合
圧迫骨折による変形障害とは、骨折した骨が元通りの形に結合せず変形した状態で結合してしまう後遺症のことです。
後遺障害としては、以下の等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 障害の内容・程度 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
後遺障害等級は、数字が小さいほど障害の程度が重いものとして設定されています。
①6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」
6級5号の「脊柱に著しい変形を残すもの」に認定されるのは、X線等の画像で脊椎の圧迫骨折が確認できる場合で、かつ、次のいずれかに該当すると認められる場合です。
- 2個以上の椎体の前方椎体高の合計が、後方椎体高の合計よりも1個分以上減少し、脊椎の前方へ折れ曲がっている場合
- 1個以上の椎体の前方椎体高の合計が後方椎体高の合計よりも50%以上減少し、脊椎の横方向への折れ曲がりがコブ法で50度以上である場合
簡単に言うと、圧迫による骨の変形の度合いが極めて大きく、一定の基準を超える場合ということになります。
②8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」
8級相当の「脊柱に中程度の変形を残すもの」に認定されるのは、X線等の画像で脊椎の圧迫骨折が確認できる場合で、かつ、次のいずれかに該当すると認められる場合です。
- 1個以上の椎体の前方椎体高が減少して後彎が生じた場合
- 側彎度がコブ法で50度以上である場合
- 環椎または軸椎が変形・固定した場合で、それによって次のいずれかに該当する場合
1. 60度以上の回旋位となっているもの
2. 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
- 側屈位となっており、X線写真等により矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
8級相当の「脊柱に中程度の変形を残すもの」をより簡単に表現すると、
- 変形の程度が6級の場合よりは小さいものの
- 一定の基準を超える変形が認められる場合
といえます。
③11級7号「脊柱に変形を残すもの」
11級7号の「脊柱に変形を残すもの」に認定されるのは、変形の程度が6級や8級の基準に至らない場合で、以下のいずれかに該当する場合です。
- 圧迫骨折等が残っていることがX線写真等で確認できる場合
- 脊椎固定術が行われた場合(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合は除く)
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた場合
(3)運動障害がある場合
圧迫骨折による運動障害とは、骨折した部分やその周辺の部位の可動域が狭くなることです。簡単に言うと体を動かしにくくなる後遺症のことです。
後遺障害としては、以下の等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 障害の内容・程度 |
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
①6級5号「脊柱に著しい運動障害を残すもの」
6級5号の「脊柱に著しい運動障害を残すもの」に認定されるのは、以下のいずれかによって頚部および胸腰部に強直が認められる場合です。
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに圧迫骨折等が残っており、X線写真等で確認できる場合
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた場合
- 項背腰部(うなじ、背部、腰部)の軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合
強直とは、分かりやすくいうと、ほとんど動かせない状態のことです。
②8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」
8級2号の「脊柱に運動障害を残すもの」に認定されるのは、以下のいずれかに該当し、頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限された場合です。
- 頚椎または胸腰椎に圧迫骨折等を残しており、X線写真等で確認できる場合
- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた場合
- 項背腰部(うなじ、背部、腰部)の軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合
参考可動域とは、分かりやすくいうと、健康な人が一般的に動かすことができる範囲のことです。
(4)荷重機能障害がある場合
圧迫骨折による荷重機能障害とは、骨折の影響により、患部より上の体幹を支えられなくなった後遺症のことです。
後遺障害としては、以下の等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 障害の内容・程度 |
6級相当 | 頚部および腰部の両方の保持が困難であるもの |
8級相当 | 頚部または腰部のいずれかの保持が困難であるもの |
6級と8級の違いは、
- 頚部と腰部の両方の保持が困難となっているか
- どちらか一方にとどまるか
です。
(5)神経症状がある場合
圧迫骨折による神経症状とは、骨折が治ったか症状固定した後も、骨折した部位や手足などに痛みやしびれが残る後遺症のことです。
後遺障害としては、以下の等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 障害の内容・程度 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級と14級の違いは、
- 神経症状の原因が医学的に「証明」可能な場合が12級
- 証明できないが「説明」可能な場合は14級
となります。
X線写真等で骨の変形や神経の損傷が確認できる場合は12級に認定される可能性が高くなります。
そのような確認ができなくても、治療経過や症状の経過などから、その神経症状が交通事故を原因として生じたものであると医学的に説明できる場合は、14級に認定される可能性があります。
3、圧迫骨折で後遺障害等級認定を受けた場合に請求できるもの

後遺障害等級の認定を受けた場合には、
- それまでの治療費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
等とは別に、次の2つの賠償金を請求することができます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
以下で、それぞれ具体的にご説明します。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によるケガが治らず障害が残ったことによって、今後の日常生活や仕事が制限されるために受ける精神的苦痛を慰謝するために支払われる賠償金のことです。
後遺障害の程度が重いほど精神的苦痛も大きいと考えられるので、慰謝料額は後遺障害等級に応じて定められています。
もっとも、慰謝料の算定基準には
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
の3種類があり、それぞれ設定されている金額が異なります。
圧迫骨折で請求できる可能性がある後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。
ただし、任意保険基準の金額は非公開のため、以下の表ではあくまで推定値を掲載しています。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
6級 | 512万円 | 600万円 | 1,670万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
(2)後遺障害逸失利益
交通事故によるケガで後遺障害が残ると、一般的に労働能力が低下し、収入が下がると考えられます。
そこで、事故に遭わなければ将来に得られたであろう利益との差額について、後遺障害逸失利益として賠償請求できます。
金額は、次の計算式で求められます。
【基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】
基礎収入額は、基本的に事故に遭った前年の年収額となります。
労働能力喪失率は、以下のように後遺障害等級に応じて定められています。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
6級 | 67% |
8級 | 45% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
14級 | 5% |
ライプニッツ係数とは、中間利息を控除する計算を行う際に用いられる数値のことです。
逸失利益の賠償では、本来なら将来に受け取るはずの金銭が前払いされます。
お金は利息を生むものと考えられているので、将来の運用益は差し引かなければなりません。
その計算を行うために用いる一定の数値がライプニッツ係数です。
その数値は労働能力喪失期間(基本的に67歳-症状固定時の年齢)に応じて定められており、年齢が若ければ若いほど大きな数値となります。
一例として、次のケースで後遺障害逸失利益を計算してみましょう。
- 交通事故による圧迫骨折で変形障害が残った
- 後遺障害等級第11級7号に認定された
- 症状固定時40歳
- 事故前年の年収は500万円
(計算式)
基礎収入額500万円×労働能力喪失率20%×27年に相応するライプニッツ係数18.327=1832万7000円
このケースでは、1832万7000円の後遺障害逸失利益を請求できます。
4、圧迫骨折の後遺症で後遺障害等級認定を受ける方法

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を受け取るためには、後遺障害等級認定を受けなければなりません。
ここでは、その方法をご紹介します。
(1)後遺障害等級認定申請の流れ
後遺障害等級認定を受けるには、損害料率算出機構というところに認定申請を行います。
申請するまでの流れは、以下のとおりです。
- 症状固定になるまで治療を受ける
- 後遺障害診断書を発行してもらう
- 必要書類をそろえて申請をする
治療中に保険会社から「そろそろ治療費を打ち切りたいので症状固定にしてほしい」と打診されることがありますが、医師が症状固定と診断するまで治療を続けることが大切です。
症状固定の診断時には、後遺障害診断書が発行されます。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査資料の中で最も重要な書類です。
受け取ったら内容を確認し、記載内容が不十分な場合は追加の検査などを検討すべきこともあります。
申請方法には、
- 事前認定
- 被害者請求
という2つの方法があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社の担当者に後遺障害診断書を渡して、後の手続きを一任する方法です。
被害者請求は、必要書類をすべて被害者自身がそろえて、加害者側の自賠責保険会社へ提出し、損害保険料率算出機構での審査を受ける方法です。
被害者請求では充実した審査資料を提出することができるので、被害者請求で申請した方が有利な結果が得られやすい傾向にあります。
(2)後遺障害等級に認定されなかった場合の対処法
後遺障害等級認定の申請を行った場合であっても、非該当(後遺障害に該当しない)と判断されたり、思ったよりも低い等級に認定されたりすることもあります。
認定結果に納得できない場合は、異議申し立てを行うことで、再審査をしてもらうことができます。
後遺症の程度が軽いために非該当となることもありますが、審査資料が不足している、後遺障害診断書などの記載が不十分であるために不利な認定を受けるケースも少なくありません。
そういった場合には異議申し立てを行い、審査資料を補充して再審査を受けることが大切です。
当初の申請を事前認定で行った場合でも、異議申立ては被害者請求の方法で行うことができます。
ただ、被害者請求の手続きは複雑ですので、もし、不利な認定を受けたら弁護士に相談の上、被害者請求で異議申立てを行うことをおすすめします。
5、圧迫骨折で保険会社と示談交渉する際の注意点

後遺障害等級の認定結果が適正であるかどうかを素人が判断することは、非常に難しいものです。
そのため、弁護士に相談しないまま保険会社との示談交渉を始めると、不当に低い金額で示談してしまうおそれがあります。
圧迫骨折の後遺症の場合は、示談交渉の際に以下の点に注意しましょう。
(1)変形が小さいため非該当とされるケース
圧迫骨折による変形障害では、変形が小さくてもX線写真等で変形が認められる場合は11級の後遺障害等級に認定されるはずです。
しかし、実際にはわずかな変形の場合は非該当とされるケースもあり、異議申し立てをしても損害保険料率算出機構の判断が変わらないこともあり得ます。
そのような場合であっても、神経症状によって12級または14級の後遺障害等級を獲得できるケースは少なくありません。
保険会社から後遺障害を否認された場合は、弁護士に相談して、後遺障害の見落としがないかを確認すべきです。
(2)運動障害があるのに変形障害しか認定されないケース
圧迫骨折で骨が変形したまま結合し、さらに腰が動きにくくなるなどの運動障害が残った場合は注意が必要です。
運動障害が認定されると後遺障害等級は6級または8級となりますが、運動障害が見過ごされてしまい、変形障害のみで11級に認定されるケースがあるからです。
骨の変形はX線写真等で確認されやすいですが、運動障害については可動域に関する検査が必要で、十分な検査が行われていない場合にこのようなトラブルが起こり得ます。
この場合は、再検査を十分に受けた上で、後遺障害等級認定の異議申し立てを行う必要があります。
(3)職種によって逸失利益を否認されるケース
圧迫骨折の変形障害で11級の後遺障害等級の認定を受けた場合でも、事務職などのケースでは、労働能力には影響がないという理由で保険会社が後遺障害逸失利益を否認することがあります。
たしかに、後遺障害の内容や程度、職種によっては裁判でも後遺障害逸失利益が減額されるケースはあります。しかしながら、慢性的に痛みが続く以上、集中力の低下などで労働能力に影響することは否定できないので、安易に後遺障害逸失利益を否認することには問題があります。
この場合は、実際にどのような症状が残っていて、仕事にどのような支障をきたしているのかを明らかにして、保険会社と交渉することになります。
6、圧迫骨折による後遺症の損害賠償請求で弁護士に依頼するメリット

圧迫骨折で後遺症が残った場合の損害賠償請求は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
交通事故の損害賠償請求の経験が豊富な弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
(1)適切な後遺障害等級の獲得が期待できる
後遺症が残った場合は、何級の後遺障害等級に認定されるかによって、受け取れる賠償金額が大きく異なってきます。
適切な後遺障害等級を獲得するためには、被害者請求で申請することが有効です。
しかし、被害者請求の手続きは複雑であり、書類に不備や不足があると、かえって不利な結果にもなりかねません。
弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きを代理してくれますので、適切な後遺障害等級の獲得が期待できます。
(2)保険会社との交渉を任せられる
弁護士に依頼すれば、代理人として保険会社との交渉を代わりに行ってくれます。
被害者自身は保険会社と直接やりとりする必要がありませんので、示談交渉に時間や労力をとられることがなくなります。
また、弁護士が高度な専門知識と交渉力で的確に交渉してくれますので、有利な内容で示談することも期待できます。
(3)高額の慰謝料獲得が期待できる
任意保険会社は、当然ながら任意保険基準で慰謝料額を計算して示談案を提示してきます。
高額な弁護士基準で計算した慰謝料額を獲得するためには、基本的に裁判をする必要があります。
しかし、弁護士に依頼すれば、示談でも弁護士基準で計算した慰謝料額が支払われる可能性もあります。
そのため、弁護士に依頼するだけで賠償金の額がアップすることも期待できるのです。
まとめ
交通事故による圧迫骨折で後遺症が残った場合、適正な賠償金を受け取るためには、症状固定に至るまで治療を継続し、適切な後遺障害等級を獲得して、その後に保険会社との示談交渉を有利に進めなければなりません。
専門的な知識がなければ、これらの各ポイントにおいて損をしているにもかかわらず、そのことに気づかないまま示談に応じてしまうことになりかねません。
被害者の方が専門知識や交渉力の不足を補い、納得のいく結果を得るためには、弁護士の力を借りることが最も有効です。
お困りの際は、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。