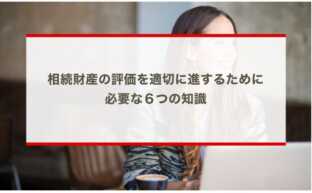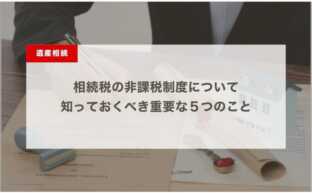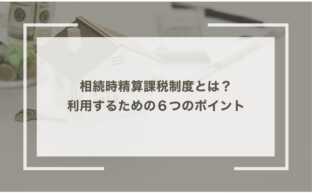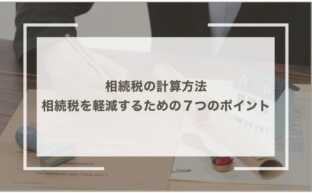遺産を相続すると、相続税がかかることがあります。
それは分かっていても、どのくらいの遺産があれば相続税がかかるのかや、相続税の計算方法などを具体的にご存じの方は多くないかもしれませんね。
相続税がかかる人の割合は低いですが、かかる場合には税額が意外に高額となってしまうケースも少なくありません。
そのため、節税対策も重要になってきます。
そこで今回は、
- 遺産を相続したときにかかる「相続税」とは
- 相続税の計算方法
- 相続税の節税方法
などについて、相続税に精通したベリーベストの税理士の監修の元で解説していきます。
その他にも、相続税の申告方法や申告期限、相続税が払えないとき・払いすぎたときの対処法もご説明しますので、相続税に関して悩みを抱えるすべての方の手助けとなれば幸いです。
1、相続税とは?〜遺産の相続にかかる税金

相続税とは、その名のとおり遺産の相続にかかる税金ですが、遺産相続のすべてのケースで相続税がかかるわけではありません。
まずは、相続税はどのような遺産に対してかかるのか、また相続税がかかる人の割合はどれくらいなのかについて解説します。
(1)相続税は課税対象財産に対してかかる
相続税は、遺産のすべてに対してではなく、遺産のうち「課税対象財産」に対してかかります。
また、相続人一人一人の相続額についてかかるものではなく、課税対象財産の全体に対して相続税がかかり、各相続人の相続分に応じて一人あたりの納税額が決まります。
相続税の具体的な計算方法は次項でご説明することとして、ここでは課税対象財産の算出方法をご説明します。
(2)課税対象財産の算出方法
遺産の中には、そもそも非課税となる財産や、相続税の計算の際に遺産から差し引ける財産もあれば、民法上は相続の対象でなくても税法上は相続財産として扱われる財産もあります。
そこで、相続によって取得した財産(遺産全体)から上記の各財産を差し引いたり加えたりして、課税対象財産を求めることになります。
具体的には、次の計算式にそれぞれの金額を当てはめることによって算出します。
相続によって取得した財産の価額 | + | みなし相続財産等により取得した財産の価額 | + | 相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与の価額 | - | 非課税財産の価額 | + | 相続時精算課税制度を利用して受けた贈与の価額 | - | 被相続人の債務と葬儀費用 | = | 各相続人の課税価格 |
この計算式によって算出した各相続人の課税価格の合計を「課税価格の合計額」といいます。これが相続税の対象となる遺産であり、次項でご説明するように、これに一定の税率をかけるなどして実際の納税額を計算していきます。
その前に、上記の計算式について少し詳しく解説します。
①相続財産をすべてピックアップする
被相続人が所有していたすべての財産を明確にします。
現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も相続財産となることに注意してください。
②現金・預貯金以外は評価し遺産総額を出す
相続財産をピックアップしたら、それらの財産を金額に換算します。現金と預貯金については金額が明らかですが、それ以外の財産については評価することが必要です。
国税庁の「財産基本評価通達」に従って、一つ一つ評価していきます。
「財産基本評価通達」に基づく主な財産の評価方法は以下のとおりです。
- 土地
土地は、路線価が定められている場合は路線価で、路線価が定められていない地域については、倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率をかける方法)で評価されます。
土地に借地権が設定されている場合は、その借地権割合を引いた額が評価額となります。
なお、「小規模宅地の特例」の要件を満たす場合は、これを適用することによって土地の評価額を大幅に減額することができます。
- 建物
建物は、原則として固定資産評価額によって評価されます。建物に借家権が設定されている場合は、その借家権割合を引いた額が評価額となります。
- 上場株式
原則として、次の1.から4.までの価額のうち、最も低い価額により評価します。
- 相続の開始があった日の終値
- 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
- 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
- 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
- 生命保険金
生命保険金は、被相続人の死亡によって支払われるものについては、実際に支払われる金額で評価します。
被相続人の死亡時に支払事由が発生していない場合(例えば被相続人の子を被保険者とし、受取人及び契約者が被相続人となっている場合等)は、被相続人が死亡した時点でその生命保険を解約した場合の、解約返戻金相当額で評価がなされます。
③みなし相続財産を加える
みなし相続財産は、遺産分割の対象にはなりませんが、税法上は相続財産としてカウントすることとされています。
上記生命保険金や死亡退職金が代表的なものです。
みなし相続財産について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
④相続開始前3年以内の生前贈与を加える
被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産も、税法上は課税対象とされています。
忘れずに加算しましょう。
⑤非課税財産を差し引く
相続財産であっても、税法上は非課税となる財産もあります。代表的なものは以下のとおりです。
- 生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」
- 死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」
- 墓所、仏壇、祭具など
- 死亡後に国などに寄付した財産
これらの遺産があるときは、忘れずに差し引きましょう。
⑥相続時精算課税制度を利用して受けた贈与額を加える
相続時精算課税制度とは、生前贈与を受ける際に一定の要件を満たす場合には贈与税を支払わず、贈与者が亡くなったときに相続税として精算できる制度のことです。
この制度を利用して贈与を受けたことがある場合は、その贈与の価額を遺産に加えます。
⑦債務を差し引く
相続税は遺産全体がプラス評価の場合にかかるものであり、借金などのマイナス財産はプラス財産から差し引くことができます。
そのため、被相続人に債務がある場合は、忘れずに差し引きましょう。
⑧葬儀費用を差し引く
葬儀費用は、一定の範囲で相続財産から支払うことが認められていますので、遺産から差し引くことができます。
ただし、香典返しや墓石・墓地の購入費、初七日など法事のためにかかった費用などは差し引けませんので、注意が必要です。
(3)相続税がかかる人の割合は低い
課税対象財産は、実際に相続で取得した遺産よりも多くなることもあれば少なくなることもあります。
しかし、次項でご説明するように相続税には大きな基礎控除があるので、大半のケースで相続税はかかりません。国税庁の統計によれば、2019年に死亡した人のうち、相続税の課税対象となった人の割合は8.3%でした。
つまり、相続が発生したケースのうち、相続税がかかるのは12件に1件程度となっています。
ただ、相続税がかかるかどうかを確認するためにも、引き続き「2、相続税の計算方法」をお読みください。
国税庁ホームページ「令和元年分 相続税の申告事績の概要」
2、相続税の計算方法

それでは、相続税の具体的な計算方法を解説していきます。
(1)課税遺産総額を計算
前項でご紹介した計算式によって各相続人の課税価格(課税対象財産)を算出したら、それを全て足して課税価格の合計額を出します。
その課税価格の合計額から基礎控除額を引いたものが、課税遺産総額となります。
【計算式】
各相続人の課税価格の合計 | - | 基礎控除額 | = | 課税遺産総額 |
(2)相続人ごとの相続税額を計算
課税遺産総額を算出したら、それを実際に相続人がどのような割合で相続(分割)したかには関係なく、法定相続分に従って相続したと仮定して各相続人の取得金額を算出します。
そして、その金額に税率をかけて、各相続人ごとの相続税額を算出します。
【計算式】
課税遺産総額 | × | 法定相続分 | × | 税率 | - | 控除額 | = | 各相続人ごとの相続税額 |
なお、相続税の税率は以下のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1、000万円以下 | 10% | ー |
| 1、000万円超から3、000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3、000万円超から5、000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5、000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1、700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2、700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4、200万円 |
| 6億円超から | 55% | 7、200万円 |
引用元:国税庁
(3)相続税額の総額を計算
相続人ごとの相続税額を算出したら、それを合計します。その合計額が相続税額の総額となります。
【計算式】
各相続人ごとの相続税額の合計 | = | 相続税額の総額 |
(4)各相続人が納付すべき相続税額を計算
相続税額の総額に、実際に相続人が相続する相続財産の割合をかけて、各相続人が納付すべき相続税額を計算します。
その際、相続人特有の控除事由があれば、控除を行うことができます。
【計算式】
相続税額の総額 | × | 実際に各相続人が取得する相続財産の割合 | - | 各種控除 | = | 各相続人が実際に納付すべき相続税額 |
上記の各種控除には、配偶者の税額の軽減のほか下記のような控除があります。
①配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者については、特別に配偶者の税額軽減という制度があり、被相続人の配偶者が実際に相続した額のうち、次の①と②のいずれかの額の少ない方までの財産については相続税が発生しないこととされています。
1億6000万円
配偶者の法定相続分相当額
②未成年者が相続する場合の税額控除
相続人が未成年者である場合は、その者が20歳に達するまでの年数(端数は切り捨て)に10万円をかけた金額を未成年者控除として控除することができます。
③障害者が相続する場合の税額控除
相続人が障害者である場合は、その者が満85歳に達するまでの年数(端数は切り捨て)に10万円(特別障害者である場合は20万円)をかけた金額を障害者控除として控除することができます。
④数次相続の場合の税額控除
今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続によって財産を取得し(一次相続)、相続税を課せられている場合は、今回の相続(二次相続)によって財産を取得した相続人の相続税額から一定の金額を控除することができます。
一次相続と二次相続の間が短ければ短いほど、控除することができる金額は大きくなります。
⑤外国税額控除
相続によって外国にある財産を取得したことにより、その財産について外国で相続税に相当する税金が課せられた場合は、その相続人の相続税額から一定の金額を控除することができます。
⑥暦年課税分の贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税によって贈与を受けた者が既に支払った贈与税がある場合は、その贈与税額を控除することができます。
⑦相続時精算課税分の贈与税額控除
相続人が、被相続人から相続時精算課税によって生前贈与を受け、それについて課せられた贈与税がある場合には、その相続税額に相当する金額を控除することができます。
なお、この場合、相続時精算課税によって課せられた贈与税額の方が多い場合は、相続税額との差額について還付を受けることができます。
3、相続税を節税するには

相続税がかかる人の割合は低いものの、先ほどご紹介した国税庁の統計によると、相続税がかかったケースにおける納税額の平均は被相続人1人あたり1,714万円であり、かなりの高額となっています。
この金額はあくまでも平均ですが、相続税がかかりそうなケースでは節税対策も重要です。
相続税を節税するには、以下の対処法が考えられます。
(1)相続財産を減らす
まず、相続財産そのものを減らすことで、「課税対象財産」を減らすことができます。
①生前贈与
生前贈与をすれば相続財産を減らすことができますが、相続開始前3年以内の生前贈与は相続税の課税対象となることに注意が必要です。
また、高額の贈与税がかかってしまうこともあるので、相続税を支払うのとどちらが有利かを試算して判断する必要もあります。
次の6つのケースでは一定の場合、贈与税がかかりませんので、相続税の節税対策として有効です。
- 暦年贈与(年間110万円以内の贈与)
- 相続時精算課税制度の利用
- 配偶者への自宅の贈与
- 子や孫への住宅購入資金の贈与
- 子や孫への教育資金の一括贈与
- 結婚資金や子育て資金の一括贈与
②評価額を下げる
土地を相続した場合には、以下の対策をとることで評価額を下げることができる可能性があります。
- 現地調査をする
土地の相続税評価額は基本的に路線価に基づいて算出されています。
ただし、いびつな形の土地や、袋小路になっている土地、私道に面している土地などの場合は、現地調査をして評価をすれば相続税における評価額が下がることもあります。
該当する場合は、税理士や不動産鑑定士などに相談してみましょう。
- アパートを建築する
賃貸物件の敷地は「貸家建付地」として、評価額が20%程度減額されます。
そのため、被相続人が自宅や更地を所有している場合には、その土地にアパートなどの賃貸物件を建設することで土地の評価額を下げることが可能です。
また、継続的に家賃収入も得られますので、土地の活用法としても有効でしょう。
- 小規模宅地等の特例を利用する
小規模宅地等の特例とは、居住用または事業用宅地を相続した場合に、一定の要件のもとに相続税評価額が50%~80%減額される特例のことです。
要件を満たす場合には、忘れずに利用するとよいでしょう。
(2)各種控除を漏れなく適用する
相続税を申告する際には、前記「2」(4)でご紹介した各種控除について、該当するものがあれば漏れなく適用しましょう。
適用し忘れても税務署は指摘してくれませんので、自分で注意して適用することが必要です。
(3)特例制度をうまく利用する
相続税の節税に役立つ「特例」としては、これまでにご紹介した配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例があります。
これらの特例制度を利用するかどうかは納税者の任意であり、利用し忘れても税務署は指摘してくれませんのでご注意ください。
4、相続税の申告方法と申告期限

相続税がかかる場合は、期限までに申告と納税を済ませなければなりません。
そこで、ここでは相続税の申告方法と申告期限について解説します。
(1)申告方法
相続税の申告方法は、簡単にいうと、必要書類をそろえて税務署へ提出するだけです。
しかし、実際の申告はそれほど単純なものではありません。
① 必要書類
どんなケースでも必ず必要となる書類は、以下の3点です。
- 申告書
- 被相続人の戸籍謄本など身分関係の書類
戸籍謄本等は数十通が必要となるケースも多いので、相続開始後の早い段階から効率的に取得していくことが大切です。
また、各遺産の所在や評価額の証明書も必要です。
例えば、不動産を相続した場合は登記簿謄本(全部事項証明書)と評価額の証明書(固定資産評価額証明書や鑑定書など)が必要となります。
これらの証明書は必ずしも申告の際に提出するわけではありませんが、税務調査が入った場合には提示する必要がありますし、税額を正確に計算するためにも必ず取得しましょう。
被相続人の債務や、葬儀関係費用の支払いをしたときの領収証なども保管しておきましょう。
また、各種控除や特例制度を適用する場合には、別途書類が必要となる場合があります。
詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
② 申告の流れ
相続税の申告は、相続開始の翌日から10か月以内という期限がありますので、以下の流れに沿って効率よく進めることが重要です。
まずは、前記「1」でご説明したように、相続財産をすべてピックアップした上で、課税価格の合計額を算出します。
課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は申告不要ですが、各種控除や特例を適用した結果非課税となる場合には申告が必要であることに注意してください。
相続財産の調査と並行して、相続人として誰がいるのかを調査することも必要です。
相続人を正確に確定しなければ、相続税の計算も間違いとなるからです。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含みます。)を取得することによって、相続人の調査を行います。
課税対象財産と相続人が確定したら、相続税がかかる場合には前記「2」でご説明した手順に従って相続税を計算します。
以上のプロセスにおいて、申告書以外の必要書類は順次、集めていきましょう。
相続税の計算ができたら、申告書を作成し、その他の必要書類を添付して税務署へ提出します。
(2)申告期限
相続税の申告期限は、先ほどもご説明したとおり、相続開始(被相続人の死亡)の翌日から10か月以内です。
結論からいうと、相続税の申告と納税を期限までに完了できない場合、次の2つの不利益を受ける可能性があります。
期限を過ぎてしまうと、追徴課税を受けたり、特例が使えなくなるというデメリットを受けてしまいます。
期限が迫っている場合や、期限を過ぎてしまった場合は、早急に申告しなければ追徴課税が膨らんでいきますので、弁護士や税理士等の専門家に相談して進めることをおすすめします。
5、相続税が払えない場合の対処法

税金は原則として免除されることはありませんので、遅れてでも支払う必要があります。
もし、期限までに相続税が支払えない場合には、延納や物納が認められることもありますので、税務署に相談しましょう。
払えないまま放置していると追徴課税が膨らみ続けますし、最悪の場合は財産を差し押さえられることがありますので、ご注意ください。
6、相続税を払いすぎた場合は還付請求を

相続税は、納税者が自分で計算して申告するものであるため、計算ミスなどにより払いすぎてしまうことがあります。
払いすぎたときは、更正の請求をすることによって還付を受けることができます。
税務署は過少申告については厳しく指摘してきますが、払いすぎた場合には何も指摘してくれません。
そのため、自分で払いすぎに気づいて更正の請求をしない限り、還付を受けることはできません。
実際のところ、相続税を払いすぎているケースは少なくありませんので、相続税の申告を専門家に依頼するか、自分で申告した場合も専門家のチェックを受けてみることをおすすめします。
まとめ
今回は遺産相続にかかる相続税についてひと通り解説しましたが、相続税は複雑な制度ですので、一般の方がすぐに理解するのは難しいかもしれません。
とはいえ、家族が亡くなった場合には相続税の問題を無視することはできません。
相続税に関する知識や理解が不十分なために相続税の負担が発生してしまうというのは、もったいない限りです。
また、相続税の節税対策をするにも、早ければ早いほど選択肢も多くなり、効果的な方法を採ることが可能になります。
相続税が気になる方は、お早めに弁護士や税理士といった専門家に相談してみることをおすすめします。