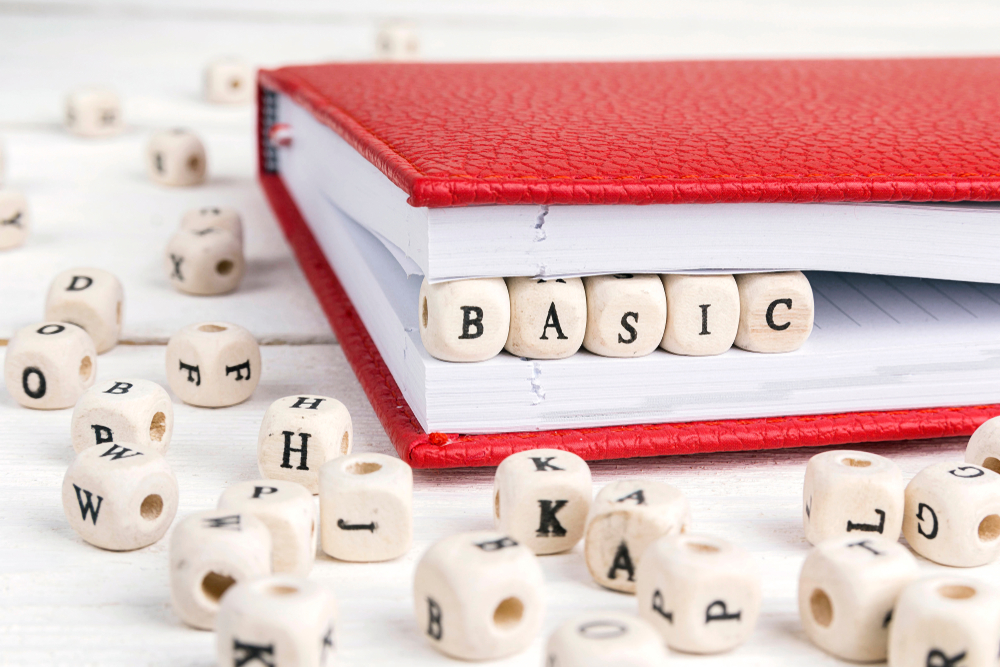遺留分はどのように計算すればよいのでしょうか。
相続人の遺産の最低限の取り分であるとされる「遺留分」。
親父が妹だけに遺産を残そうとしているみたいだけど、自分の遺留分っていくらになるんだろう?
そんなときは、自分で概算だけでも計算してみたいと思うものです。
今回は、この遺留分について、
- 遺留分はどのように計算するのか
等についてご紹介したいと思います。
ご参考になれば幸いです。
遺留分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、遺留分の計算はどうすればいい?|そもそも遺留分とは
では、そもそも遺留分とはどのような制度なのでしょうか。
遺留分とは、民法で相続人に認められる相続財産に対する最低限の権利(一定の財産は必ず相続できる権利)のことです(改正民法1042条)。
民法は、相続に関して、遺言がある場合は遺言に従って相続を行うということを原則としています。
これは、自分の財産は生きている間は、自分の自由に処分できるのですから、亡くなる前に死後の処分方法について定めていたとしても同様に尊重すべきと考えているからです。
しかし、被相続人が、「全ての財産を愛人に譲る」という内容の遺言を残したらどうなるでしょうか。
ここでも被相続人の意思の尊重が第一だとしてこの遺言どおりにしてしまうと、遺された家族は無一文となって生活に困るかもしれません。
このような事態を避け、遺された相続人を保護するために作られたのが「遺留分」なのです。
2、遺留分が認められる相続人と遺留分の割合
このように、遺留分は、遺された相続人の保護という目的があるため、遺留分が認められるのは法定相続人のなかでも一定の範囲に限られます。
具体的には、配偶者、子供(代襲相続人)、父母(直系尊属)にのみ認められるものであって、兄弟姉妹には遺留分が認められません(改正民法1042条第1項柱書)。
そして、認められる遺留分の割合は、
- 直系尊属(父母)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1(同条1号)
- その他の場合は、被相続人の財産の2分の1(同条2号)
となります。
いくつか具体例を考えてみましょう。
たとえば、相続人が父母だけのときは、1号のケースですから、遺された父母は遺産の3分の1は遺留分として確保できます。
相続人が子供だけのときは2号のケースですので、遺産の2分の1が遺留分として保証されます。
また、よくあるケースである相続人が配偶者と子供の場合はどうでしょうか。
これも2号のケースなので、遺留分は2分の1です。
この遺留分を配偶者と子供でどう分けるかは法定相続分(民法900条)の規定に従って、各2分の1(遺産全体に対しては4分の1)となります。
3、遺留分が侵害された場合は?
遺留分を侵害するような内容の遺言が遺された場合には、どうすればいいのでしょうか。
この場合、遺留分を侵害された各相続人は、遺留分を請求する権利を行使することができます。
この請求を、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)と言います。
被相続人の遺産を考えて、遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分を請求するようにしましょう。
4、遺留分算定の基礎となる財産について
では、遺留分が侵害されているかどうかはどのように求めるのでしょうか。
これは、遺留分の算定の基礎となる財産に遺留分割合、各自の法定相続分を掛けてもとめることになります。
したがって、ここでいう「遺留分算定の基礎となる財産」の範囲がどこからどこまでなのかというのが非常に重要になります。
「遺留分算定の基礎となる財産」は、法律で次のように定められています。
すなわち、被相続人が相続開始時において有していた財産(いわゆる遺産です。)の価額に、生前贈与した財産の価額を加え、これから債務を引いたものです(改正民法1043条)。
なお、対象となる生前贈与については、無制限ではありません。
相続人以外については、原則として相続開始前の一年間のものに限られます(改正民法1044条1項前段)。
ただし、一年以上前の贈与であっても、当事者双方が、その贈与をすることで遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は対象となります(改正後民法1044条1項後段)。
一方、相続人に対する贈与については、基本的に特別受益として、相続でもらうべきものの前渡しとみなされますので、相続開始前の十年間の贈与であれば、遺留分の算定の基礎となる財産の対象となります(改正後民法1044条3項)。
5、遺留分の計算方法について
先ほど申し上げた通り、遺留分は、遺留分の算定の基礎となる財産に遺留分割合、各自の法定相続分を乗じて求めます。
具体例を取り上げて実際に計算してみましょう。
ケース
配偶者と長男・次男の子供2人、遺産が8000万円、相続開始1年前までの贈与が2000万円、債務が2000万円。
この場合の配偶者と子供の具体的な遺留分額は、次のとおりです。
●遺留分の算定の基礎となる財産
8000万円+2000万円-2000万円=8000万円
●配偶者と子供2人合計の遺留分
8000万円×2分の1(遺留分割合)=4000万円
●配偶者の遺留分
4000万円×2分の1(法定相続分)=2000万円
●子供の遺留分
4000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(2名だから)
=1000万円
したがって、この場合、配偶者と子供が、遺言でもらえる金額がそれぞれ2000万円、1000万円を下回る場合は遺留分が侵害されているので、遺留分侵害額請求が行使できます。
6、遺留分侵害額請求の方法
上記の方法で遺留分を計算して、自分の遺留分が侵害されている場合、侵害をしている者に対して遺留分侵害額請求権を行使して、侵害されている分を請求することになります。
たとえば、5で取り上げたケースで、長男に全ての財産を譲るという内容の遺言がある場合、配偶者と次男は、長男に対して遺留分侵害額請求権を行使して、それぞれ2000万円と1000万円を請求していくことになります。
行使の方法については、必ずしも法的な手続きによる必要はありません。
したがって、遺留分を侵害している者に対して任意の交渉を持ちかけ、これにその者が応じてくれるのであれば、話し合いで解決することも可能です。
しかし、任意での話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停で問題解決を目指すことになります。
調停は、裁判所での話し合いの手続きですが、裁判官や調停委員といった第三者が仲介をしてくれるので、当事者だけの話し合いよりも落ち着いて話し合いを行うことができるでしょう。
調停でも決着がつかないと訴訟に移行することになります。
7、遺留分侵害額請求の時効の時効
遺留分侵害額請求はいつまでもできるというわけではありません。
相続開始および遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。
また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分侵害額請求は、相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます。
したがって、遺留分侵害額請求される場合には、内容証明郵便など、日付を証明できるように通知することをお勧めします。
まとめ
そして、遺留分侵害額請求で重要なことは、遺留分は、相続人に法律上認められた権利ですから、請求権を行使さえすれば、基本的に請求者の主張は認められるということです。
もちろん、遺留分侵害額請求をするかしないかは自由ですが、遺留分が侵害されており、少しでもその分の金銭を請求したいとお考えの方は、遺留分侵害額請求をすることをお勧めします。
具体的な遺留分額や行使の方法については、弁護士のサポートが必要な場合もありますから、ぜひ一度弁護士に相談をされるとよいでしょう。