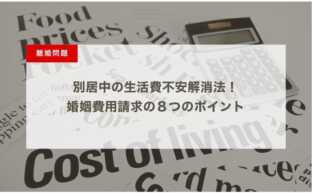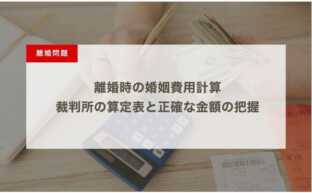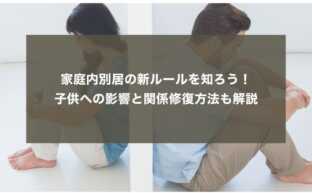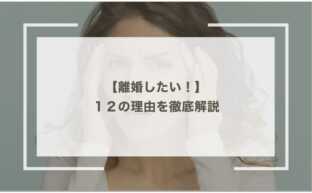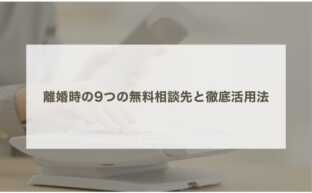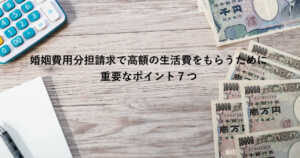
パートナーと離婚を考えて別居中の場合でも、公式に離婚が成立するまで、婚姻費用分担請求を行うことが可能です。
この記事では、婚姻費用分担請求の申し立て手続きや流れについて詳しく解説し、さらに、生活費の急務な支払いを求める場合や生活費を最大化する方法について、夫婦関係の専門家であるベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく説明します。
別居を考えている方や既に別居中で生活費に困っている方にとって、この記事が有益な情報となり、解決への一助となることを願っています。
目次
1、婚姻費用分担請求とは?

「婚姻費用分担請求」という言葉を聞き慣れていない方も多いと思いますので、まずはその意味を詳しくご説明します。
(1)そもそも婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営むためにお互いに分担すべき費用のことです。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:民法
夫婦はお互いに協力して共同生活を営むべき「扶助義務」を負っており、経済的にも支え合って生活していかなければなりません。
扶助義務は、たとえ夫婦が別居中であっても、離婚協議中であったとしても、法律上の夫婦である限り続くものです。
夫婦が同居している間は、婚姻費用分担請求が問題となることはあまりありませんが、別居している場合には分担すべき生活費を相手方に対して支払う必要があります。
通常は収入の高い方が低い方に対して、婚姻費用を支払うことになります。
収入の低い方から高い方に対して、この婚姻費用の支払いを求めることが「婚姻費用分担請求」です。
(2)どのような費用を婚姻費用として請求できる?
婚姻費用とは「婚姻から生ずる費用」のことであり(民法第760条)、わかりやすくいうと、夫婦の日常の生活費のことです。
具体的にどのような費用が婚姻費用に含まれるかというと以下の通りです。
- 日常の衣食住に使う費用
- 医療費
- 子どもの養育費
- 子どもの教育費
- 一般的に必要だと考えられる交際費
- 一般的に必要だと考えられる娯楽費
別居後に賃貸住宅に住む場合の家賃が含まれるのかが気になる方も多いと思いますが、「日常の衣食住に使う費用」として家賃も含まれます。
ただし、婚姻費用として分担請求できる金額は、その家庭の収入や資産、社会的地位に見合った範囲内に限られます。
したがって、パートナーの負担で自由に高級住宅に住めるわけではありません。
(3)婚姻費用はいつからいつまでもらえる?
婚姻費用はいつからもらえるかというと、「請求したとき」からとお考えください。
「別居を開始したとき」ではありませんので、一定期間経過したのちに別居開始時からの婚姻費用を請求できるわけではないため、「請求」をいかに早くしておくかが重要です。
しかも、「請求したとき」とは、口頭やメールで相手方に支払いを請求するだけではなく、「調停を申立てたとき」と解することが多いです。
そのため、別居前に任意に婚姻費用の分担について話し合いが成立していないのであれば、可能な限り別居と同時に調停を申し立てることをお勧めします。
(4)婚姻費用はいくらもらえる?
婚姻費用の金額は、法律上明確に決まっているというものではありません。
夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
ただ、何の基準もなければ、話し合いで具体的な金額を決めるのも難しいでしょう。
そこで、通常は裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にして金額を決めることになります。
この算定表は、家庭裁判所の婚姻費用分担請求調停や審判でも使用されています。
婚姻費用算定表の詳しい見方については、こちらの記事をご参照下さい。
(5)婚姻費用分担請求ができない場合とは?
法律上の夫婦である以上、婚姻費用を分担すべき義務がありますが、中には婚姻費用を請求しても支払ってもらえない場合もあります。
以下の各事項のいずれかに該当する方は、要注意です。
①勝手に別居した
夫婦は同居すべきことが法律で定められています(民法第762条)。
正当な理由がないのに勝手に家を出て別居するということは、夫婦の同居義務に違反していることになります。
自ら同居義務に違反しながら婚姻費用を請求することは、権利の濫用として認められません。
仮に認められたとしても、少額にとどまることが多いです。
ただし、請求が認められないのは配偶者としての生活費の部分だけで、子どもの養育費や教育費に当たる部分については、通常のケースと同様に請求が認められることが多いでしょう。
なお、顕著なDVを受けていて、緊急的に別居をしなければ身の安全を確保できない場合のように、正当な理由がある場合には婚姻費用の請求が認められます。
②自分が別居の原因を作った
家出をした場合でなくても、自分が不倫をするなどして婚姻関係を破たんさせて別居に至ったような場合も、有責配偶者からの婚姻費用の請求は権利の濫用として認められません。
ただし、子どもの養育費や教育費に当たる部分について請求が認められることは、上記「(1)」の場合と同じです。
③相手方よりも収入が高い
基本的には婚姻費用は、通常、収入の低い方が高い方に対して生活費を請求するものです。
ご自身の方が相手方よりも収入が高く、生活するに十分な経済力がある場合は、婚姻費用の請求は認められません。
ただし、手元に子どもがいる場合には(1)や(2)の場合同様に子どもにかかる費用については一定の割合で分担を求めることができるでしょう。
また、婚姻費用は必ずしも女性から男性に対して請求できるものではないことにご注意ください。
④相手方が支払不能
婚姻費用は、夫婦の扶助義務(民法第752条)に基づいて支払われるものです。
扶助義務の内容を噛み砕いていいますと、自分と同程度の生活を配偶者にも保障する義務のことです。
したがって、相手方が病気で働けずに自分の生活に苦労しているような場合には、婚姻費用は請求できないことになります。
また、相手方に借金があるような場合には、理論上は請求可能でも実際に支払ってもらうことは難しいことが多いでしょう。
⑤相手方が住宅ローンを支払っていて、自分がその住宅に住んでいる
もともと夫婦が同居していた住宅から夫が出て行き、妻子がその住宅に住み続けている場合で、夫が住宅ローンを支払っている場合には、婚姻費用をもらえるとしても月々の住宅ローンを一定程度考慮した額が差し引かれるのが原則です。
なぜなら、夫は住宅ローンを支払うことによって妻子の住居費を負担していることになるので、その分は婚姻費用から差し引くべきだからです。
したがって、算定表で導かれる婚姻費用の額と考慮されるべき金額によっては婚姻費用をもらえないということもあり得ます。
⑥相手方が生活保護を受けている
生活保護は、対象者個人の最低限度の生活を維持するために支給されるものです。
したがって、相手方が受給している生活保護費の中から婚姻費用を支払ってもらうことはできません。
なお、ご自身が生活保護を受けている場合は婚姻費用分担請求できますが、それによって最低生活費を上回ることになる場合は、生活保護費が減らされますのでご注意ください。
⑦既に財産分与を受け取っている
まれに、既に夫婦で離婚について合意して、財産分与も行われたにもかかわらず、離婚届を提出せずに婚姻費用を請求し続けるケースがあります。
このような場合は、財産分与で受け取った金銭などの財産を生活費に充てるべきであり、婚姻費用分担請求は認められない可能性もあるでしょう。
婚姻費用を請求するために形式上の離婚を引き延ばそうとしても、権利の濫用として認められないからです。
⑧過去の婚姻費用は請求できない
前記「1(3)」でも少しお話ししましたが、婚姻費用は「請求したとき」からもらえるものであり、過去の分は請求できません。
夫婦で助け合って生活していくためのお金が婚姻費用ですので、実際に生活できた過去の分についてまでさかのぼって支払ってもらうことはできないのです。
一定の期間、婚姻費用を請求しなかったことによって生活が困窮してしまった場合も、あくまでも現在の生活の扶助として、相手方が分担すべき部分を請求することになります。
2、婚姻費用分担請求をする方法

では、実際に相手方から生活費を支払ってほしいときは、どのようにすればいいのでしょうか。
ここでは、婚姻費用分担請求をする方法をご説明します。
(1)まずは夫婦で話し合う
婚姻費用の分担を請求するには、まずは夫婦で直接話し合うことが基本となります。
普段から連絡を取り合っている場合は、生活の実情を話して、必要としている金額を具体的に伝え、相手方の理解を求めるのがよいでしょう。
任意に支払ってもらうためには、できる限り円満に話し合いを進める方がベターです。
相手方が婚姻費用に関する話し合いを避けようとするような場合には、内容証明郵便で請求書を送付するなどした上で、正式な話し合いを始めましょう。
(2)婚姻費用分担請求調停を申し立てる
どうしても話し合いができないか、まとまらない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停は、家庭裁判所において調停委員を介して相手方と話し合う手続きです。
相手方が婚姻費用を支払うべきであるにもかかわらず支払わない場合には、調停委員から相手方に対して説得もしてくれます。
3、婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法

婚姻費用分担請求調停を申し立てるには、必要書類と費用を家庭裁判所に提出することが必要です。
以下で、具体的にご説明します。
(1)申立てに必要な書類
まずは、必要書類を準備しましょう。
婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な書類は以下の通りです。
- 婚姻費用の分担請求調停の申立書
- 夫婦の戸籍謄本
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、確定申告書、給与明細等)
- (もし持っていれば)相手方の収入関係の書類
申立書の雛形は最寄りの家庭裁判所で入手できますが、裁判所のホームページからもダウンロードできるので、利用しましょう。
(2)申立書の書き方
次に、申立書の書き方を具体的にご説明します。
ここからは、記載例を見ながらお読みいただけるとわかりやすいかと思います。
では、順にご説明していきます。
①申立先家庭裁判所と申立日の欄
まずは申立先の家庭裁判所名と申立て日を記載しましょう。
②申立人の記名押印の欄
あなたの名前を記載し、押印して下さい。認印で構いません。
③申立人の住所・氏名の欄
家庭裁判所から期日指定書など書面が届くことがあるので、住所・氏名を記載しましょう。
④相手方の住所・氏名の欄
裁判所から相手方に申立書のコピーなどが送られるので、相手方の住所・氏名を記載しましょう。
⑤未成年の子の欄
夫婦間に未成年の子どもがいる場合に現在の状況を書く欄です。
まず、現在申立人と相手のいずれと同居しているのかをチェックしましょう。
その上で、名前と生年月日を全員分書いていきましょう。
⑥申立ての趣旨の欄
この欄では、婚姻費用としていくらを請求するのかを記載します。
まず、順に「相手方」「申立人」「調停」をチェックしましょう。
その上で「1」~「3」のうち「1」に○を付けて、毎月請求する金額を書きましょう。
金額については、「別居時の婚姻費用の計算ツール|正しい計算方法も教えます」を参考に適正な婚姻費用を計算して下さい。
⑦申立ての理由の欄
次に「申立ての理由」を記載します。ここには婚姻費用の請求に至るまでの事実関係について記載します。
まずは同居を開始した日を書きましょう。
もし、明確な日付が分からなければおおよその日付でもよいでしょう。
その隣に別居した日を書きましょう。
明確な日付が分からなければ分かる範囲で記載しましょう。
(3)調停の申立にかかる費用
必要書類の準備ができたら、費用も準備しておきましょう。
申立てにかかる費用は以下の通りです。
①収入印紙代 1,200円
離婚調停を申立てるには収入印紙を購入し、申立書に貼って家庭裁判所に提出します。
収入印紙は、郵便局やコンビニで買うことができます。
②切手代 800円前後
調停を申立てる際には、裁判所が相手側に書類を郵送する必要から、切手を購入して裁判所に提出することになります。
金額は800円前後となりますが、裁判所によって総額や切手の種類の組み合わせが異なりますので、申立先の家庭裁判所で事前にご確認ください。
③戸籍謄本の取得費 450円
戸籍謄本は、本籍地の市区町村の役所で取得します。
自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで受け取り可能なところもあります。
取得費は、ほとんどの自治体で1通450円です。
夫婦は同じ戸籍に記載されていますので、1通取得すれば足ります。
(4)申立先の裁判所
婚姻費用分担請求調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家裁となります。
遠方の別居先に引っ越した方は、ご注意ください。
もっとも、どこの家裁に調停を申し立てるかを相手方との間で合意した場合は、その家裁に申し立てることもできます。
その他の家裁の管轄区域については、こちらの裁判所のページから調べることができますので、ご利用ください。
4、婚姻費用分担請求調停の流れ

婚姻費用分担請求調停の申し立てが受理されると、いよいよ家裁にて話し合いが行われます。
どのような流れで調停が進むのか、みていきましょう。
(1)申立てから第1回目の調停まで
申立てが受理されると、第1回の調停期日の日が記載された呼出状が申立人と相手方の住居に届きます。
呼出状が届くのは申立てから2週間ほど経過したタイミングです。
第1回の調停の期日は申立てから1ヶ月後あたりです。
(2)第1回目の調停期日
第1回目の調停では、申立人と相手方の収入を把握する必要から、最新の源泉徴収票やそれがない場合は、直近3ヶ月分程度の給与明細の持参を要求されるでしょう。
もし提出するように言われている場合には、忘れずに持っていきましょう。
また、遅刻しないように余裕をもって出かけましょう。
調停期日における手続きの流れは、以下のとおりです。
①待合室で待機
家庭裁判所に到着すると待合室で待機することとなります。
待合室は夫婦別々に離れた場所に設けられていて、ばったり会ったりしないように配慮されています。
②調停室へ呼び出し
指定された時刻になると、調停室に呼び出されます。
基本的には、申立人が先に呼び出されることとなります。
調停室には、裁判官と男女1名ずつの調停委員がいます。
まず、調停の進め方などについて説明があるでしょう。
裁判官は最初に軽く説明するだけで退席し、あとは調停委員の主導で調停が進められます。
③次に相手方が調停室へ呼び出される
調停室へ戻ると、次は相手が調停室に呼び出されて同じように30分ほど事情を聞かれます。
この時、調停委員は相手方の主張を聞くことが多いでしょう。
その際に、申立人の主張も伝えられます。
一通り聞かれると調停室から待合室に戻ることとなります。
④また調停室へ
相手方の番が終わると、また調停室へ呼ばれることとなります。
また時間としては30分ほどです。
この時、相手の主張を聞かされるでしょう。
その上で、婚姻費用算定表を見せられて、適正な金額を提示されます。
基本的には、算定表に基づいて合意案を提示してくれるようです。
⑤今度は相手方が調停室へ
申立人にて調停委員らとの2回目のやり取りが終わると、次はまた相手方が調停室へ呼ばれます。
相手方へも婚姻費用算定表に基づいて適正な合意額が提示されることとなります。
⑥第1回の調停終了
もし、調停委員の提示した金額で合意に至れば調停は終了となります。
夫婦関係調停調停の場合と異なり、婚姻費用の分担請求調停の場合には1回で終わることも少なくありません。
これに対して、金額面での合意に至らなかった場合には2回目の調停が行われることとなります。
(3)第2回目以降の調停の流れ
第2回目以降の調停についても、ほぼ第1回と同様の流れで進みます。
以後、合意に至るまで行われます。
(4)調停が成立した場合
話し合いの結果、当事者が合意に至ると調停が成立し、調停調書が作成されます。
調停調書があると、後に相手方が婚姻費用を支払ってくれないという事態になっても強制執行することが可能となります。
これにより、貯金や給料を差し押さえることができるので、継続的に婚姻費用を支払ってもらうことができます。
(5)調停が不成立となった場合
一方、調停が不成立となった場合には自動的に審判に移行します。
審判では、裁判所が調停に提出された資料などを総合的に判断して婚姻費用を決定します。
ほとんどの場合は、婚姻費用算定表に従って金額が決定されます。
審判が下されると審判書が作成されますので、調停調書と同様に、審判書に基づいて強制執行の申し立てが可能となります。
5、すぐに婚姻費用を支払ってほしいときは?

婚姻費用分担請求調停を申し立ててから調停が成立するまでには、早くても2ヶ月弱、長ければ半年以上かかることもあります。
審判にまで進むと、さらに時間がかかる可能性があります。
しかし、生活費を支払ってほしいと申し出ているのに、これだけの期間は待てないほど生活が逼迫していることもあるかと思います。
そんなときは、次の2つのいずれかをとることで、早期に婚姻費用を支払ってもらえる可能性があります。
(1)調停前の仮処分
調停前の仮処分とは、調停を申し立てから調停が終了するまでの間に、裁判所が仮に命令や勧告を発することをいいます(家事事件手続法第266条)。
家裁へ仮処分を求める上申書を提出すれば、緊急の必要性が認められる場合には、裁判所の職権によって相手方に対して、婚姻費用を支払うように命令または勧告をします。
もっとも、調停前の仮処分が認められても、強制執行力はありません。
しかし、相手方が裁判所の命令や勧告に従わなければ「10万円以下の過料」というペナルティが定められているので、それなりの効果は期待できるはずです。
(2)審判前の保全処分
審判前の保全処分とは、調停前の仮処分と似た手続きですが、審判手続における決定が出るまでの間に裁判所が一定の処分を命じることをいいます(家事事件手続法第105条)。
やはり緊急の必要性が認められる場合には、裁判所が相手方に対して、一定額を支払うように命じます。
調停前の仮処分とは異なり、審判前の保全処分には強制力があります。
相手方が裁判所の命令どおりに婚姻費用を支払わない場合には、強制執行手続きによって相手方の給料などの財産を差し押さえることができます。
6、婚姻費用分担請求で少しでも多くの生活費を獲得するためのポイント

婚姻費用分担請求をするなら、少しでも多くの生活費を獲得したいところでしょう。
そのためには、以下のポイントをチェックしておきましょう。
(1)できる限り話し合いで決着をつける
実は、高額の婚姻費用を獲得するためには、家裁へ調停や審判を申し立てる前に、パートナーとの話し合いで決着をつける方が有利なことが多いです。
なぜなら、調停では調停委員が裁判所の「婚姻費用算定表」を機械的に適用しがちであり、審判では家裁が一方的に算定表を適用して金額を決めることになりがちだからです。
そのため、家裁の手続きで算定表を超える金額を獲得するのは難しいのが実情となっています。
話し合いの段階で生活の実情やお金の必要性を上手に訴えかけた方が、むしろ相手方の理解が得られやすいケースも多いものです。
(2)相手の収入や財産を把握しておく
パートナーとの話し合いがスムーズに進んだと思っても、財産隠しをされたのでは適切な金額を獲得することはできません。
したがって、相手の収入や財産を把握しておくことは非常に重要です。
もっとも、別居してから相手の収入や財産を探ることは難しい場合が多いので、できる限り同居中に確認しておくことが望ましいといえます。
どうしても相手の財産調査が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
(3)必要な金額の根拠を説明し、証拠も提出する
パートナーと直接話し合う場合でも、調停で話し合う場合でも、高額の婚姻費用を請求する場合には、必要な金額を計算して、その根拠を具体的に説明し、証拠も示すことが重要です。
一般的に高額の婚姻費用が認められやすいのは、子どもが私立学校に通っている場合や、ご自身または子どもが病気やケガをして医療費が必要となっている場合です。
その他にも、居住地域によっては家賃や交通費がどうしても高額になってしまう、ということも正当な理由となるでしょう。
こういった具体的な事情に基づいて、実際に必要な金額を計算し、学費の納付書や病院の診断書・診療報酬明細書などの証拠も用意して、パートナーの説得に努めましょう。
調停の場合は、調停委員に対して「自分でどんなに努力しても、どうしてもあとこれだけの婚姻費用が必要です」という形で訴えかけるとよいでしょう。
7、婚姻費用分担請求で困ったときは弁護士へご相談を

夫婦である以上は婚姻費用を分担すべきとはいっても、理解のあるパートナーばかりではありません。
相手方にも生活があるので、できる限り支払いたくないと考えるのでしょう。
そのため、婚姻費用分担請求に相手方が応じなかったり、相手方ともめてしまうことも多々あります。
そんなときは、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談すれば、あなたの状況で婚姻費用分担請求が可能かどうか、可能だとしていくら請求できるのか、どのように請求すればよいのかなど、あらゆる面でプロのアドバイスを受けることができます。
まとめ
婚姻費用は、パートナーが自発的に支払ってくれない限り、請求しなければもらえません。
「婚姻費用分担請求」という言葉をお調べの方は、パートナーから別居後の生活費を払ってもらえずにお困りなのではないでしょうか。
過去の分は請求できませんので、別居を開始したらすぐに婚姻費用分担請求をすることが重要です。
お困りの場合は弁護士が味方となりますので、お気軽にご相談ください。