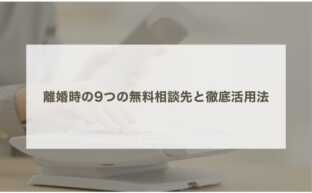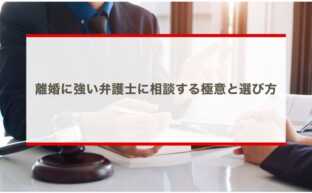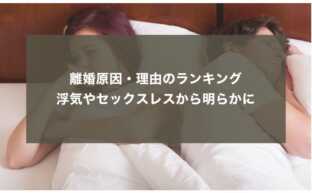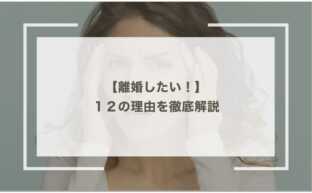同居生活における姑との関係は、嫁たちからよく「大変だよ」と口をそろえて聞かれることがあります。しかし、近年では「同居だから助かっている」という肯定的な声も増えてきています。姑や義両親との同居を始める予定の方や、既に同居を始めて違和感を感じている方にとって、姑との同居での問題や悩みを解決するために必要な情報を知ることが大切です。
そこで、この記事では実際の体験を通じて学ぶ、嫁姑の関係における問題の実態や、円滑なコミュニケーションのコツ、そして解決が難しい場合の対処法について詳しく説明します。同居生活が非常に困難で夫婦関係にまで影響を及ぼす前に、この記事を参考に問題解決に向けて一歩踏み出しましょう。
1、姑との同居が辛い…妻の体験談8選
まずは、姑との同居に辛さを感じている女性の体験談からチェックしていきましょう。
(1)玄関を分ければ良かったと後悔
結婚後すぐに二世帯住宅を建て、姑との同居をスタートさせたRさんは、家の玄関を分けずに1つにしてしまったことをずっと後悔しています。
姑との関係は良好で表面的なトラブルは一切ないものの、1階に住む姑は2階のRさん夫婦宅にことあるごとに顔を出し、階段を上がるだけですぐに行き来ができることもあって、何をしていても「姑が来るかも…」と思うと気持ちが落ち着かないのです。
(2)家族のお出かけにも毎回義母が一緒
義父が亡くなってから、1人になってしまった義母との同居を開始したIさん。
普段の生活にも習慣の違いなどから小さな負担を抱えていますが、さらにIさんを悩ませているのが、家族で食事や遊びに出かけるとき、必ず義母も一緒についてくること。
当然外出先での記念写真にも毎回義母が一緒に写り、Iさん夫婦と子供だけの写真はほとんどありません。
義母だけ家で留守番させるのは可哀想という夫の気持ちも分かるのですが、レストランなどで水入らずに過ごしている他の家族を見ると、ついつい「羨ましい」という気持ちが湧いてきてしまいます。
(3)似た者親子すぎて悪口が言えない
Eさんの悩みは、夫と姑があまりにも似た者親子であることです。
姑とは比較的仲が良く、普段から色々な話をしますが、「(夫)さんったら、また職場に傘を忘れて帰ってきて…」と愚痴っても、「分かるわぁ、私もよくやっちゃうのよ」と返されてしまうと、それ以上は何も言えません。
夫の悪口を言うと、かなりの確率でそれがそのまま姑の悪口になってしまうので、うかつに口を開けないのです。
(6)妻・母の役割を奪う姑
Aさんと同居中の姑は、Aさんの夫が帰ってくると玄関でカバンを受け取り、脱いだコートをいそいそとクローゼットにしまい、「お風呂?それとも先にご飯?」。
Aさんは内心「それって妻である私のセリフだと思うんですけど!?」と憤慨していますが、夫と姑は何の違和感も抱いていないらしく、親密な親子関係を見せつけられるたびに、Aさんは「自分のほうが部外者なのではないか」という疎外感を覚えてしまいます。
さらに、Aさんの子どもたちの世話も姑の仕事。
学校から帰ってきたときの体操着などの洗濯や、子どもたちの夕飯の世話までしゃしゃり出てきます。
姑にばかり気を使い譲ってきたものの、子どもたちの親としての経験も半減。
姑のペースに振り回され、Aさんのイライラは限界です。
2、姑との同居をうまく回すコツ

みなさんの体験談、いかがでしたか?
このようにはなりたくない、どうにか手を打たなければと考えるみなさんのために、本項では姑との同居をうまく回すコツについて、お話していきます。
(1)自宅は二世帯住宅にする
家を準備するにあたり、必ずしも二世帯仕様にできない場合もありますが、もし可能であれば自宅は二世帯住宅にすべきです。
二世帯住宅とは、1つの自宅でありながら、その内部に2つの世帯が住めるように造られた家屋のことです。つまり、台所、手洗い場等が各世帯用に設けられていることが必要です。
なぜこれが必要なのかですが、同居前は親しいつもりであったとしても、やはり「限界」がお互いに存在します。「限界ってなに?」「これまで通りやればいいだけ」と軽く考える人も少なくありませんが、やはりプライバシーを守れる空間がないと、お互いにだんだん苦しくなってくるでしょう。
自宅とは、
- 見たいテレビを観る
- 好きな時間にお風呂に入る
- 好きな時間に眠る
- 好きなものを好きなだけ食べる
というような自由が確保されているべきです。健康で余裕があるときばかりではありません。相手側に心配や迷惑をかけないためにも、プライベート空間を確保することは必要なことと考えておきましょう。
(2)子どもがいるなら姑と孫との関わり方をルール化する
子どもがいる場合、姑と同居をすると、姑の子育てへの関与をゼロにすることは難しいかもしれません。
姑側がなんらかの事情で孫の世話を拒んでいたとしても、あなたがどうしても抜けられない用事があるときは、もっとも近所に住む親戚として頼ることになるでしょうし、元気な場合はたいていの方は「子育ての役に立ちたい」と張り切っています。そのため、妻側に頼る気がなくても、頼らざるを得ないケースも少なくありません。
同居前に仲良くしていた嫁姑ほど、堅苦しい決め事はやめてそのときどきで決めましょうなどと考えがちです。
しかしそれは得策ではありません。実の親子ならそれでも大丈夫かもしれません。しかし義理の親子でそれをすることは難易度が高いのです。
決め事なんてしづらい・・と思ったのなら要注意です。なぜなら、それは仲がいいからではなく、過度に遠慮をしているからしづらいということ。夫を巻き込み、ぜひ決め事はしておきましょう。
(3)暮らしについてもルールを共有
子育てだけではありません。
洗濯や楽器の演奏など、いわゆる近所間で騒音トラブルになるようなことについても、何時まで行うのか等共有し、時間帯についてもルールにした方がよいでしょう。ペットを飼っても大丈夫かなども、会話の中で確認しておくとよいかもしれません。
また、夫婦世帯で外食や旅行等に頻繁に行きたい家庭や、共働きで帰りが遅い夫婦であれば、そのような生活スタイルであることも事前に共有しておきます。
こうして、姑側の「思っていたのと違う」を少しずつ同居前からなくしていくことが重要となります。
(4)姑の言葉を気にしない
「姑の言葉をいちいち気にしない」ということもポイントです。
いろいろな嫁姑の形があるので一概には言えませんが、多くのケースでは姑が強いのではないでしょうか。
そうすると、嫁側は姑の言葉を気にしてしまいます。姑に言われたからこうしよう、姑が勧めるからこうしなければ・・。
これが積もると「ストレス」になってしまうのです。
初めのうちはなかなかできることではないかもしれませんが、「はいはい~」と聞き流すことが大切なときがあることを忘れないでください。
(5)姑に期待しない
あなたの実母が立派な女性であったり、あなたに「母親像」や「女性像」があると、姑に母親(祖母)としての動きを期待してしまうかもしれません。
- 朝は玄関の前を掃除しておくべき
- ゴミは回収時間の2時間前には出しておくべき
- 家事は効率よくこなすべき
などの理想像をもっていると、それができない姑にイライラし、尊敬の気持ちを持てず、ついキツイ態度に出てしまう方も少なくありません。
姑は、あなたの夫の母親です。それ以上でも以下でもありません。
過度に母親として、女性としての期待値をもつことは、なにもよい結果を生みません。
3、姑との同居を解消したいと思ったら
姑との生活に我慢の限界を感じたら、同居を解消するためには一体どうすれば良いのでしょうか。
具体的な同居解消へのステップをご紹介していきます。
(1)夫に別居の意思を伝える
何はともあれ、まずは夫に相談してみることが第一です。
しかし、その際は伝え方が肝心で、
- 姑と同居することの何が辛いのか
- なぜこれ以上同居を続けることが難しいのか
- 自分と夫・子供・姑それぞれが別居によって得られるメリット
これらのポイントを落ち着いて説明することができるよう、事前にしっかり状況を整理しておきましょう。
みなさんにとっては気を使う相手でしかない姑でも、夫にとっては実の母親。
身内を悪く言われるのは、どんな場合であっても決して気分の良いことではありません。
だからこそ、単なる愚痴や悪口で終わってしまうのではなく、「私たち夫婦や子供にとってはもちろん、お義母さんにとっても別居したほうが良いと思うの」という流れで、前向きに話し合いを行うよう心がけてみてください。
(2)転居先を探す
夫の同意を得ることができたら、次に行うべきは転居先の決定です。
姑に「別居したい」という話を切り出す前に、先手を打って引っ越しの準備を進めておくことで、万が一姑が同居解消に反対したとしても、「すでに引っ越し先も日程も決まっているので」と説得することができます。
あまり考えたくないことですが、世の中には息子夫婦の引っ越しを妨害しようとしたり、別居の希望を伝えた途端に嫌がらせをしてきたりする姑もいるため、なるべくギリギリまで水面下で準備を進め、実際に話をするのは姑が手出しをできなくなるタイミングまで待ちましょう。
(3)実家に戻る
そもそも夫が姑との同居解消に同意してくれないなど、夫婦で一緒に家を出ることが難しいケースもあります。
そんなときには、夫との話がまとまるまで一旦実家に戻るのもおすすめです。
無理をせず、自分と子供だけ実家に身を寄せてしばらく様子を見るのもひとつの手。
4、どうしても姑との同居解消が難しい場合は
事情があってどうしても同居を解消することができない場合は、次のような対処法を試してみるのもおすすめです。
(1)セカンドハウスを作る
セカンドハウスとは、夫と姑が暮らす家のほかにもうひとつ別の賃貸物件などを契約することで、妻は基本的にセカンドハウスで寝泊まりし、家事などの必要があるときにだけ夫と姑の家に通います。
夫がいない日中だけ・週の半分だけなど、セカンドハウスの活用の仕方は人によって様々ですが、姑と直接顔を合わせる機会をなるべく減らし、心理的な負担を和らげるという目的は同じです。
また、新たに賃貸物件を契約するとなると、その費用の出所が気になる方も多いかと思いますが、「同居を解消できないなら離婚する、それが嫌ならせめてセカンドハウスを用意して」という妻側の要求によってセカンドハウスが実現するケースも多く、その場合は夫が家賃もそこでの生活費も負担するというのがよくあるパターンです。
(2)極力、外に出る時間を作る
別居することが難しくても、姑が家にいるときにはできる限り外出し、物理的に姑との接触を避けるようにすれば、心はだいぶ軽くなるでしょう。
「買い物に行く」「子供を習い事に連れて行く」など、口実は何でも構いません。
外に出たほうが単純に気分もリフレッシュすることができますし、積極的にお出かけの予定を作りましょう。
(3)実両親に相談する
辛くて誰かに話を聞いてほしいときには、自分の実の両親に相談するのが1番です。
夫は妻であるみなさんと自分の母親との間で板挟みになっている状態なので、100%みなさんだけの味方になってくれるとは限りません。
その点、実の両親なら何の屈託もなく娘の幸せを最優先して考えることができ、みなさんの悩みにも誰より共感してくれるでしょう。
(4)話し合ってルールを決める
たとえば「午前中の間は2階の息子夫婦宅に入るのを遠慮してもらう」「週に1回は義母抜きで出かける」など、みなさんが今不満に思っていることを改善できそうなルールを、家族で話し合って作ることも効果的です。
姑側がわざと意地悪をしているわけではない限り、普段の行動は案外無意識で、自分の振る舞いが嫁に嫌な思いをさせているなんて思いもしなかった!ということも多いでしょう。
明確にルールを定めることで、姑にとっても息子夫婦とどう付き合えば良いかが分かりやすくなります。
(5)相手にしない・放っておく
相手が誰であれ、人間関係に疲れてしまう理由のひとつに「相手の言葉を深読みしすぎてしまう」というものがあります。
特に嫁姑の関係はデリケートなので、ちょっとした言葉にも「実は裏があるのではないか」「本当はこういうことが言いたかったのではないか」と勘繰って、それが心の負担につながってしまうこともあるのです。
1度そういった深読みを一切やめて、姑が何を言ってきても「そうですね~」と軽く受け流すようにしてみるのも、心の平穏を保つ方法のひとつ。
同居のストレス対策については、こちらの記事もご覧ください。
5、姑との同居生活に疲れ離婚を考えたときは
実は、令和3年の司法統計によれば、家族親族と折り合いが悪いという理由での女性側からの離婚調停の申立ては2,789件あり、その割合は全体の5.8%を占めています。多い割合ではありませんが、毎年一定数いらっしゃることは確かです。
みなさんの中には、姑との同居に疲れ果てて「もう正直離婚したい」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
そんなときには、ひとまず弁護士に相談することで、法的な観点もふまえたアドバイスを得ることができ、自分が今何をするべきなのか、こじれた状況やこの先の展望もスッキリ整理することができます。
まとめ
嫁姑問題は昔から根深く、毎日顔を合わさざるを得ない同居の場合は、特にうつなどの病気を発症してしまうケースも少なくありません。
今みなさんが姑との同居生活に疲れを感じているのなら、1日でも早く何かしらの対策を取ることが重要です。
今回ご紹介した同居の解消方法や、事情があって別居できないときの対処法も参考に、少しでもみなさんが楽に生活できるよう最初の一歩を踏み出していきましょう。