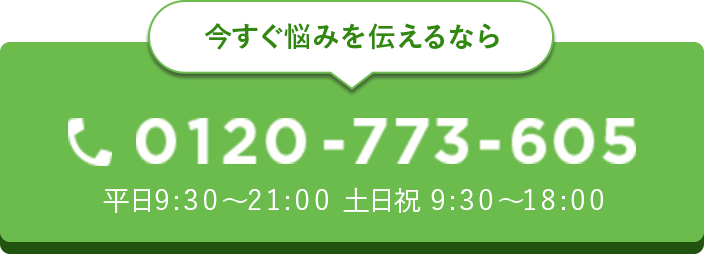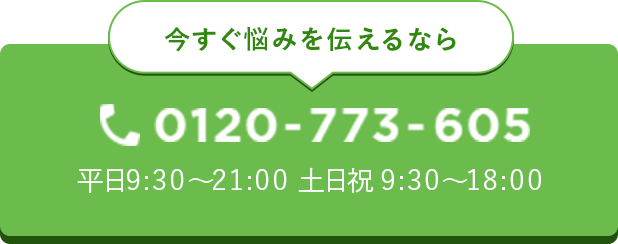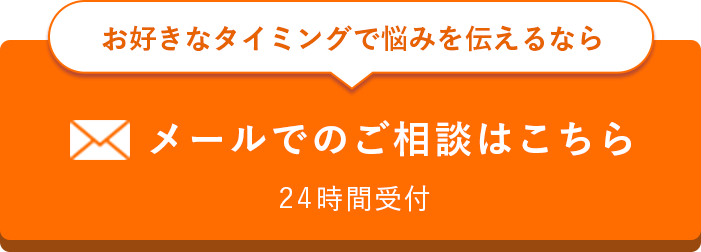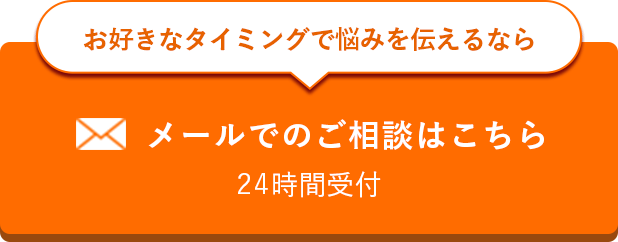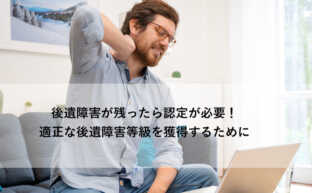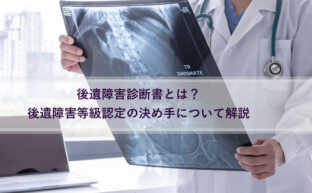交通事故による負傷で最も多いのが「むちうち(頚椎捻挫)」です。
むちうち(頚椎捻挫)は命に関わるような負傷ではないものの、なかなか治らずに苦しむことがあります。
それにもかかわらず、保険会社からは「もう治っているはずだ」「そんなに重症なはずはない」などと言われて、適切な保険金を支払ってもらえないケースも少なくありません。
また、むちうち(頚椎捻挫)になると後遺障害が残ることも少なくありません。その場合には損害賠償金が大きく上がりますが、被害者自身の対応次第では適正な賠償金を受け取ることができないおそれもあるのが実情です。
そこで今回は、
- 交通事故によるむちうち(頚椎捻挫)の適切な治療法
- 交通事故によるむちうち(頚椎捻挫)でもらえる賠償金
- むちうち(頚椎捻挫)の賠償金を上げるための注意点
という観点から、交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になってしまった人が知っておくべき重要なことを6つのポイントにまとめて解説していきます。
この記事が、交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になってしまい、苦しんでいる方の手助けとなれば幸いです。
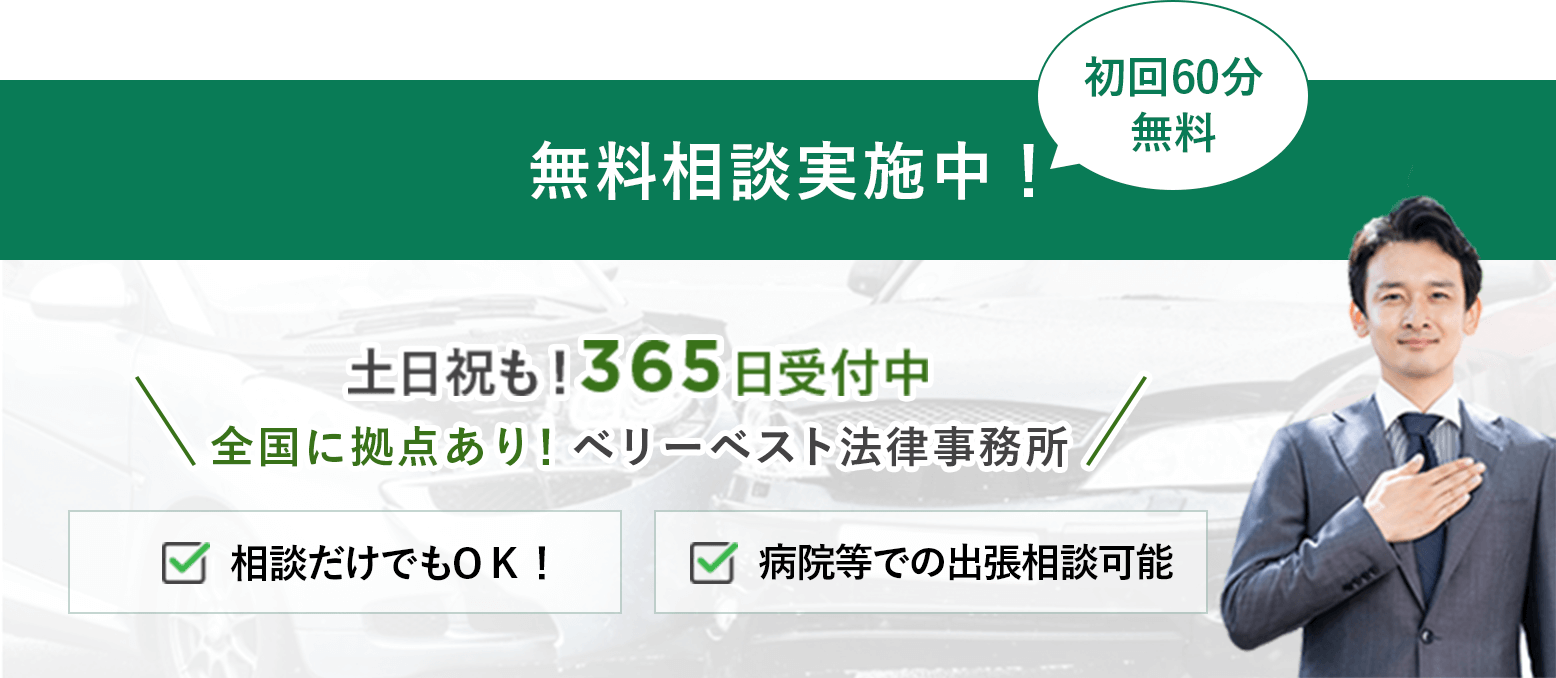

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、交通事故によるむちうち(頚椎捻挫)とは

むちうち(頚椎捻挫)とは、首や頭、体に衝撃をうけて、首が捻挫してしまうことをいいます。交通事故では、追突事故を受けたときに起こりやすい症状です。
むちを打つときのように首が大きくしなることから、俗に「むちうち症」と呼ばれています。なお、「捻挫」とは、関節に力が加わって起こるケガのうち骨折や脱臼以外ものをいいます。
損害賠償金を正しく受け取るために、まずはむちうち(頚椎捻挫)について正しく理解しておきましょう。
(1)症状
頚椎捻挫の症状で多いのは、首や肩・背中の痛み、頭痛、手足の痛みやしびれなどです。重症の場合、めまいや吐き気、耳鳴りを伴うこともあります。はっきりとした症状がなくても、何となく気分が重くて集中力が続かなくなったり、だるさが続いたりすることもあります。
このような頸部の自律神経機能障害が出ている場合を、「バレ・リュー症候群」と呼びます。
また、朝だけ気分が悪くなったり、天候が悪い日だけ痛みが強くなるなど、気圧や湿度の変化によって症状が変化することも少なくありません。骨折などの外傷と違い、事故直後は特に症状がなく、数日後に症状が現れる場合もあります。
(2)治療方法と治療期間
受傷後はまず、できる限り安静にしつつ冷湿布などで患部を冷やすことで炎症を抑えます。痛みがひどいときは痛み止めの処方や神経ブロック注射が行われることもあります。
炎症がおさまったら、リハビリを始めます。病院でのリハビリは、首の牽引療法や温熱療法、電気療法が中心となります。場合によっては、整骨院や鍼灸院での施術が有効な場合もあります(ただし、医師による指示があることが望ましいです。)
痛みの緩和と自然治癒を図る治療方法が一般的ですが、次にご説明するように深刻な負傷の場合には手術が必要な場合もあります。
治療期間については、一般的な医学的知見として、約2、3か月程度の期間が相当とされています。ただし、負傷や症状の程度、個人差によって必要な治療期間は様々で、6か月ないしはそれ以上の治療期間を必要とする場合も当然あります。症状が残っているのであれば、継続して治療を受けることが大切です。
(3)実はさらに深刻な負傷であることも
頚椎捻挫は、多くの場合、筋肉や靱帯の損傷にとどまり、いずれは自然治癒するといわれています。しかし、なかには、骨や神経を損傷しているなど、自然治癒が期待できない重いケースもあります。
比較的多い関連傷病として、強い衝撃で椎間板の一部が飛び出して神経を圧迫する椎間板ヘルニアが挙げられます。椎間板ヘルニアの治療法も基本的には上記のような保存療法となりますが、程度によっては手術をしなければ症状が改善しないこともあります。
深刻な傷病が潜んでいる場合、原因を特定して適切な治療を受けない限り症状がいつまで経っても治らないことになります。原因不明のまま治療を終了すると、適切な後遺障害等級認定を受けることができず、わずかな損害賠償金しかもらえないおそれもあります。
頚椎捻挫と関連する様々な症状、傷病の原因は、CTやMRIなどの検査によってようやく判明する場合が多いです。頚椎捻挫の可能性がある場合、早めに詳しい検査を受けておくことが大切です。
2、交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になった方へ弁護士が一番伝えたいこと

私ども弁護士は、数多くの交通事故の被害者の方からご相談を受け、損害賠償請求の問題を解決に導いて参りました。その経験に基づいて一番伝えたいことは、むちうち(頚椎捻挫)は決して軽い負傷だとは限らないということです。
本当は重い症状であり、高額の賠償金がもらえるケースであるにもかかわらず、被害者本人も医師も気付かず「軽傷」として取り扱ってしまい、わずかな賠償金しか受け取っていないケースが少なくないのです。特に、むちうち(頚椎捻挫)がなかなか治らない場合には、「後遺障害」の問題として慎重に対応する必要があります。
(1)むちうち(頚椎捻挫)は「後遺障害」にあたる場合がある
後遺障害とは、交通事故による負傷が完治せずに残った症状のうち、自動車損害賠償保障法施行令で定められた等級(「後遺障害等級」といいます。)に該当するものとして認定を受けたもののことをいいます。
一般では、治療を受けても残存する症状のすべてを「後遺症」と呼びますが、交通事故で損害賠償の対象となる「後遺障害」は、その中でも「後遺障害等級」の認定を受けたものに限られるのです。
交通事故でむちうち(頚椎捻挫)となって治療をある程度の期間続けていると、完治しないものの、症状が良くも悪くも変化しない状態になることがあります。この状態になることを「症状固定」といいます。
症状が固定すると、「もう仕方ない」といって諦める人がいますが、これはもったいない限りです。残存した症状は、後遺障害にあたる場合があります。しかし、諦めてしまうと保険会社では後遺障害はないものとして取り扱われるので、適正な賠償金を受け取れない可能性があるのです。
(2)交通事故で「後遺障害」の認定を受けると賠償金が上がる
医師から症状固定の診断を受けると、交通事故によるケガの治療は終了します。怪我を負ったことに対する慰謝料(入通院慰謝料)は、それまでの入通院期間に応じて計算されます。
しかし、「後遺障害」の認定を受ければ、それまでの賠償金とは別に後遺障害に関する賠償金が支払われます。つまり、最終的に受け取れる賠償金が上がることになるのです。
後遺障害に関する賠償金には、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」の2つがあります。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって今後の仕事や日常生活で余儀なくされる精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ると労働能力が一部制限されてしまい、今後の収入が減ってしまうのが通常であるため、「事故に遭わなければ将来に得られたであろう利益」として支払われる損害賠償金のことです。
これらの損害が認められるかどうかによって、最終的に受け取れる賠償金が数百万円から場合によっては数千万円も異なってくることがあります。したがって、後遺障害の認定を適切に受けることは極めて重要です。
3、交通事故のむちうち(頚椎捻挫)で賠償金を上げるための注意点

交通事故のむちうち(頚椎捻挫)で賠償金を上げるためには、後遺障害の認定を適切に受けるだけでなく、治療中から注意しておくべき点もあります。
治療中や事故直後にこの記事をお読みの方は、十分に注意して対応しましょう。
(1)後遺障害等級認定での注意点
後遺障害等級の認定を受けるには、「損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所」というところへ申請を行う必要があります。その際に注意すべきポイントは、以下の3点です。
①後遺障害診断書の記載内容に注意する
むちうち(頚椎捻挫)の治療を続けていて症状固定となったら、主治医に「後遺障害診断書」を発行してもらうことになります。
後遺障害等級認定の申請をする際には様々な資料を提出しますが、そのなかで最も重要となる資料が後遺障害診断書です。
後遺障害診断書には、残存した自覚症状の他、他覚所見やさまざまな検査結果が記載されますが、自覚症状以外の記載が乏しい場合には後遺障害等級認定を受けるのは難しくなります。
むちうち(頚椎捻挫)の場合、CT、MRI検査等により他覚的所見(画像上の異常)が発見されるケースは多くありませんので、神経学的な異常を調べる検査(スパーリングテスト、ジャクソンテスト等)を受けて、その結果を正確に記載してもらうことが重要となります。
②後遺障害等級認定の申請方法を工夫する
後遺障害等級認定の申請を保険会社に全て任せてしまう方も多くいらっしゃいます。保険会社に後遺障害等級認定手続をしてもらう方法を「事前認定」と呼びます。
この方法はご自身では何もする必要がないので手続として楽ですが、保険会社が被害者に有利な資料を収集して提出してくれたり資料の中の不利な記述について修正してくれたりすることは全く期待できません。
反対に、保険会社任せにせずにご自身で資料を収集・提出して申請することもできます。このように、ご自身で後遺障害等級認定の申請をする方法を「被害者請求」と呼びます。
被害者請求によって申請する方が、申請時の書類をより万全なものにできるため、適切な認定を受けられる可能性がより高くなるといえるでしょう。
③認定結果に納得できないときは異議申立てをする
申請後、1~3か月程度を経て自賠責から文書で審査結果の回答がなされます。その結果に納得できない場合は、異議を申し立てることができます。
ただし、いったん出された認定結果を覆すのは簡単なことではありません。新たな資料を提出せずに異義だけ申し立てても結論が覆ることはまずないため、新たに検査を受けるなどしてさらに詳細な検査結果を提出するほか、専門的知見に基づく意見書などの資料を提出する必要があります。
異議申立てをするときには、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
(2)慰謝料に関する注意点
交通事故でむちうち(頚椎捻挫)となった場合は、入通院期間に応じた「入通院慰謝料」と、後遺障害が認定された場合には後遺障害等級に応じた「後遺障害慰謝料」を請求できます。
もっとも、これらの慰謝料の金額は、算定基準によって大きく異なってくることに注意が必要です。
慰謝料の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。この3つの算定基準の中では、自賠責保険基準による慰謝料額が最も低く、弁護士基準による慰謝料額最も高額となります。
したがって、同じ事案でも弁護士基準を用いて慰謝料を請求すれば、それだけで高額の慰謝料を受け取ることが可能になります。
①入通院慰謝料の計算方法
自賠責保険基準では、入通院期間中の慰謝料は1日あたり一律4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故については4,200円)で計算されます。
「入通院期間の総日数」と「実際に入通院した日数×2」のどちらか少ない方の数字に、上記の金額をかけたものが入通院慰謝料の金額となります。
弁護士基準では、一般的な場合とむち打ち症で他覚所見がない場合等に分けて、以下のように定められています。
【一般的な場合(単位:万円)】
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
【むちうち症で他覚所見がない場合等(単位:万円)】
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | ||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 |
②後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害が認定された場合の慰謝料は、自賠責保険基準でも裁判基準でも後遺障害等級別に定められています。
具体的な金額は以下の表のとおりです。どちらの基準で請求するかによって金額が大きく異なることが分かるでしょう。
(単位:万円)
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 | 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
第1級 | 1100 | 2800 | 第8級 | 324 | 830 |
第2級 | 958 | 2370 | 第9級 | 245 | 690 |
第3級 | 829 | 1990 | 第10級 | 187 | 550 |
第4級 | 712 | 1670 | 第11級 | 135 | 420 |
第5級 | 599 | 1400 | 第12級 | 93 | 290 |
第6級 | 498 | 1180 | 第13級 | 57 | 180 |
第7級 | 409 | 1000 | 第14級 | 32 | 110 |
(3)治療・通院での注意点
上でご説明したように、入通院慰謝料は入通院期間に応じて計算されます。そのため、適正な入通院慰謝料を受け取るためには、適切に入通院をする必要があります。
そこで、治療・通院においては次の3点に注意しましょう。
①速やかに継続して通院すること
まず、交通事故に遭ったらできる限り早めに医療機関を受診することです。事故からしばらくの期間が経って初めて受診すると、事故と負傷の因果関係を疑われるおそれがあります。事故当日に症状を感じなかった場合は仕方ありませんが、異常を感じたらすぐに受診しましょう。
受診後は継続して通院することも大切です。通院の頻度に関しては、主治医の指示に従うことになりますが、むちうち(頚椎捻挫)の場合は、おおむね週に2~3回の頻度で通院される方が多いといえます。
通院頻度が低いと適切な慰謝料額が受け取れないこともありますし、たまにしか通院していなかった場合、治療の必要性がなかったと保険会社に判断され、わずかな慰謝料しかもらえない場合もあります。
仕事が忙しくて通院が難しいこともあると思いますが、通院のためにやむを得ず仕事を休んだ場合には、仕事を休んだことによる損害を「休業損害」として請求していくことができますので、ご自身のためにお体を優先して、継続的に通院しましょう。
②整骨院・鍼灸院に通う場合は主治医に相談する
交通事故による傷病の治療費として賠償される費用は、あくまで「治療行為」によって生じた費用に限られます。
整骨院・鍼灸院での施術は医師が行うものではないため、その必要性に疑義が生じやすく、施術費用を治療費として認めてもらえない場合も多いので注意が必要です。
ただし、一定の場合に頚椎捻挫の症状の改善に有効であるということは知られているので、医師の指示による場合は整骨院や鍼灸院の施術費用も賠償され得ます。
整骨院・鍼灸院での施術を受けたい場合は、主治医に相談したうえ、念のために保険会社の担当者にも整骨院・鍼灸院に通っていいかどうかを確認しておきましょう。
③保険会社からの「治療費打ち切り」に安易に応じてはならない
むちうち(頚椎捻挫)の治療を始めてから3か月ほどが経過すると、保険会社が治療費の打ち切りを告げてくることがあります。その際、症状が改善されていないことを伝えても、後遺障害等級認定の手続をするか、自己負担で今後も通院するかを選ぶよう打診してくることもあります。
しかし、治療を続ける必要があるかないかに際しては、主治医による医学的判断が尊重されるべきです。安易に保険会社からの打診に応じて治療を打ち切ると、治るはずの症状も治らないおそれがあります。
また、治療期間中の慰謝料は入通院期間又は実通院日数に応じて算定されます。早期に治療を打ち切ると適切な慰謝料を受け取れなくなってしまうこともあります。
まだ傷病が治っていないのに保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、主治医によく相談してください。治療継続の必要性がある場合には、その旨の医学的な見解を保険会社に出して(主張して)治療費の支払いを継続してもらうようにしましょう。
4、交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になった人の損害賠償額シミュレーション

それでは、交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になった場合に、実際にどのくらいの損害賠償金がもらえるのかをケース別にみていきましょう。
むちうち(頚椎捻挫)で後遺障害が認められる場合の等級は基本的には14級、重いケースでは12級となるので、「12級」「14級」「非該当」の3パターンに分けてご紹介します。
なお、むち打ち症で後遺障害が認められたとしても、MRI等における他覚所見が明らかでかなりの重症である場合などを除いては14級と認定されるケースが大半です。
それぞれのパターンごとに、
- 1か月入院し、その後5か月通院したケース
- 入院せず、6か月通院したケース
の慰謝料を比べてみましょう。
後遺障害が認定された場合には、「後遺障害逸失利益」も受け取れるので、この点も併せてシミュレーションしてみます。
後遺障害逸失利益については、被害者が症状固定時に35歳、事故前年の年収が450万円のケースを想定して計算してみます。
①後遺障害等級12級の場合
ケース | 入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 |
入院1か月+通院5か月 | 141万円 | 290万円 | 537万4026円 |
通院6か月 | 116万円 | 290万円 | 537万4026円 |
※逸失利益の計算式は次のとおりです。
450万円(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×8.5302(ライプニッツ係数)
なお、むち打ち症で12級の場合、労働能力期間として10年が認められる例が多いため、労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)は10年を前提に計算しています。
②後遺障害等級14級の場合
ケース | 入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 |
入院1か月+通院5か月 | 105万円 | 110万円 | 103万0433円 |
通院6か月 | 89万円 | 110万円 | 103万0433円 |
逸失利益の計算式は次のとおりです。
450万円(基礎収入)×5%(労働能力喪失率)×4.5797(ライプニッツ係数)
なお、むち打ち症で14級の場合、労働能力期間として5年が認められる例が多いため、労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)は5年を前提に計算しています。
③後遺障害等級非該当の場合
ケース | 入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 |
入院1か月+通院5か月 | 105万円 | 0円 | 0円 |
通院6か月 | 89万円 | 0円 | 0円 |
※むち打ち症で他覚症状がない場合を想定しています。
入通院期間によっても慰謝料額が異なりますが、後遺障害等級によって慰謝料と逸失利益の金額が大きく異なることが分かるでしょう。
なお、後遺障害逸失利益について、詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
5、交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になったら弁護士に相談すべし!

交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になったら、保険会社との示談書にサインする前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。
たとえ弁護士費用がかかったとしても、弁護士に対応を依頼した方が最終的にプラスになるケースも多く、その場合には依頼を検討するとよいでしょう。
(1)適切な後遺障害等級認定を受けるためのアドバイスがもらえる
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、治療や検査の受け方に始まり、後遺障害等級認定申請(被害者請求)をする際の必要書類の作成・収集方法、認定結果に納得できない場合の異議申し立て方法に至るまで、数多くのポイントがあります。
弁護士に相談すれば、あなたの状況に応じて具体的なアドバイスが受けられます。
弁護士に依頼した場合には、被害者請求や異議申し立ての手続きは弁護士があなたに代わって的確に行ってくれるので、適切な等級を獲得できる可能性高まります。
(2)慰謝料を弁護士基準でもらえる
慰謝料は弁護士基準で計算するだけで増額できますが、弁護士基準は別名で「裁判基準」とも呼ばれ、本来は裁判をした場合にのみ用いられる基準です。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼した場合には、保険会社も示談交渉が決裂すれば裁判を起こされることは分かっていますので、弁護士基準による慰謝料額で示談できるケースも少なくありません。
つまり、同じ事案でも弁護士に示談交渉を依頼するだけで慰謝料の増額が期待できるのです。
(3)医師や保険会社への適切な対応をアドバイスしてもらえる
交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になった場合に1人で対応していると、医師や保険会社への対応に苦労することが少なくありません。
医師は必ずしも交通事故の損害賠償に関する知識を有しているわけではありません。そのために、後遺障害等級を獲得するために重要な検査であっても、「検査をして治るわけではない」と考え、検査してくれないこともあります。
また、後遺障害診断書の的確な記載方法を知らない医師も少なくありません。むしろ、交通事故による負傷者を専門的に扱っている医師以外は、よく知らないものです。
保険会社は、前記「3」(3)③でご説明したように、治療の途中でも治療費を打ち切ってくることがあります。
また、治療終了後の示談交渉では、被害者を素人扱いして不利な示談案を一方的に押しつけてくることも少なくありません。
以上の事態に適切に対応するためには、専門的な知識が要求されます。
そこで、弁護士に相談すれば、状況に応じて具体的なアドバイスが得られます。弁護士に依頼した場合には、あなたに代わって弁護士が医師や保険会社にも対応してくれるので、安心できます。
6、交通事故でのむちうち事件(頚椎捻挫)での弁護士費用

弁護士に相談・依頼した方が有利になる可能性があるとはいっても、弁護士費用がいくらかかるのかは気になるところでしょう。弁護士の力で賠償金をアップできたとしても、費用倒れになってしまっては元も子もありません。
そこで、ここでは交通事故でのむちうち(頚椎捻挫)事件における弁護士費用の相場をご紹介します。
(1)弁護士特約に入っている場合
ご自身が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、特約を使うことによって、自己負担なしで弁護士に相談・依頼ができます。
弁護士にかかる費用は、300万円まで(法律相談料については別途10万円まで)を上限として、保険会社が支払います。
この上限を超えるのは、よほど重傷で重度の後遺障害が残るケースに限られますので、ほとんどの場合は心配いりません。
弁護士費用特約を使っても保険の等級が下がることはありませんので、加入している場合は遠慮なく特約を使うとよいでしょう。
(2)弁護士特約に入ってない場合
弁護士費用特約に入っていない場合は、自腹で弁護士費用を支払わなければなりません。
弁護士費用は、各弁護士ごとに異なりますが、交通事故でのむちうち(頚椎捻挫)事件における弁護士費用の相場は、以下のようになっています。
①法律相談料
30分あたり5,000円程度です。ただし、初回に限り無料で相談を受け付けている法律事務所も多くあります。
②着手金
経済的利益の額(加害者に請求する金額)に応じて、以下の基準を目安としつつ、具体的な事情に応じて決められるのが一般的です。
経済的利益の額 | 着手金額 |
300万円以下の場合 | 8% |
300万円超~3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円超~3億円以下 | 3%+69万円 |
③報酬金
経済的利益の額(弁護士の事件処理によって加害者から回収できた金額)に応じて、以下の基準を目安としつつ、具体的な事情に応じて決められるのが一般的です。
経済的利益の額 | 報酬金額 |
300万円以下の場合 | 16% |
300万円超~3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円超~3億円以下 | 6%+138万円 |
なお、着手金の分割払いに応じる事務所もありますし、着手金無料で成功報酬型の料金体系を採用している事務所もあります。初期費用が準備できなくても依頼できる法律事務所も少なくありませんので、探してみるとよいでしょう。
ただし、弁護士費用は安ければよいというわけではありません。弁護士を選ぶ際には、「交通事故の案件に強いこと」を最低条件としましょう。
まとめ
交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になった方へ弁護士が一番伝えたいことを再度申し上げますと、むちうち(頚椎捻挫)は後遺障害にあたる可能性があり、高額の賠償金がもらえるはずなのにわずかな賠償金しかもらっていない人が少なくないということです。
ご自身で保険会社と交渉して示談した場合でも、それなりの金額をもらえるケースはあります。
そのような場合、本人は納得していても、弁護士基準と比較すればかなり低い金額となっているケースも数多く存在します。
損害賠償金の基準等を知らないがために損をしてしまっている人が非常に多いのです。
交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になったケースの損害賠償請求にはこのような問題がありますので、適切な損害賠償を受けるためには、事故後できる限り早いうちに弁護士に相談して、正しい知識を得ておくことをおすすめします。