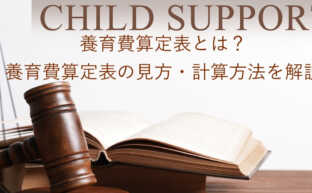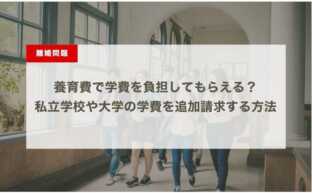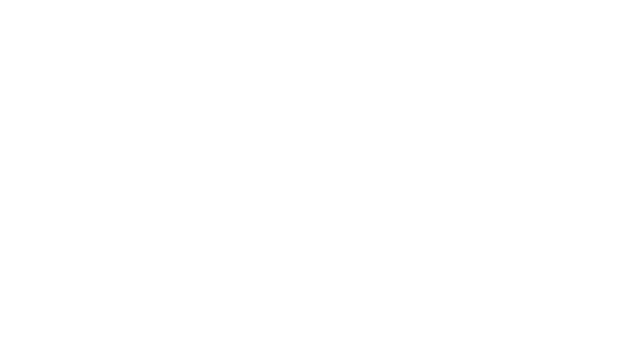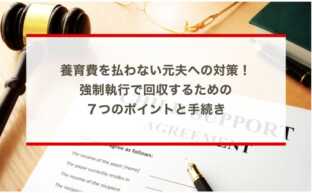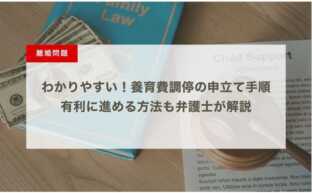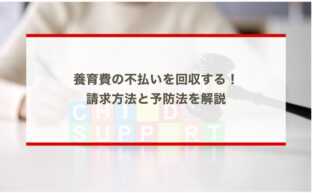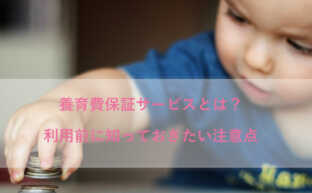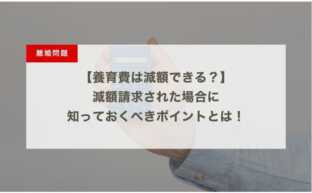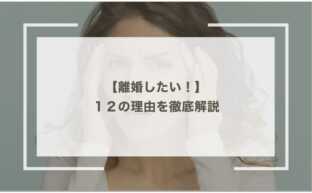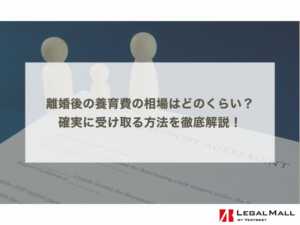
「離婚後、養育費は具体的にどれくらいもらえるのか気になりますよね。相場を知りたいと思います!」
養育費とは、未熟な子供が自立するまでに必要な費用を指します。
離婚後に未成年の子供を引き取る場合、(元)パートナーから養育費を請求することが可能です。
養育費の額は、両親間で話し合いによって合意することができますが、一般的な相場を知らないと、適切な金額を決めるのは難しいでしょう。
ここで、次の内容について、経験豊富なベリーベスト法律事務所の専門弁護士が詳しく解説します。
一般的な養育費の相場
適正な養育費の評価方法
養育費を最大限に得るための交渉術
養育費は離婚後、子供を育てるために不可欠な支援です。
この記事が、適切な養育費の受け取り方を理解し、確実に実行する手助けとなれば幸いです。
目次
1、世間一般における養育費の平均相場は?

子供を連れて離婚する人が気になるのは、実際に養育費を「いくらもらえるのか」「いくら請求すればよいのか」ということでしょう。
そこでまずは、世間一般の離婚した夫婦間において、どれくらいの養育費が支払われているのか、平均相場をご紹介します。
(1)母子世帯の平均相場は5万485円
厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果」によれば、(元)パートナーから養育費を受け取っている母子世帯における1か月あたりの全体的な平均相場は5万485円とされています。
もっとも、子供の人数によって養育費の金額が異なっており、子供の人数が多いほど高額となる傾向にあります。内訳は以下のとおりです。
- 子どもが1人の世帯:4万468円
- 子どもが2人の世帯:5万7,954円
- 子どもが3人の世帯:8万7,300円
- 子どもが4人の世帯:7万503円
(2)養育費をもらっている母子世帯はわずか24.3%
上記の調査結果を見て、「意外にしっかりもらっているんだな」と思った人もいるのではないでしょうか。
しかし、実際には養育費をもらえていない世帯も多いことに注意が必要です。
上記の調査で、母子世帯のうち養育費をもらっている世帯はわずか24.3%に過ぎないという結果も出ています。
つまり、シングルマザーのうち養育費をもらっている人は、4人に1人もいないという状況です。
毎月4万3,707円というのは、養育費をもらっている人の平均値ですので、もらっていない人も含めれば、平均相場はごくわずかな金額ということになります。
(3)実際には子ども1人あたり11万円~12万円が必要
世間一般で支払われている養育費の平均相場は上記のとおりですが、実際に子どもを育てるためにどれくらいのお金が必要になるのかを知っておくことも大切です。
さまざまな試算によれば、子どもが生まれてから大学を卒業するまでに必要な金額は、1人あたり概ね3,000万円程度と言われています。
単純計算で、3,000万円を22年(264か月)で割ると、1か月あたりの金額は11万円~12万となります。
もちろん、子どもが小さいうちはこれほどの金額は必要ありませんが、高校生や大学生になれば学費もかかってきますので、上記の金額でも足りなくなるでしょう。
2、養育費の正しい相場(適正金額)は裁判所が公表している

実は、世間一般で支払われている養育費の金額は、必ずしも適正なものとはいえません。
そこで、ここでは養育費の適正金額としての正しい相場をご紹介します。
(1)養育費算定表とは
養育費の適正金額を調べるには、裁判所が公表している「養育費算定表」を見るのが便利です。
本来は養育費の金額を算定するには複雑な計算が必要となりますが、個別のケースごとに実際に計算するのは困難です。
ただ、通常は次の4要素によって養育費の金額が概ね決まってきます。
- 子供の人数
- 子供の年齢
- 義務者(養育費を支払う義務を負う者)の年収
- 権利者(養育費を受け取る権利を有する者)の年収
この4要素の具体的な数値に応じて養育費の目安が簡単に分かるようにまとめられた早見表が、「養育費算定表」です。
養育費算定表の改訂版は、こちらの裁判所のページから確認していただけます。
参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
(2)養育費算定表の見方
養育費算定表は、子どもの人数・年齢ごとにそれぞれ別の表が用意されています。
ですので、まずは上記の裁判所のページから、ご自身のお子様の人数・年齢に応じた算定表を開きましょう。
算定表には、義務者(養育費を支払う側)の年収と権利者(養育費をもらう側)の年収に応じて、養育費の金額が掲載されています。
あなたが権利者である場合は、まず(元)パートナーの年収を確認し、算定表の縦軸に記載されている年収額の中から該当する欄を見つけます(①)。
そこから、右に線を引いていきましょう(②)。
次は、横軸に記載されている年収額の中から、あなたの年収に該当する欄を見つけます(③)。
そこから、上に線を引いていきましょう(④)。
以上の2本の線が交わる欄に記載されている金額が、あなたがもらうことのできる養育費の金額(適正金額)になります(⑤)。
仮にパートナー(会社員)の年収が500万円、あなた(パート勤務)の年収が150万円だとすれば、養育費算定表による金額は月4~6万円となります。
(3)養育費の計算方法
養育費算定表に掲載されている金額には、1~2万円の幅があります。
基本的にはその幅の範囲内で、各世帯の生活状況などに応じて決めることになりますが、ピンポイントで養育費の金額を計算する方法もあります。
本来の養育費の計算式は、以下のとおりです。
子供の生活費×{義務者の基礎収入÷(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)}=1年間の養育費
子供の生活費や義務者・権利者の基礎収入を計算する方法は複雑なので、ここでは説明を割愛します。
上記の(2)の例をこの計算式に当てはめると、義務者が負担すべき1年間の養育費は51万2,387円で、1か月あたり4万2,699円となります。
養育費算定表で割り出した金額は月4~6万円でしたが、この幅の中では低い方の金額ということになります。
本来の養育費の計算方法を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
3、養育費早見表でチェック!養育費の正しい相場

裁判所の養育費算定表は見づらい、難しそう……と感じる方もいらっしゃることでしょう。
そんな方のために見やすい早見表を用意しましたので、こちらで養育費の相場をチェックしましょう。
(1)養育費早見表
こちらの早見表で子供の人数と年齢で該当する行において、義務者・権利者の年収を選択していただくと、あなたがもらえる養育費の目安がすぐに分かります。
(2)両親が離婚した場合と未婚で認知したケースで養育費は異なる?
養育費算定表では、両親が離婚した場合と未婚で認知したケースとで養育費はまったく同じ金額となります。
(3)東京の場合と地方の場合で養育費は異なる?
東京等の大都市圏と地方では必要な生活費が異なりますが、養育費算定表では特に考慮されていません。
ただし、養育費の金額における幅の中で、大都市圏では高い方の金額となりやすく、地方では低い方の金額となりがちという傾向があります。
4、養育費を確実に獲得するための請求方法
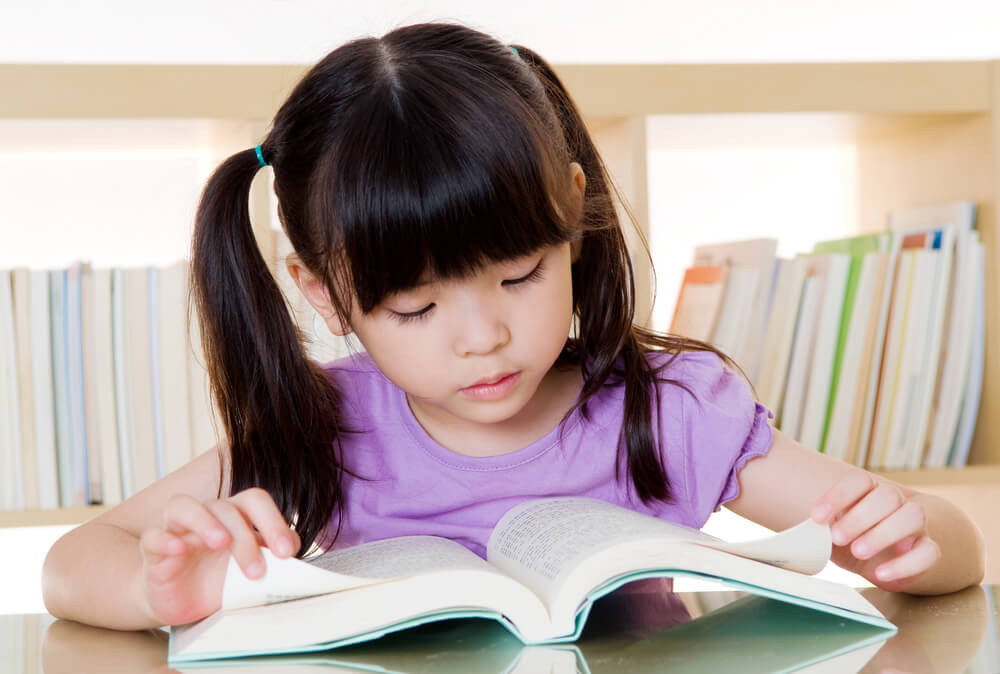
そこで次に、適正な金額の養育費を請求する方法を解説します。
養育費を取り決める際には、裁判所の養育費算定表が重視されますが、算定表の金額はあくまでも目安であり、法的な拘束力はありません(ただし、調停、審判及び裁判では、ほとんどのケースで養育費算定表の範囲内で定められます)。
そのため、まずは養育費算定表に記載された金額に縛られることなく、子どもを育てるために必要かつ適正と考える金額を話し合って決めることが重要です。
子育てに支障をきたさないため、妥協せずにきっちり交渉して、少しでも多くの養育費の獲得を目指しましょう。
(1)できるだけ多くの養育費を獲得するコツは?
①きちんと相手の収入を把握しておく
相手の収入が多ければ多いほど、もらえる養育費は多くなります。
そのため、相手が過少申告してきても適正な養育費を獲得できるよう、きちんと相手の収入を把握できるようにしておくべきでしょう。
②これからの子どもの学習計画をある程度明確にしておき、主張する
まだ子どもが幼いとしても、将来のことを考えずに養育費を決めてしまうと、後で多額の教育費が必要になった場合などは支払いが困難となります。
また、子どもが様々な選択肢から自分の将来を決定できるようにするために、教育費に充てられる金額は余裕を持って決めておくべきでしょう。
余裕ある教育費を含んだ養育費をもらえるようにするには、現時点で分かっている範囲での学習計画を立てておき、その計画に基づいて交渉するべきです。
例えば
- 小学校5年生から学習塾に通わせる
- 高校は県内有数の私立学校に通わせる
- 中学2年生から家庭教師を雇う
などです。
学習塾の受講料や私立学校の授業料については、それぞれ月額2万円、月額5万円などと、交渉前にあらかじめおおよその相場を確認しておき、計画に盛り込んでおくとよいでしょう。
③面会交流に適度に応じる
非親権者となった相手方には、子どもと継続的に会って親子の交流を図る「面会交流」を行う権利があります。
適正な金額の養育費を獲得するためには、面会交流に適度に応じるのが得策です。
なぜなら、定期的に面会交流を行ってもらうことで、相手方の子どもに対する愛情も維持されますし、養育費を支払うモチベーションや責任感が強まることも期待できるからです。
(2)支払い方法を工夫することで養育費をもらえる確実性が増す
養育費の支払い方法としては、義務者が権利者の口座へ毎月一定額を振り込む形を取るのが一般的です。
しかし、この方法では義務者が振込みを怠る危険性が少なからずあります。
そこで、より確実に養育費を受け取るために、支払い方法を工夫してみるのもよいでしょう。
①一括払いで養育費を受け取る
両親が合意すれば、将来の養育費を一括で支払ってもらうこともできます。
ただし、一括払いで養育費を受け取ると、トータルで見れば本来もらえるはずの金額よりも相当に少なくなってしまうケースが多いことに注意が必要です。
子供が小さければ小さいほど、その差が大きくなりがちです。
そこで、「事情の変更があった場合には、改めて養育費の分担について協議する」という合意も取り付けておいた方がよいでしょう。
②金銭以外の財産で受け取る
養育費は金銭に限らず、他の財産で受け取ることも可能です。
例えば、これまで家族で住んでいたマイホームを養育費代わりに財産分与として権利者がもらうという方法がよく行われています。
ただし、住宅ローンが残っている場合は、義務者がその返済を怠ると最終的に権利者と子供がその家から追い出されてしまうかもしれないというリスクはあります。
また、義務者の不倫やDVなどといった有責行為により離婚に至った場合には、慰謝料も含めて必要な財産を要求することも可能です。このことを「慰謝料的財産分与」といいます。
③必ずしも権利者名義で養育費を受け取る必要はない
義務者が「権利者への振り込みでは何に使うか分からない」という理由で、養育費の支払いを渋るケースもあるでしょう。
そんなときは、私立学校の学費、塾や習い事の費用などの振替口座を義務者の口座に設定し、その口座から自動的に引き落とされるようにしておくことも良いでしょう。
また、面会交流の際に子供へ小遣いを渡したり、服飾品を購入したりするなどの約束を取り付けることも考えられます。
ただし、以上のように約束したとしても、義務者が口座に必要なお金を入金しなかったり、子供へ小遣いを渡さなかったりするリスクはあります。
このようなリスクを回避するためにも、次にご説明する「公正証書」の作成が重要となります。
(3)話し合いがまとまったら公正証書を作成しておく
以上の点に注意しつつ相手方と交渉し、話し合いがまとまったら、口約束だけで済ませずに離婚協議書や合意書を作成しましょう。
これらの書面を作成する際は、公正証書にしておくことが大切です。
もし相手方が約束どおりに養育費を支払わない場合、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば裁判をしなくてもすぐに強制執行を申し立て、相手方の給料や預金口座などの財産を差し押さえることができるからです。
(4)話し合いがまとまらなければ調停・審判をする
どうしても話し合いがまとまらない場合や、相手方が話し合いに応じないときは、家庭裁判所へ「養育費請求調停」を申し立てましょう。
調停では、家庭裁判所の調停委員のアドバイスや説得を交えて話し合いが進められるため、当事者だけで話し合うよりも合意に至りやすくなります。
調停でも話し合いがまとまらない場合は「調停不成立」となり、自動的に審判の手続きに移行します。
審判では、それまでに提出された資料などを基にして、審判官(裁判官)が養育費の支払い方法や金額を決定します。
なお、いきなり審判を申し立てることも可能ですが、ほとんどの場合は家庭裁判所の判断で、まずは調停に付されることになります。
(5)途中で相手が養育費を支払わなくなった場合は?
もし、途中で相手が養育費を支払わなくなったとき、公正証書がある場合や、調停・審判・裁判をした場合には、強制執行を申し立てることによって養育費を回収できます。
調停・審判・裁判をした場合なら、家庭裁判所から履行勧告や履行命令を出してもらうこともできます。
当事者間の離婚協議書や合意書(公正証書にしていないもの)しかない場合には、調停や審判、裁判を起こした上で以上の手段を取ることになります。
なお、最近では民間の業者による「養育費保証サービス」も広まってきています。
保証料について自治体の補助を受けられるところもありますので、養育費保証サービスの利用を検討してみるのもよいでしょう。
5、養育費は相場より増額させることはできる?

いったん相場どおりに養育費を取り決めた場合に、将来、必要に応じて増額できるのでしょうか。
(1)事情が変われば金額の変更も可能
まず、当事者間の話し合いで合意ができれば、自由に養育費の金額を変更することができます。
しかし、実際には増額を求めても相手方が応じてくれないことが多いものです。
そのようなときでも、事情が変わった場合には、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用することで、養育費の金額を変更することができます。
事情が変わった場合には改めて現在の事情を考慮して、子どもの養育のために適切で、かつ、現実的と考えられる養育費の金額を決めなおすことが認められているのです。
(2)増額される要素
養育費の金額を変更する際には、さまざまな「事情」が総合的に考慮されます。
そのため、増額される条件を一概にいうことはできません。
ですが、増額が認められやすい要素として、以下のような事情を挙げることができます。
- 子供の進学によって教育費が増大した
- 子供の病気や怪我のために想定外の医療費が必要となった
- 親権者が病気や失業などによって収入が減った
- 物価の上昇や増税など社会情勢の変化によって生活が苦しくなった
ただし、社会情勢の変化については、相手方の生活も同じように苦しくなっている場合には、増額は認められにくくなります。
職種や雇用形態などの違いによって、ご自身の生活のみが苦しくなり、相手方の生活には影響がないというような場合には、増額が認められやすいでしょう。
(3)養育費の増額を請求する方法
相手方に直接連絡できる場合は、連絡をして事情を話し、増額を求めてみるとよいでしょう。
直接話し合いにくい場合や、相手方が話し合いに応じようとしない場合には、内容証明郵便で増額請求書を送付するのがおすすめです。
話し合いがまとまったら、新たに合意書を作成し、公正証書にしておきましょう。
話し合いができない場合や、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費増額請求調停」を申し立てます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判の手続に移行し、家庭裁判所が養育費の金額を新たに決めてくれます。
養育費増額の請求方法についてさらに詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
6、養育費は相場より減額されることもある?

では、逆に養育費が相場より減額されることもあるのでしょうか。
(1)支払者の事情によっては減額を求められることも
養育費算定表の金額はあくまでも目安ですので、もらう側に特別の事情がある場合には増額できるのと同様、支払う側に特別の事情がある場合には減額されることもあります。
また、いったん相場どおりに取り決めた後でも事情が変われば金額の変更も可能なのですから、支払う側の事情が変われば減額される可能性もあることになります。
(2)減額される要素
養育費の減額が認められやすい要素としては、以下の事情を挙げることができます。
- 親権者が再婚して、子供と再婚相手が養子縁組をした場合
- 非親権者が病気や失業などによって収入が減った
- 非親権者に新たに子供が生まれ、扶養すべき人数が増えた
- 物価の上昇や増税など社会情勢の変化によって生活が苦しくなった
社会情勢の変化については、もらう側にとっては増額の必要性として挙げられるものですが、支払う側が現実にいままでどおりの金額を支払うのが難しい場合には、減額が認められる可能性があります。
(3)減額を請求されたときの対処法
元パートナーから養育費の減額を請求されたときの対処法も、基本的な考え方としては、養育費を新たに請求する場合や増額を請求する場合と異なるところはありません。
つまり、養育費として必要な金額とその根拠を具体的に主張して、理解を求めることになります。
話し合いがまとまらなければ元パートナーから「養育費減額請求調停」を申し立てられる可能性もありますが、その前によく話し合うことで柔軟な解決方法が見つかることもあります。
養育費を少しでも多く回収するためには、このように相手の経済状況を改善する方法を考えてあげるなど、柔軟な対処法が有効な場合もあります。
その他、減額を請求された場合の対処法についてはこちらの記事でも解説していますので、併せてご参照ください。
7、養育費でお困りのときは弁護士へ相談を

ここまで、養育費の相場や養育費算定表の使い方、養育費の増額・減額をめぐる問題などについて解説してきました。
しかし、実際に適切な養育費を獲得するためには、専門的な知識や交渉力などが要求されます。そのため、お困りの際は弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に詳しい事情を伝えれば、適切な養育費の金額を判断してもらえますし、元パートナーと交渉する際のポイントなどについてもアドバイスが得られます。
養育費の請求手続きを依頼すれば、交渉は弁護士が代わりに行ってくれますし、調停や審判、裁判でも全面的にサポートが受けられます。納得できる金額の養育費を獲得することが期待できるでしょう。
離婚後の養育費についてのQ&A
Q1.世間一般における養育費の平均相場は?
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によれば、(元)パートナーから養育費を受け取っている母子世帯における1か月あたりの全体的な平均相場は4万3,707円とされています。
Q2.母子世帯のうち養育費をもらっている世帯の割合は?
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によれば、母子世帯のうち養育費をもらっている世帯はわずか24.3%に過ぎないという結果も出ています。
Q3.実際に子どもを育てるためにどれくらいのお金が必要になる?
子どもが生まれてから大学を卒業するまでに必要な金額は、1人あたり概ね3,000万円程度と言われています。単純計算で、3,000万円を22年(264か月)で割ると、1か月あたりの金額は11万円~12万となります。
離婚時の養育費の相場まとめ
養育費を請求することは正当な権利であり、お子さまの成長のために大切なことでもあります。
しかし、実際には相場どおりの養育費を獲得することが容易ではないケースも少なくないものです。
お困りのときは、離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士が豊富な経験に基づいて、あなたの状況に応じて最適な解決方法を柔軟に考えてくれるはずです。
専門家のサポートを受けて、適切な養育費を獲得しましょう。