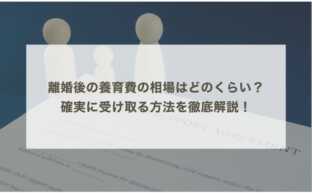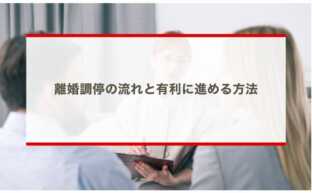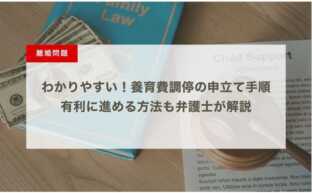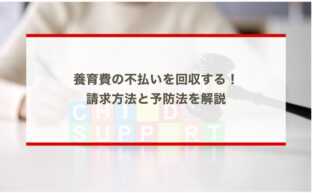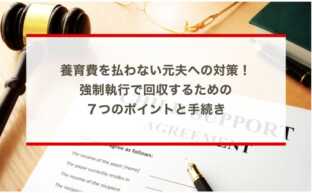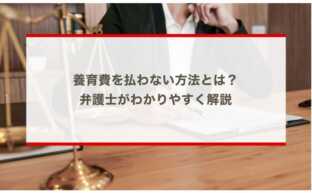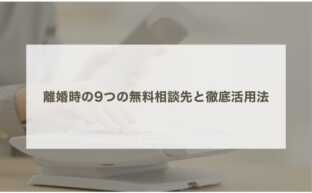離婚した元パートナーが子どもの養育費を支払わない場合、裁判手続きを通じてその請求と回収を行うことが可能です。
養育費の請求と回収のための裁判手続きは、状況に応じてさまざまな方法が用意されており、以下の8つの方法があります。
・夫婦関係調整調停(離婚調停)
・離婚訴訟
・婚姻費用分担請求調停・審判
・養育費請求調停・審判
・養育費増額請求調停・審判
・養育費減額請求調停・審判
・履行勧告・履行命令
・強制執行
この記事では、養育費を取り戻したい方々に向けて、さまざまな状況に応じた裁判手続きを、詳細に弁護士が解説します。
目次
1、養育費の裁判とは?
養育費は、未成熟な子どもが自立できるようになるまで育てていくために必要なお金のことです。
子どもは両親が共同して育てるものなので、養育費もそれぞれの経済力に応じて分担すべきこととされています。
両親が離婚しても親子関係は続きますので、子どもを引き取って育てる側の親(親権者)は元パートナーに対して養育費を請求することが法律で定められています。
この法律上の権利を実現するために、さまざまな裁判手続きが用意されています。
2、裁判で高額の養育費を獲得するためのポイント
せっかく裁判をして養育費を請求するなら、できるかぎり高額の養育費を獲得したいところです。
ここでは、裁判で高額の養育費を獲得するためのポイントをご紹介します。
(1)適正な養育費の金額を知っておく
まずは、一般的にどれくらいの養育費がもらえるのかを知っておくことが大切です。
高額の請求をしても必ずしも認められるものではありませんが、相場より低い請求をするとその分しか獲得できなくなるからです。
養育費の金額は、裁判においては基本的に養育費算定表に従って決められます。
養育費算定表では、両親の収入と子どもの人数・年齢に応じて養育費の目安が示されています。
養育費の相場についてさらに詳しくはこちらの記事で解説していますので、併せてご参照ください。
(2)相手方の財産・収入を明確にする
養育費算定表が使われる場合は、ほぼ機械的に養育費の金額が割り出されるのが通常です。
子どもの人数・年齢を動かすことはできませんので、適正な金額を割り出すためには裁判所に対して両親の収入を正確に申告することが重要です。
もし、元パートナーが収入を過少申告すれば、養育費として低い金額しか獲得できなくなります。
また、収入の他に保有資産が考慮されることもあるので、元パートナーの資産が多い場合には財産状況も明らかにしたいところです。
相手の財産・収入が不明な場合、訴訟に至れば「調査嘱託」や「文書送付嘱託」の申し立てといった裁判上の手続きによって調査することもできますが、調停や審判ではなかなか難しいのが実情です。
したがって、離婚前に同居している段階から、元パートナーの給料明細などの資料を確認して財産・収入を調べておくのが望ましいといえます。
(3)生活費や学費など必要な金額を明確にする
裁判では養育費算定表が機械的に適用されることが多いのですが、それを超える金額の養育費を獲得することも一切できないわけではありません。
特に、調停では元パートナーを説得することができれば高額の養育費を獲得することも可能です。
審判や訴訟でも、状況によっては高額の養育費の支払いが命じられる可能性もあります。
そのためには、生活費や学費などにどれくらいの金額が必要になるのかを明確に割り出して、その根拠とともに裁判手続きの中でしっかりと説明することが重要となります。
(4)有力な証拠を提出する
高額な養育費を裁判で獲得するためには、必要な金額とその根拠を証明できる証拠を提出することも重要です。
有力な証拠としては、自分と元パートナーの給料明細など収入や財産に関する証拠の他、例えば子どもが医学部への進学を希望しているために高額の学費を必要としている場合には学校の通知表や模試の成績などを提出することが考えられます。
子どもの病気やケガのために高額の治療費を要する場合には、医師の診断書や病院の診療報酬明細書などが有効となるでしょう。
3、これから離婚する人が裁判で養育費を請求する手続きの流れ
ではここから、実際に裁判で養育費を請求する手続きの流れをご紹介します。
まずは、これから離婚する人がパートナーに養育費を求めたい場合の手続きをみていきましょう。
(1)離婚調停を申し立てる
まだ離婚が成立していない人の場合は、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てて、この調停の中で養育費も請求することになります。
離婚問題については、まず調停を申し立てなければならないこととされているので、いきなり審判や離婚訴訟を起こすことはできません。
(調停前置主義)
第二百五十七条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
引用元:家事事件手続法
調停とは、家庭裁判所において男女1名ずつの調停委員を介して相手方と話し合う裁判手続きのことです。
調停委員が中立・公平な立場でアドバイスや説得を交えて話し合いを進めてくれるので、当事者だけで話し合うよりも合意に至りやすくなるというメリットがあります。
離婚調停の場合、養育について合意できても、慰謝料や財産分与など他の争点について合意ができなければ解決できないことに注意が必要です。
(2)調停が不成立となったら離婚訴訟を起こす
離婚調停がまとまらない場合は、離婚審判の手続に移行する場合もありますが、一般的には離婚訴訟に進みます。
なぜなら、審判に移行した場合は、調停委員から勧められた調停案どおりの(または近い)内容の審判が下る可能性が高く、また当事者から異議が出た場合、訴訟に移行するため実効性に乏しいからです。
調停案に納得できない当事者が、自分の主張を裁判所に認めてもらうためには、強力な証拠を提出するなどして徹底的に争う必要があります。
そのため、調停で決裂した場合には通常、離婚訴訟を起こした方がよいでしょう。
(3)主張と証拠を提出し合う
離婚訴訟では、家庭裁判所で離婚問題について、通常の訴訟と同じルールのもとに当事者が主張や証拠を出し合います。
最終的に、自分の主張を裏づける事実を証拠で証明できた側が勝訴判決を獲得することになります。
証拠がなければ訴訟で勝つことはできませんので、養育費についてパートナーとの話し合いがまとまらないと思ったら、早い段階で証拠を集めておくことが大切です。
(4)証人尋問・本人尋問が行われる
原告と被告の双方が主張と証拠書類を出し尽くしたら、証人尋問と本人尋問が行われます。
証人と本人の法廷での供述も証拠となりますので、有力な証人を立てるとともに、本人尋問では自分の主張に矛盾がなく正当なものであることを裏づける事実をしっかりと述べることが重要となります。
(5)途中で和解が成立することもある
訴訟では、判決が言い渡される前に裁判所から和解を勧められ、話し合いが行われることもよくあります。
和解を勧められるタイミングとしては、主に証人尋問・本人尋問の前と後です。
当事者の主張と証拠書類が出そろうと、裁判官はすでに判決内容についておおよその心証を固めているものです。
そのまま尋問を行って判決言い渡しに進んでもよいのですが、できることなら当事者双方が納得できる解決を図る方がベターであるため、尋問前に和解を勧められることが多いのです。
尋問が終了すると、裁判官はほぼ完全に心証を固めています。
ただ、最後にもう一度、柔軟な解決を図るために和解を勧めてくるケースが多いです。
これらのタイミングで、納得できる和解案を示され、パートナーも合意する場合には和解に応じるのもよいでしょう。
(6)和解できなければ判決が言い渡される
和解が成立しない場合は、尋問終了後に当事者双方が最終的な意見をまとめた書面を提出して結審し、判決が言い渡されることになります。
判決で決められる養育費の金額は、やはり養育費算定表に掲載されている金額の範囲内となることがほとんどです。
そのため、養育費算定表を超える金額を求める場合は、その金額と根拠を主張し、有力な証拠を提出しておく必要があります。
なお、判決で養育費を獲得できるのは、離婚を求める側が勝訴したときだけです。
敗訴するとそもそも離婚が認められませんので、養育費について裁判所の判断は下されません。
したがって、パートナーが離婚そのものに反対している場合には、相手の離婚原因についても主張と証拠を提出しておかなければなりません。
4、すでに離婚した人が裁判手続きで養育費を請求する流れ
すでに離婚した人が養育費を請求するための裁判手続きは、調停と審判のみです。訴訟はありません。
(1)養育費請求調停を申し立てる
まずは、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てましょう。
離婚調停の場合と異なり、養育費を請求するのみの場合は調停前置主義は適用されませんので、いきなり審判を申し立てることも可能です。
しかし、いきなり審判を申し立てても、ほとんどの場合は「まずは話し合ってみましょう」という家庭裁判所の判断で、調停に付されることになります。
そのため、通常は調停を申し立てた方がよいでしょう。
(2)調停不成立の場合は養育費請求審判に移行する
養育費請求調停で話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合は、自動的に審判の手続きへ移行します。
審判では、調停段階で当事者が提出した主張や証拠、家庭裁判所調査官による調査結果などに基づいて、裁判所が相当と考える解決方法を命じます。
新たに主張や証拠を提出することもできるので、できる限り提出するようにしましょう。
なお、家庭裁判所が下した審判の内容に納得できないときは、異議申し立てと即時抗告の手続きをとることによって、改めて審理をしてもらうことができます。
ただし、一度下された審判を覆すことは簡単ではないので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
5、離婚前の別居中に裁判で養育費を含む生活費を請求する手続きの流れ
パートナーと別居していても、離婚が成立するまでは夫婦ですので、夫婦の生活費の分担を請求することができます。
ここにいう夫婦の生活費のことを「婚姻費用」といいます。
請求する側が子どもを監護している場合、婚姻費用には養育費も含まれます。
パートナーとの話し合いによって婚姻費用を払ってもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
別居中に離婚調停を申し立てる場合には、離婚調停と婚姻費用分担請求調停の2つを同時に申し立てるのが一般的です。
この場合、離婚調停が長引いたとしても、婚姻費用分担請求調停については1回の期日で成立し、婚姻費用を払ってもらえるようになることも多いです。
離婚問題については時間をかけて検討したいという場合には、婚姻費用分担請求調停のみを申し立てることも可能です。
婚姻費用分担請求調停について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
6、離婚後に養育費を払われなくなったときに裁判で回収する手続きの流れ
離婚時または離婚後に養育費を取り決めたにもかかわらず不払いとなった場合にも、裁判手続きを利用して元パートナーから養育費を回収することが可能です。
なお、裁判外で養育費を取り決めていた場合は、離婚協議書や合意書を公正証書にしていなければ、まずは養育費請求調停または審判を申し立てる必要があることにご注意ください。
(1)家庭裁判所の履行勧告・履行命令を申請する
家庭裁判所の調停・審判・訴訟といった裁判手続きで養育費の支払いが定められている場合で、元パートナーが決められたとおりに支払わない場合には、家庭裁判所の履行勧告・履行命令を申請することができます。
履行勧告とは、家庭裁判所から元パートナーに対して、「決められたとおりに支払いなさい」と催促してくれる制度のことです。
ただ、履行勧告には強制力がありませんので、なかなか支払わない元パートナーに対しては履行命令を申請した方がよいでしょう。
履行命令が発出されると、元パートナーが従わない場合には10万円以下の過料を課されることがあるので、一定の強制力が期待できます。
(2)強制執行を申し立てる
家庭裁判所が発行した「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」がある場合の他、当事者間で養育費を取り決めた場合でも「公正証書」にしている場合は、強制執行の申し立てが可能です。
具体的には、差押えの対象となる元パートナーの財産を特定した上で、「差押命令の申し立て」という手続きを行います。
この手続きによって相手の給料を差し押さえた場合は、勤務先会社から毎月一定額を直接支払ってもらえるようになります。
預金口座を差し押さえた場合は、口座残高の中から養育費を受け取ることができます。
元パートナーの財産を特定できなければ、強制執行を申し立てることはできません。
しかし、2020年4月1日から施行されている改正民事執行法において「財産開示手続」が強化されています。
相手の財産が不明の場合は、まず財産開示手続を利用するようにしましょう。
7、離婚後に養育費の増額を裁判で請求する手続きの流れ
現在、元パートナーから養育費をもらっているものの、過去に取り決めた金額では足りなくなった場合には、家庭裁判所に「養育費増額請求調停」を申し立てることができます。
ただし、増額請求は無制限に認められるものではありません。
増額が認められやすいのは、以下のような事情がある場合です。
- 自分の収入が大幅に減った
- 元パートナーの収入が大幅に増えた
- 子どもが小さいときに学費を考慮せず養育費を取り決めたが、子どもが成長して学費がかかるようになった
- 子どもが病気やケガをして継続的に医療費が必要となった
- 現在もらっている養育費の金額が相場より低い
養育費増額請求調停においても、調停で話し合いがまとまらなければ審判に移行し、家庭裁判所が増額の可否と金額を決定します。
8、離婚後に養育費の減額を裁判で請求する手続きの流れ
あなたが養育費を支払っている立場の場合、離婚後のさまざまな事情によって養育費の支払いが難しくなることもあるでしょう。
そんなときは、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てることができます。
減額が認められやすいのは、以下のような事情がある場合です。
- 自分の収入が大幅に減った
- 自分が再婚し、扶養家族が増えた
- 元パートナー(親権者)の収入が大幅に増えた
- 元パートナー(親権者)が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした
- 現在支払っている養育費の金額が相場より高い
養育費減額請求調停においても、調停で話し合いがまとまらなければ審判に移行し、家庭裁判所が増額の可否と金額を決定します。
9、養育費の請求・回収で裁判をお考えなら弁護士に相談を
この記事では、(元)パートナーが養育費を払ってくれない場合に請求・回収したい場合を中心に、利用可能な裁判手続きについて解説してきました。
以上にご紹介した裁判手続きはいずれも、ご自身でも利用できますが、中には複雑な手続きを要するものもあります。
調停の手続きはそこまで複雑なものではありませんが、適正な金額の養育費を獲得するためには、専門的な知識や交渉力が必要になります。
そのため、養育費の請求・回収で裁判をお考えなら、弁護士に相談するのが得策といえます。
弁護士に相談すれば、養育費の請求の可否や適正な金額が分かりますし、利用すべき裁判手続きや利用する際のポイントについて具体的なアドバイスが得られます。
依頼した場合には、複雑な手続きはすべて弁護士に任せることができますし、調停には弁護士が同席して、交渉を有利に進めてもらうことも可能になります。
また、弁護士の力を借りれば、裁判をせずに(元)パートナーとの交渉によって養育費を獲得することも期待できます。
養育費の請求・回収で困ったら、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
元パートナーが養育費に関して協力的でない場合でも、裁判手続きを利用すれば強制的に養育費を獲得できます。
とはいえ、裁判手続きには時間や費用など、手間が大きいので、最終手段と考えておいた方がよいでしょう。
元パートナーとの任意の話し合いによって養育費を支払ってもらうのが理想的ですが、話し合いがスムーズに進まないときは、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。