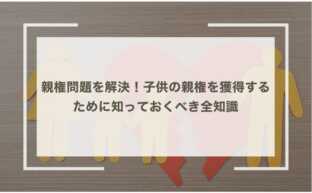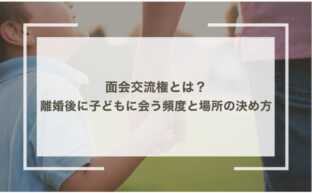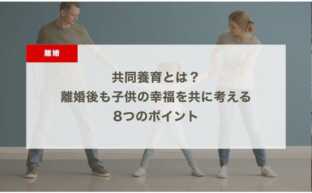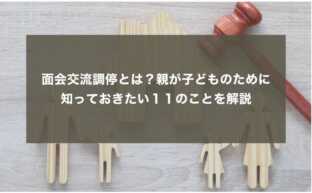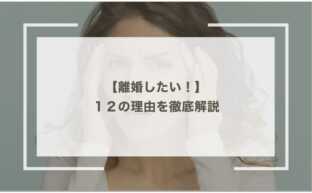離婚する時、子どもがいる家庭では親権を父親がもつのか、母親がもつのかで揉めるケースが多くありますが、一般的には父親が親権を得られる可能性は低いといわれています。
実際、家庭裁判所の手続きによって父親が親権を獲得するケースは全体のわずか1割に満たないと言われています。
しかし、数は少ないですが、父親が親権を持つ例も存在し、父親が親権を獲得するためのポイントも存在します。
この記事では、
- 親権者が父親になりにくい理由
- 父親が親権を獲得するためのポイント
などについて解説します。
目次
1、離婚時に父親が親権者になりにくい理由は?
父親の立場から見ると、離婚時の親権争いにおいて、父親というだけで圧倒的に不利とされてしまうことには納得いかないでしょう。
ここでは、なぜ親権争いで母親が優位とされているのか、日本における親権の考え方について詳しくご説明します。
(1)子育てでは母性が最重要視されるから
子どもが生まれたら、しつけや教育よりもまず、授乳やおむつ替えにはじまり、食事や衣服、風呂、寝かしつけなどが子育ての中心となります。
このような身の回りの世話は、一般的に父性よりも母性がよくなし得るところです。
このように、子育てにはまず父性よりも母性によるきめ細やかな世話が重要であるとする考え方のことを「母性優先の原則」といいます。
子どもの年齢が低ければ低いほど、母性優先の原則が強く働きます。
もっとも、子どもの年齢が上がるにつれて母性優先の原則は次第に後退していきます。
おおむね15歳程度になれば、身の回りのことは自分でできるようになることから、さほど母性優先の原則は考慮されなくなります。
(2)離婚前から母親が主に子育てをしていることが多いから
日本の社会では、まだまだ「父親が外で働き、母親が家庭で子育てをする」ことが当然であると考える風潮があります。
近年は共働きの夫婦も多いですが、それでも子育ては母親が主に担っている家庭が多いはずです。
家庭裁判所では、子どもが生まれてからずっと母親が主に世話をしてきたのであれば、特段の問題がない限り、離婚後も母親が子育てを継続するのが望ましいと考えられています。
このように、離婚後の子どもの養育環境について、できる限り現状から変更しない方がよいとする考え方のことを「継続性の原則」といいます。
なお、ここでいう「継続」については、これまでの子どもとのやりとりの継続(どちらが子育ての中心であったか)と、生活の継続(離婚後の生活環境をこれまでの連続で保てるか)の両面から判断されます。
もし、今まで母親よりもあなたが中心となって子育てをしていたのであれば、「継続」を重視する限り、離婚後も子どもはあなたのもとに置いておくべきという結論となります。
したがって、この原則を過度に恐れる必要はありません。
(3)離婚後も父親が子育ての時間を確保するのが難しいから
子育てにおいては、豊富な資産があるかどうかよりも、子どもに対する愛情があるかどうかが重要と考えられています。
外で働いて収入を得ることも愛情には違いありませんが、子どもが幼ければ幼いほど、家庭で常に一緒に過ごして愛情を注ぐということが重要となります。
ただし、時間があればいいというものではありません。
本当にその時間が子育てに有意義に使われ、愛情が育まれる時間なのか、これが重要です。
あなたが今後、現実に子どもの面倒をみることが可能な程度の時間を確保できるのであれば、親権争いにおいて有利になる可能性もあります。
(4)子どもが母親を求める傾向があるから
親権争いでは、子どもが父親と母親のどちらに懐いているかということも考慮されます。
一般的に母親の方が子どもと一緒に過ごす時間が長いことから、子どもは母親に懐くことが多いものです。
そのため、父親と母親のどちらかを選ばなければならないとしたら、母親を選ぶ子どもの方が多い傾向にあります。
もっとも、この傾向も子どもの年齢が上がるにつれて次第に後退していきます。
子どもが15歳以上になると本人の意思が尊重されますし、それ未満でも10歳を超えると子どもの意思がある程度尊重されるようになります。
おおむね12歳~13歳以上の子どもが父親を尊敬しているようであれば、離婚時に父親を選ぶ可能性も十分にあるでしょう。
(5)家庭裁判所では先例が重視されるから
親権の問題に限りませんが、裁判所が何かを判断する際には、基本的に先例を踏襲するものです。
これまで、家庭裁判所における親権争いにおける先例としては、母親が親権者に指定されたケースが圧倒的に多くなっています。
そのため、母親の子育てに重大な問題があるようなケースは別として、多少の問題があったとしても、先例に従って母親が親権者に指定されることが多いのが実情です。
2、離婚時に父親が親権を獲得するためのポイント
親権者を決める際に最も重要なことは、「子どもの福祉」、つまりどちらが子育てをした方が子どもの利益になるかということです。
以下で、父親が親権を獲得するためのポイントをご紹介します。
どうしても親権を獲得したい方は、以下の解説をご参考の上で、少しでも有利な状況を作るようにしましょう。
(1)積極的に子育てに関わっているか
父親が自力で「母性優先の原則」を突き崩すことは困難ですが、「継続性原則」については、父親にも勝ち目はあります。
そのためには、これまで子育てにどれくらい積極的に関わってきたかという点が重要となります。
子どもと一緒に過ごす時間は母親よりも短いとしても、日々子どもと真剣に向き合ってきたか、十分な愛情を注いできたかという点が問われます。
日中は仕事で子どもと過ごせないとしても、帰宅後や休日などには子どものことを第一に考えて子育てに関わることが必要でしょう。
(2)今後の養育環境は整っているか
父親の多くは外で働いているため、日中は子どもに関わることができません。
保育園や学童などを利用するのもよいですが、それでも父親一人では子育てに手が回らないこともあるでしょう。
子育ては、何も親権者が一人で行わなければならないものではありません。
夫の両親など身近な人の協力が得られるのであれば、積極的に協力を依頼しましょう。
このようにして離婚後の養育環境が整っている場合は、親権争いでプラスに働きます。
(3)母親の子育ての問題点を証明できるか
母親の子育てに問題点がある場合は、それを主張・立証することも重要となってきます。
例えば、以下のような事情があるケースでは、母親が子育てをすることは子どものためにならない可能性が高いといえます。
- 母親が不倫に夢中になっており、子育てが二の次となっている
- 母親が子どもを虐待している
- 母親がDV・モラハラ体質であり、子どもがなついていない
- 子どもの食事をほとんど作らない
- 子育てで必要な手続き(医療手続きや進学関係等)を適切にすることができない
- 夜に意味もなく家を空けている等々
これ以外にも母親の子育ての問題点として挙げられるのか、そういった不明点があれば是非弁護士にご相談ください。
(4)すでに子どもとの別居が長引いていないか
夫婦が不仲になると、離婚前に別居をすることも多いでしょう。
別居するケースでは、母親が子どもを連れて家を出ることが多いと思いますが、このような別居が長引いてしまうと、父親は親権争いで不利になってしまいます。
親権を獲得したいなら、なるべく同居したままで離婚協議をするか、別居するとしても子どもを手放さないことが重要となります。
もし、すでに母親・子どもと別居している場合は、早急に「面会交流権」を活用して子どもと交流しつつ、離婚協議も早めにまとめる方がよいでしょう。
(5)子どもが自分になついているか
前記でもご説明したように、子どもが父親になついているかどうかという点も重要です。
母親は子どもと一緒に過ごす時間が長いだけに、子どもを叱らなければならない機会も多いものです。
それに対して父親は、子どもの遊び相手や話し相手になって楽しい時間を中心として過ごすことも可能です。
ただし、子どもの気を引くために母親の悪口を吹き込むことは避けてください。
このような行為は親権者としてふさわしくありませんので、親権争いで不利になってしまいます。
父親としては、自由な時間にはできる限り子どもと楽しい時間を過ごすように心がけるとよいでしょう。
(6)親権をとれたら|面会交流を認める寛容性はあるか
元配偶者と子どもとの面会交流を認めない親よりは、積極的に面会交流権を認める親の方が親権を獲得できる可能性は高くなります。
この原則のことを「寛容性の原則」といいます。
離婚した元配偶者も子どもにとっては親です。
親権者でなくなった親との面会交流は、子どもが健全に成長していくために非常に重要な意味を持っています。
そのため、面会交流に積極的に応じる親の方が、親権者としてふさわしいと判断されるのです。
ちなみに、面会交流の頻度の相場は、月に1回、半日程度が相場です。
3、父親でも離婚時に親権を獲得したい!そんな場合の具体的な手続き
それでは、父親が親権を獲得するためには具体的にどうすればよいのでしょうか。
ここでは、離婚時に父親が親権を獲得するための具体的な手続きについて解説します。
(1)父親が育てた方が子のためになるという証拠を固める
離婚手続きに入る前に、まず証拠を確保しておくことが大切です。
これまで解説してきたことを参考に、「父親が育てた方が子のためになるという証拠」と「母親が育てることが子のためにならないという証拠」の両方をできる限り集めていきましょう。
妻側に離婚原因がある場合、離婚原因に関する証拠も必要ですが、それだけではなく、さらにその事実がどのように子どもにとってよくないのかを示す証拠が必要ということです。
例えば、妻が不倫しているケースなら、不倫したことの証拠に加えて、子どもの食事をあまり作らない、夜に外出することが多いなど、子育てに手を抜いていることがわかる証拠を集めましょう。
また、収入を示す資料(給与明細や源泉徴収票、確定申告書の控えなど)や、両親などの親族が子育てに協力する旨の誓約書も提出するとよいでしょう。
(2)母親と話し合う
証拠を確保したら、親権を決める手続きに入りますが、基本的には父母の協議によって決めることになります。
相手に証拠を突きつけて説得する一方で、慰謝料や財産分与などについては譲歩して、相手にもメリットのある離婚条件を提案して交渉するのも有効となります。
また、前記でご説明したように面会交流を積極的に認めることと、その他にも可能であれば「共同養育」(離婚後も元夫婦が協力して子どもを育てていくこと)を提案するのもよいでしょう。
実際に共同養育を実践している元夫婦も少なくありません。
母親としても、形式的な「親権」はなくても継続的に子どもと関わっていけるのであれば、説得に応じやすくなるでしょう。
共同養育について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
(3)離婚調停では家庭裁判所調査官の調査を求める
母親との話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員2名を介して当事者間の話し合いが進められます。
父親が親権を獲得するには、その方が子どもの成長にとって望ましいことをしっかりと主張し、その主張を裏づける証拠を提出することが重要となります。
さらに、調停では希望すれば家庭裁判所調査官による調査を求めることもできます。
家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所に持ち込まれるトラブルにおいて、法律ではなく心理学や社会学、社会福祉学、教育学といった専門知識に基づいて具体的な調査を行い、トラブルを解決するための調整を行う人のことです。
親権争いにおいては、父親・母親それぞれの家庭を訪問するなどして、どちらが親権者としてふさわしいのかについて調査を行い、一定の意見を家庭裁判所へ提出することになります。
(4)離婚裁判で徹底的に争う
離婚調停で話し合いがまとまらなければ、離婚裁判(訴訟)を起こすことになります。
裁判(訴訟)では、当事者双方が出し合った主張と証拠を裁判所が精査した上で、最終的に判決が言い渡されます。
判決には強制的に従わなければなりませんので、離婚裁判(訴訟)を起こすなら十分に準備をした上で、徹底的に争う必要があります。
なお、裁判(訴訟)の途中でも話し合いによって和解をすることができます。
実際のところ、民事裁判(訴訟)の約7割は和解で終了しています。
しかし、有利な和解案を引き出すためには、その前提として主張をしっかりと行い、十分な証拠を提出しておく必要があることにご注意ください。
4、離婚時に父親が親権を勝ち取った事例
ここまで読んで、父親が親権をとるのは「なかなかハードルが高そう…」と思っていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
たしかに割合的には少ないですが、実際に父親が親権を獲得している事例もあります。
そこで、ここでは父親が親権を獲得した実例をいくつかご紹介しますので、参考になさってください。
(1)ベリーベストにおける実例
当事務所の解決事例で、以下の通り父親が親権を勝ち取れたケースがありましたのでご紹介します。
①ご相談者様
30代男性
②ご相談時の状況
妻が不倫をしている。仕事は風俗。
③ご相談内容
親権を獲得して離婚をしたい。慰謝料請求したい。
④ベリーベストの対応とその結果
風俗で働いていることは口外しないことを条件に、公正証書により慰謝料を分割弁済、親権者は夫とすることになりました。
⑤解決のポイント
この事例では、妻が不倫をしていることと、風俗で働いていることについて明確な証拠を確保できたことが決め手となりました。
動かぬ証拠によって妻に非があることは明らかでしたので、交渉を有利に進めることができました。
このように、離婚時の親権の問題について交渉する際には、しっかり証拠を集めて立証していくことが重要になります。
(2)裁判例
次に、実際の裁判(調停、審判、訴訟)で父親に親権が認められた事例をご紹介します。
①母親が子どもを連れ去ったケース
〇父親の不在時に母親が無断で子どもを連れて家を出て別居に至ったケースで、母親は親権者としてふさわしくないと判断された。
このケースでは父親は親権を獲得できれば母親との面会交流にも積極的に応じる意向を示していたこともあり、父親が親権者に指定されました(千葉家庭裁判所松戸支部平成28年3月29日判決)。
②母親が一人で家を出て別居を開始したケース
〇母親が父親との生活を嫌って、子どもを置いて一人で家を出たケースで、父親が親権を勝ち取った。
このケースでは、父親は別居前から積極的に子育てをしており、別居後も円滑に子育てを続けていたことから、継続性の原則により父親に親権が認められたものと考えられます(大阪高裁平成30年8月2日決定)。
③子どもの希望で父親が親権を勝ち取ったケース
〇離婚時には母親が親権者となったものの、10歳の子どもが父親との生活を望んだことから、親権者が父親に変更された。子どもが15歳未満の場合でも、ある程度の年齢になると子ども自身の意思が重視されるため、母性優先の原則はさほど重要ではなくなってきます。
5、離婚時の親権争いでよくあるQ&A
ここでは、離婚時の親権争いについてよくある疑問について、まとめてお答えしていきます。
(1)母親が離婚原因を作った場合でも父親が不利になる?
離婚原因をどちらが作ったかという問題は、基本的に親権とは関係ありません。
したがって、たとえ母親が不貞行為をしたようなケースでも母親が親権を獲得するケースが多く、父親は不利なのが実情です。
もっとも、単に母親が離婚原因を作っただけではなく、母親の子供への虐待や不倫など、子育てに支障をきたしているような場合には、父親が親権を獲得することも可能になってきます。
そのような事情があるときは、その状況を記録して証拠化しておきましょう。
(2)母親が子どもを連れ去った場合でも母親が有利になる?
理屈上は、母親が無断で子どもを連れ去った場合には父親が親権争いで有利になるはずです。
しかしながら、たとえ無断で子どもを連れ去ったとしても、実際に罪に問われることはそれほどありません。
罪の点を度外視すれば、母性優先の原則と継続性の原則によって、子どもと一緒にいる母親の方が有利になってしまうケースが多いのが実情です。
(3)父親が親権を獲得するためには仕事を辞めなければならない?
親権を獲得するためには、実際に子どもの面倒をみるための時間を確保することが不可欠です。
しかし、必ずしも今の仕事を辞めなければならないわけではありません。
フルタイムの仕事をしていても、会社で働いている間は子どもを保育園に預けたり、両親などの親族に面倒をみてもらうという形でも、親権を獲得できないわけではないからです。
ただし、あくまでも父親自身が中心となって子どもの面倒をみることが親権獲得の条件であると考えるべきです。
子どもの世話を両親に任せきりにしていて、自分は毎日深夜まで帰宅できないという状況では、親権を獲得するのは難しいでしょう。
(4)父親が親権を取った場合、母親から養育費は取れる?
結論からいえば、基本的には養育費をとることができます。
養育費は、別居している親が子どもに対して支払うべきものなので、父親が親権を取った場合には母親から養育費を受け取ることができるのが原則です。
もっとも、養育費は、法律的には扶養義務と呼ばれるものの履行の一環です。
したがって母親に扶養する余裕がない場合には、請求できないこともあります。
実際に父親から母親に対して養育費を請求するケースが少ないのは、母親の経済力が父親に比べて乏しいことが多いからです。
6、離婚時に父親が親権を得られなかった場合には
やるべきことをやっても離婚時に親権を得られない場合はあります。
その場合は、以下の対処法によって子どもとの絆をつなぐように心がけましょう。
(1)面会交流を取り決める
面会交流とは、離婚後に非監護親が子どもと定期的に会って、親子の交流を図ることをいいます。
通常は月1回程度を目安に行われていますが、当事者の話し合いで回数は自由に決められますので、親権を譲る代わりに面会交流の回数を増やしてもらえるように話し合いましょう。
面会交流は子どもの健全な発育のためにも重要なものなので、この点を母親にしっかりと説明し、父親と子どもの交流の重要性を理解してもらうように努めましょう。
(2)将来の親権者変更を目指す
親権者の指定は、一度決められたら不変のものではなく、後に変更することも可能です。
離婚時に親権を獲得できなくても、諦めずに面会交流で子どもとの絆を育てながら養育環境を整えていけば、親権者変更を勝ち取れる可能性もあります。
短期間で親権者変更を勝ち取るのは容易ではありませんが、子どもがある程度の年齢になると母性優先の原則が考慮されなくなるので、変更される可能性も高まってきます。
親権者変更を勝ち取る方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
7、妻に子どもを連れ去られたときの対処法
あなたが離婚しても子どもと離れたくないと考えるのと同じように、母親も「絶対に子どもを手放したくない」と考えていることも多く、そんな母親が子どもを連れ去るケースも少なくありません。
そこで、子どもを取り戻すためには以下の法的手続きをとることになります。
(1)監護者の指定・子の引き渡し審判の申し立て
〇監護者指定:子どもの世話をする人の指定
〇子の引渡しの審判:監護者指定を受けることを前提として、連れ去られた子どもの引き渡しを命ずる家庭裁判所の審判手続き一時的なものではありますが、この手続きによって子どもをあなたの元に取り戻すことができれば、後の調停や審判、離婚訴訟でも「継続性の原則」によってあなたが親権を獲得できる可能性が高まります。
逆に、監護者の指定・子の引き渡し審判の申し立てをせずに事態を放置していると、「継続性の原則」によって母親がそのまま親権を獲得する可能性が高まってしまいます。
したがって、子どもを連れ去られたら、できる限り早急に、家庭裁判所へ監護者の指定・子の引き渡し審判を申し立てましょう。
(2)審判前の保全処分の申し立て
上記の審判を申し立てる際には、「審判前の保全処分」も併せて申し立てましょう。
保全処分とは、緊急の必要性がある場合に、申立人の権利を保全するために裁判所が下す暫定的な処分のことです。
監護者の指定・子の引き渡し審判でも結果が出るまでに一定の時間がかかりますが、保全処分が認められると暫定的に子どもをあなたの元に取り戻し、養育することが可能となります。
まとめ
親権争いの段階において、母親には「母性優先の原則」という強力な武器があるため、父親が親権を獲得するのは簡単ではありません。
父親がこれに対抗できる武器を持てるとすれば「継続性の原則」です。
親権者になるためには何より継続して監護しているという実績が重要ですから、日ごろからお子さんの育児には積極的に関与するように心がけましょう。
それでも父親は不利な場合が多いので、実際に親権を争う際には弁護士という味方をつけることをおすすめします。
まずは無料相談を利用して、具体的な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。