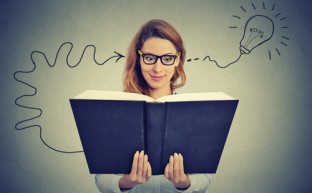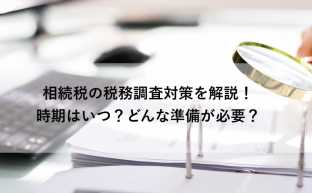相続には、時効があります。
夫や妻、父親や母親が亡くなった場合には、その遺産を受け継ぐ手続き、つまり「相続」が発生します。
相続が発生した場合、亡くなった方(被相続人)に遺産があれば、その遺産を貰い受けることができます。それでは、「そのうち、他の相続人と話しあって遺産を分けよう」と考えて、何もしないで放っておいても良いのでしょうか?
実はそんなことはありません。
相続が発生した場合でも、何もしないで一定の期間が過ぎてしまうと、自分の言いたいことが言えなくなる場合があります。
そのような事態とならないよう、今回は相続に関する時効について説明していきます。
ご参考になれば幸いです。
相続の手続きについて詳しく知りたい方は以下の記事に掲載されていますので是非ご覧ください。
目次
1、相続に時効が関係するのはどのような場合か
(1)「時効」とは?
まず、「時効」という言葉から解説していきます。
「時効」とは、一定の期間が経過すると、自分の主張が認められなくなること(自分の権利を失ってしまうこと)をいいます。
例えば、あなたが、お友達にお金を貸した場合、何もしないで10年間放っておくと、「金を返せ」とは言えなくなってしまいます。
これを、貸金の返還を請求する権利(貸金返還請求権)が、時効によって消滅したといいます。
(2)相続に関係する「時効」のいろいろ
相続が発生した場合、「時効」が問題となる場合は、大きく分けて
- 遺産分割を請求する権利
- 遺留分侵害額請求権
- 相続放棄
- 相続回復請求権
の場合があります。
ちょっと、難しい言葉もありますが、この意味は、これから各項目で順番に説明していきます。
2、遺産分割を請求する権利の場合
(1)遺産分割を請求する権利とは?
被相続人が遺言を残していなかった場合、残された相続人の間で、しなければいけないのが、遺産の分割の話し合いです。
これを「遺産分割協議」といいます。また、ある相続人が、他の相続人に、遺産分割を申し出る権利を「遺産分割を請求する権利」とか、「遺産分割請求権」といいます。
(2)遺産分割を請求する権利に時効はあるのか
遺産分割を請求する権利、遺産分割請求権自体に期間制限はありません。
したがいまして、遺産分割をしなかったとしても、遺産分割を請求する権利が時効によって消滅することはありません。
しかし、遺産分割をしないと、遺産は、いつまでも相続人全員の共有状態になり続けます。
不動産で言えば、相続人全員の共有物ということになります。
このような状態にしておくと、管理や売却する場合に、面倒なことになります。
また、相続人のうち一人が亡くなったとすると、その相続人について、さらに相続が発生することになります。その相続人に子供が何人もいる場合、その何人もの子供と協議をすることなります。
つまり、手続きや交渉がどんどん面倒になっていくわけです。
例えば、兄弟であれば、感情的なつながりもあり話合いがうまくいくこともありますが、兄弟の子供すなわちいとこ同士だと感情的な繋がりも小さい上、人数も増えてしまうため、話合いをまとめることが困難となってしまうことがあります。
したがいまして、遺産分割はすぐに請求しなくても時効によって消滅することはありありませんが、なるべく早めに請求するに越したことはありません。
3、遺留分侵害額請求権の場合
(1)遺留分侵害額請求権とは
「遺産分割」は、被相続人が遺言を残していなかった場合のお話でした。一方、ここでお話する「遺留分侵害額請求」とは、被相続人が遺言を残していた場合のお話です。
例えば、父親が、「遺産は長男にすべて相続させる」という遺言を残していたとしましょう。次男、三男は、一切、遺産を取得することはできないのでしょうか?実は、そんなことはありません。相続人には、最低限の遺産を取得できる権利が保証されています。
この相続人に保証された最低限の遺産取得割合を「遺留分」(いりゅうぶん)といいます。
そして、遺言を残されなかった相続人(この例ですと、次男と三男)が、遺言を残された相続人(この例ですと、長男)に、「遺留分をよこせ」と請求することを、遺留分の侵害額請求といいます。
(2)遺留分侵害額請求権の時効
この遺留分侵害額請求には、期間制限があります。
相続開始と侵害額の請求をすることができる遺言があることを知った時から1年間経過すると、遺留分の侵害額請求ができなくなってしまいます。
つまり、父親の「遺産は長男にすべて相続させる」という遺言が発見されたときから、1年以内に、長男に対して「遺留分をよこせ」と請求しなければなりません。
被相続人が死亡した場合、葬儀などの法要が続き、1年というのは、すぐに経ってしまうものです。
遺言を発見した場合には、すぐに遺留分の侵害額請求をすべきです。
また、遺留分の侵害額請求権は、相続開始時から10年を経過した場合にも、当人が知っているかどうかに関わらず、時効によって消滅してしまいます。
(3)遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することを回避する方法は
遺留分侵害額請求権は、相続開始と侵害額請求をすべき財産の移転を知った時から1年、相続開始時から10年、経過すると時効によって消滅してしまいます。
これを回避するためには、遺留分を有する権利者(さきほどの例だと、次男と三男)が、遺留分を侵害した者(さきほどの例だと長男)に対して、「遺留分侵害額を請求する」旨の通知を送付する必要があります。
この通知は、後日の紛争防止のため特に遺留分侵害額請求をした日時を明確にするために、配達証明付きの内容証明郵便などで送付しておくことが必須となります。
4、相続放棄の場合
(1)相続放棄が問題となる場面
いままでは、被相続人が遺産を残した場合のお話をしてきました。
しかしながら、被相続人が残すのは遺産だけではありません。
被相続人がマイナスの資産つまり借金を残してしまうことも多々あります。
被相続人が借金を残していた場合、相続人がその借金を引き続き、返済していかなければなりません。
ここで、借金の金額が微々たるもので、返済できるくらいのものであれば、それほど問題はないのかもしれません。
しかし、借金の金額が数千万にのぼり、一方、さしたる遺産も残していない場合、返済することができない場合もありえるでしょう。
このような場合、「相続の放棄」という手続をとることができます。
相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産(遺産)もマイナスの財産(借金)も一切引き継がないこととする手続きです。
(2)相続放棄と時効
この相続の放棄がとれる期間は、相続が開始したのを知った時から3カ月間となります。
3カ月という期間はあっという間なので、被相続人に多額の借金があることが分かっている場合には、すぐに相続放棄の手続きをとる必要があるといえます。
特に、相続順位第1位の相続人(夫、妻及び子)が相続放棄した場合、相続順位第2位の相続人(両親等)は注意が必要です。この点については、相続放棄の項目を参照して頂ければと思います。
(3)相続放棄をするには
この相続の放棄は、家庭裁判所で、「相続の放棄をする」ということを申し出る必要があります。
5、相続回復請求権の場合
(1)相続回復請求権とは
相続人ではない者が相続をしてしまい、本来の相続人が遺産を相続できなかった場合、本来の相続人は、相続人でない者に対し、「遺産を返せ」と言うことが当然出来ます。
これを「相続回復請求権」といいます。
このような事例はあまりないかもしれないですが、相続人でない者が相続に関わっていることが疑われる場合には、知っておきましょう。
(2)相続回復請求権と時効
この「相続回復請求権」にも時効があります。
自分の相続権が侵害されていることを知った時から5年間、相続開始から20年間です。
(3)相続回復請求権の消滅時効を回避するために
この場合も、「遺留分減殺請求」と同じですが、相続権を侵害されている者が、相続権を侵害している者に、通知をする必要があります。
配達証明付き内容証明郵便で発送すべきなのも同様です。
6、税金の申告について
(1)税金の申告期限について
「時効」とは少し話が違いますが、相続に関係して、知っておかなければならないもう一つの大切な事項が、税金の申告期限です。
この期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税を支払わなければならなくなるからです。
(2)相続税
相続に関係する最もポピュラーな税金が、「相続税」です。相続した遺産に応じて申告すべき税金です。
相続人が2人の場合、相続財産が4200万円以上であれば、相続税の申告と納付が必要になります。
この相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から起算して、10カ月です。
(3)所得税
また、相続財産に収益不動産がある場合など、被相続人が収益を得ていた場合、被相続人の所得税を、相続人が申告しなければなりません。
これを所得税の準確定申告といいます。
所得税の確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から起算して4カ月です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
相続にまつわる時効についてお話してまいりました。
この記事を参考に法律をしっかり抑えてご判断いただければと思います。