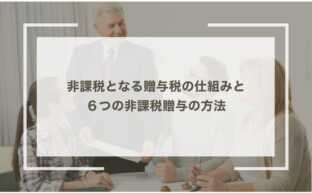被相続人を介護してきたお嫁さんも被相続人の配偶者や子どもと同じように相続することができるのでしょうか。
実は、2019年の法改正により、これまでよりも相続に際して、お嫁さんが金銭を受け取ることができる可能性が高まりました。
ここでは被相続人の介護をしてきたお嫁さんに向けて
- 相続に際して金銭の支払いを請求できる新しい制度の詳細な内容
- 介護をしてきた方が金銭の支払いを請求する方法
について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
新しい制度であなたの苦労も報われるかもしれません。
お嫁さんの相続に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、介護をしてきた相続人が他の相続人より「多く」相続する方法

まず、介護などで被相続人の生活に貢献してきた相続人が、他の相続人よりも多く相続する方法についてお話します。
お嫁さんは「相続人」ではないので次の項目でご説明しますが、まずはこの項目をご覧ください。
複数の相続人の中で、「自分だけが親の介護をしてきた」という場合もあるでしょう。
そのような場合、介護をしてきた相続人は、他の相続人と平等に相続することに納得がいかないこともあります。
ここでは、そのような介護をしてきた「相続人」が、他の相続人よりも「多く」相続する方法について、2つのケースに分けてご説明します。
(1)被相続人(亡くなった方)が望む場合
被相続人が介護してくれた相続人により多くの遺産を残したいと望んでいた場合には、いくつかの方法が考えられます。
①生前贈与・死因贈与
生前贈与や死因贈与を利用することで、一部の相続人が他の相続人よりも多く遺産を譲り受けることが可能です。
生前贈与とは、遺贈者が生きているうちに財産を贈与する契約で、死因贈与とは、死んだ場合に贈与するという契約です。
ただし、額には注意が必要です。相続人に対する生前贈与や死因贈与は「特別受益」にあたるからです。
特別受益を得た相続人がいる場合、相続財産に特別受益の金額を持ち戻したものを「みなし相続財産」としたうえで、各相続人の具体的相続分を算出します。
特別受益を得た相続人は算出された具体的相続分から特別受益の金額を差し引いた額のみを相続することになります。
仮に、算出された具体的相続分よりも特別受益の金額の方が大きいという場合には、上回った部分について他の相続人に支払う必要はありません。
したがって、最終的に得になるかなるかどうかは特別受益の金額によって変わってきます。生前贈与や死因贈与の際にはこの点に注意が必要です。
もっとも「持ち戻し免除の意思表示」をすることで、持ち戻しの計算をしないようにすることは可能ですから、その点に注意したうえで遺言書を作成しておくことも重要です。
また、税金にも注意する必要があります。
生前贈与には贈与税、死因贈与には相続税がかかります。
生前贈与について贈与税がかからない方法についてはこちらの記事をご覧ください。
さらに、生前贈与や死因贈与が他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求をされる可能性がありますので注意が必要です。
②遺言書を利用する
遺言書を作成して、相続分や相続する財産を指定するか、遺贈を行う方法があります。
相続分を法定相続分よりも大きく指定したり、相続する財産として法定相続分に相当する財産よりも多い財産を指定することによって、特定の相続人により多くの財産を相続させることが可能になります。
また、遺贈とは、遺言書を利用して特定の者に財産を譲る方法です。
死因贈与と違うのは、死因贈与は契約なので贈与を受ける者との合意が必要ですが、遺贈は贈与する者の一方的意思で成立する点です。
遺贈を受ける者(受遺者)の意に反することもあるので、受贈者はこれを放棄できるのもメリットといえるでしょう。
特別受益と遺留分についての注意点は、生前贈与・死因贈与と同様です。
遺贈特有のデメリットとしては、遺言書に不備があれば遺贈が無効になってしまう可能性があることです。
心を込めた遺言書であればあるほど、無効になってしまうのは悲しいことです。
遺贈の場合は遺言書のルールをきちんと把握することが大切です。
また遺贈にも相続税がかかります。
遺贈に関する詳細は下記の記事をご覧ください。
③贈与と遺贈-選ぶポイント
では、生前・死因贈与と遺贈では、どの方法を選ぶべきか。
選ぶポイントは「税金」です。
生前贈与は贈与税、死因贈与と遺贈は相続税がかかります。
贈与税、相続税にはそれぞれ非課税の制度があります。
それらをうまく利用するように選ぶべきです。
また、不動産については別途税金がかかり、その額が異なります。
生前贈与・死因贈与では不動産取得税が4%、登録免許税が2%かかります。
法定相続人に対する遺贈では不動産取得税はかからず、登録免許税も0.4%とかなり抑えられます。
税の計算は複雑ですので、税理士にご相談されることをお勧めします。
(2)相続人が望む場合(被相続人による対策はしていない場合)
相続人が被相続人に多くの貢献をして財産の維持や増加に寄与したこと(寄与分)を主張することで、他の相続人よりも多くの相続財産を得られる場合があります。
①遺産分割協議で「寄与分」を主張する
もしも生前に介護を行ったことなどによって被相続人の財産の維持や増加に貢献したと主張したいなら、「寄与分」を主張しましょう。
そのためには手順があります。
まずは相続人たちと遺産分割協議を行う際に、寄与分を主張し、寄与分を踏まえた遺産分割をするよう求めます。
そこで話がまとまれば、寄与分を前提としてまとまった内容の遺産分割協議書を作成して終了です。
それをもとに不動産の相続登記を行うなど相続財産の名義変更等を行います。
遺産分割協議は話合いの手続きのため、相続人全員が納得するのであれば内容はどのようなものでも問題ありません。
法的には寄与分の主張ではありませんが、相続人の1人が自分の妻が介護をしたとして法定相続分よりも多い相続を主張することも可能ですし、他の相続人が同意するのであれば、その内容で合意することも可能です。
②寄与分を定める処分調停
相続人同士の話し合いでは合意できなかった場合には、寄与分を定める処分調停を行います。
家庭裁判所に申立てを行い、調停委員を介して寄与分について話し合い、合意を目指します。
調停が成立すると、寄与分が決定しますので、それをもとに遺産分割協議や遺産分割調停を進めていきます。
③寄与分審判
調停も不成立なら、寄与分審判に移行します。審判では、当事者が証拠を提出して主張を行い、裁判官が資料などを精査して判断します。
審判では裁判官が判断するため、証拠がなければ寄与分が認められない可能性は高くなります。
寄与分を獲得するためには下記記事も参考にしてください。
2、介護をしてきたお嫁さんなど(≠相続人)が遺産を譲り受ける方法

では次に、介護をしてきたお嫁さんなど、相続人以外で介護や家業の手伝いによって被相続人の財産の維持や増加に貢献してきた方が相続の際に財産を取得する方法をご紹介します。
(1)被相続人が望む場合
被相続人が相続人ではないお嫁さんなどに遺産を渡したいと考えている場合の方法をご紹介します。
①生前贈与・死因贈与
相続人の場合と同様、生前贈与や死因贈与によって遺産(となる予定の財産)を渡す方法があります。
基本的に前述の説明の通りですが、「特別受益」の点だけが異なります。
相続人でない限り、「特別受益」を心配する必要はありません。
もっとも、遺留分侵害額請求の対象にはなりますので、この点はご注意ください。
また、生前贈与で贈与税が発生することはもちろんのこと、相続人ではありませんが、死因贈与の場合は相続税がかかるうえ、税額が2割加算されることにもご注意ください。
さらに、不動産の場合、不動産取得税4%、登録免許税2%がかかります。
②養子縁組する
被相続人と養子縁組をすることで法定相続人になれます。
これによって法定相続人になり、遺産分割協議にも相続人として参加でき、法定相続分を主張することができます。
そのためには被相続人は生前に財産を渡したい人と養子縁組の意思を確認し、手続きしなければいけません。
③遺贈-遺言書を利用する
相続人の場合と同様、遺贈の方法もあります。
遺留分についてはやはり注意が必要です。
さらに、相続人ではありませんが、遺贈を受けると相続税がかかりますのでご注意ください。
「1」で、法定相続人への遺贈の場合、不動産の不動産所得税がかからないとご説明しましたが、法定相続人でない人への特定遺贈の場合は不動産取得税4%(原則)が発生します(包括遺贈であればかかりません)。
ご注意ください。
登録免許税は2%です。
④生命保険の受取人にする
生命保険の受取人に指定するのも一つの方法です。
生命保険金は、遺留分侵害額請求の対象とならないことが特徴です。
そのため、遺産争いと無関係に財産を遺すことができる手段といえるでしょう。
ただ、デメリットが2点あります。
1つは、生命保険は生前に継続してそれなりの保険料の支払いが必要となることです。
もう1つは、生命保険金を受け取った場合にも相続税がかかることです。
さらに、法定相続人が受取人の場合には非課税枠がありますが、相続人以外の者が受け取る場合には非課税枠がなく、全額が課税対象となります。
相続方法 | メリット | デメリット |
生前贈与 | ç① 生きているうちに確実に財産を渡せる ② 方法次第で相続税対策になる | ① 贈与税がかかる →非課税制度の検討を ② 遺留分侵害額請求の対象となる →贈与額につき遺留分を考慮した額の算出が必要 ③ 贈与対象物が不動産の場合、不動産取得税と登録免許税がかかる |
死因贈与 | ① 現在使用しているもので生前贈与が難しいものを特定の人に渡すことができる(例:自宅の贈与など) ② 相手の同意を得た上で渡すことができる(↔︎遺贈) ③ 生前に○○してくれたら死亡と同時に贈与する、という形で、贈与に条件をつけることができる(負担付贈与契約) | ① 受贈者は放棄ができない(↔︎遺贈) ② (契約書がなくても契約は成立しているものの)契約書がなければ遺産争族に巻き込まれることも ③ 相続税がかかる → 非課税制度の検討を ④ 遺留分侵害額請求の対象となる →贈与額につき遺留分を考慮した額の算出が必要 ⑤ 贈与対象物が不動産の場合、不動産取得税と登録免許税がかかる |
養子縁組 | ① 法的な相続人にできる ② 親子の絆を結べる | ① 一定の縁組手続きが必要 ② 相続人が増えるため、既存の相続人からの反発の可能性がある ③ 相続税がかかる → 非課税制度の検討を |
遺贈(遺言書) | ① 生前、内容を秘密にできる ② 受遺者は放棄ができる | ① 遺言書にミスがあれば無効になる → 専門家の指導の元ミスのない遺言書を ② 財産や状況に応じて遺言書を定期的に見直す必要がある ③ 相続税がかかる → 非課税制度の検討を ④ 遺贈対象物が不動産の場合、不動産取得税が4%(包括遺贈ではかからない)、登録免許税が2%かかる ⑤ 遺留分侵害額請求の対象となる →遺贈額につき遺留分を考慮した額の算出が必要 |
生命保険の受取人 | 遺留分侵害額請求の対象にならない(↔︎生前贈与・死因贈与、遺贈) | ① 生前、保険料の支払いが必要 ② 譲り渡す対象が現金に限定される ③ 相続税がかかる → 非課税制度の検討を |
(2)お嫁さんなどの親族が望む場合(被相続人が対策をしていない場合)
お嫁さんなどの相続人ではない親族が遺産を獲得することを望む場合にも、いくつか方法があります。
見ていきましょう。
①相続人である夫(被相続人の実子)が健在の場合
相続人の夫が健在の場合には、まずは相続人の夫を介して遺産を取得することを検討します。
お嫁さん(被相続人の実子の妻)自身の相続ではありませんが、夫が相続すればそれでよいと考える方も多いのではないでしょうか。
そのため、夫が相続人として参加する遺産分割協議の中で、介護など特別の貢献をしてきたことを考慮したうえで夫の相続分を増やすよう主張するということが考えられます。
お嫁さんを夫の履行補助者であると位置づけて、お嫁さんの介護等による貢献を相続人である夫の貢献であると評価して、夫の寄与分を認めるという例もあります。
②相続人となるはずだった夫が既に亡くなっている場合
被相続人の子どもとして相続人となるはずだった夫が既に亡くなっている場合にはどうなるでしょうか。
相続人となるはずだった者が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、相続人となるはずだった者の子どもや孫が「代襲相続」します(民法887条)。
したがって、夫との間に子どもがいる場合には、その子どもが代襲相続により相続人になりますので、子どもは被相続人の遺産を相続できます。
お嫁さんは献身的に介護していたとしても、代襲相続をすることはありませんから、この場合も相続人にはなりません。
③特別寄与料制度の創設
以上のように、嫁は献身的に介護をしてきたという場合でも相続人ではないために、遺言がない限り、遺産を相続することができませんし、相続に際して金銭を請求することもできませんでした。
しかし、相続人が介護等を行った場合には寄与分による調整がある一方で、相続人の妻が介護等を行った場合には何らの手当てがないことがかねてより問題視されており、民法の改正により2019年7月からは相続人以外の親族も特別寄与者として特別寄与料を相続人に請求することができるようになりました。
3、特別寄与制度について解説

では、2019年7月に施行された「特別寄与制度」について詳しく解説していきます。
(1)特別寄与者になれる親族とは
被相続人に介護等何らかの寄与をして被相続人の財産を維持・増加したとして特別寄与料を請求できるとする者を「特別寄与者」といいますが、特別寄与者は「親族」でなければなれません。
近隣の者やヘルパーなど、親族以外の者が寄与したとしても、この制度の対象ではありません。ご注意ください。
「特別寄与者」になれる親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族の中で相続人ではない人のことです。
具体例をあげると、被相続人の子どもの配偶者(お嫁さん)などがこれに当たります。
介護をしてきたお嫁さんはまさにこの特別寄与者に該当しうるというわけです。
(2)相続人に対し金銭的な請求(特別寄与料の請求)を行う
法改正では、お嫁さんが相続人になるとされたわけではありません。
相続人に対して特別寄与料の請求ができるようになったということにとどまります。
特別寄与料を得るためには、相続人に対して請求を行う必要があります。
(3)特別寄与料の算出方法
寄与の時期や期間、方法、程度や遺産の額などの一切の事情を考慮して特別寄与料の額は決まります。
そのため、具体的にいくらもらえるという額はそのケースによって異なります。
特別寄与料は、それぞれの相続人に法定相続分に応じて請求することができます。
(4)施行日
2019年7月1日に施行になりました。2019年7月1日以降に開始した相続にのみ適用されます。
4、遺留分侵害額請求に注意

生前贈与や死因贈与、遺贈などによって多くの遺産を受け取ろうとすると、法定相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあります。
遺留分とは、相続の際に兄弟姉妹以外の相続人に最低限取得できる割合のことです。
生前贈与や死因贈与、遺贈によってこれを侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
生前贈与や死因贈与、遺贈を行う場合や遺言書を作成する場合には、相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
もっとも、遺留分侵害額請求は相続人から請求があって初めて問題となるものです。
遺留分を侵害する内容の遺言書は無効となるわけではなく、遺贈等を受けた者が相続人から遺留分侵害額請求がなされた場合にはその分の金銭を支払わなければならないリスクを負うということです。
遺留分についての詳細は下記記事をご覧ください。
5、相続でお困りの際は弁護士へご相談ください

相続は、家族の数だけ形があり、一般化することが難しい問題です。
個別具体的なお悩みは、お早めに弁護士にご相談ください。
ご希望に沿った方法の提案を受けることができるはずです。
まとめ
介護をしてきたにもかかわらずに相続人になれない親族にとって、特別寄与料の新設は明るい希望です。
被相続人となる方が遺言書を作成してくれるのであればその方が良いですが、それができなくても特別寄与料を請求する余地があります。
特別寄与料の請求には期限がありますので、請求をお考えの場合には早急に動きましょう。
お困りのことがありましたら、お早めに弁護士にご相談ください。
あなたの苦労が報われることを願います。