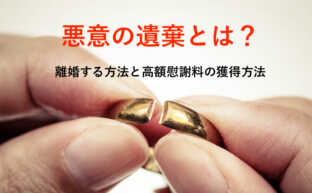この記事では、失踪した配偶者との離婚手続きに関する情報を提供し、手続きの方法、留意点、および失踪事案への対応方法に焦点を当てています。
失踪によって生じる家族内の問題を考慮し、関係を整理し前向きに進むための支援を目的としています。
「3年以上の生死不明」について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
1、旦那・嫁の失踪を理由に離婚する方法
一般的な離婚は、まず離婚の意思があることを相手に伝え、夫婦間で話し合いを行うことが最初のステップになりますが、配偶者が失踪してしまっている場合、話し合いでの離婚成立を目指すことは状況的に不可能です。
そのため、配偶者が失踪している場合の離婚方法は、離婚訴訟を提起することになります。
2、失踪離婚で離婚訴訟がうまくいく条件
離婚訴訟で離婚できるケースは決まっています。民法第770条第1項各号に記載された、法定離婚事由があるケースです。
いずれかのケースに当てはまっていれば、配偶者が失踪していて不在でも、離婚訴訟で離婚することが可能です。自分のケースがどれに当てはまるか不安な場合は、弁護士の無料相談で確認してみてください。
第二款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
引用:民法
(1)3年以上の生死不明
配偶者の失踪で離婚する場合、民法770条第1項第3号に当てはまることがあります。
民法770条第1項第3号とは、「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」という項目です。
これは配偶者が失踪し、失踪から3年以上生死がわからないケースが該当します。
そのため、たとえ居場所が分からなくてもメールや電話で連絡がつく状態であったり、自分以外の誰かが3年以内に配偶者を目撃している場合は、「生死不明」ではないためこの項目には当てはまりません。
(2)悪意の遺棄
生死不明でない場合や3年以上も経過していないというケースでは、同条同項第2号に定められている「悪意の遺棄」への該当を考えましょう。
悪意の遺棄とは、生活費や養育費を一切渡さない・健康なのに働かない・理由もなく同居を拒否するなどのケースであり、簡単に言えば「配偶者を見捨てる」ような行為です。
詳しくはこちらの記事でもご紹介していますので、ぜひあわせて参考にしてください。
(3)婚姻を継続し難い重大な事由
生活費を送ってくるなど配偶者としての義務を果たそうとしているケースでは、悪意の遺棄が認められない可能性もあります。
この場合は、同条同項第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」で離婚できる可能性は残されています。
メールや電話で連絡は取れているものの本人に帰宅の意思がない場合など、すでに婚姻関係が破綻していて今後修復できる可能性も低いと判断されれば、裁判で離婚を認めてもらうことができるでしょう。
3、失踪から7年以上が経過していた場合は別の方法もある
失踪の期間が7年間以上に及んでいる場合は、別の手段で手続きを行うこともできます。
(1)失踪宣告制度の利用
配偶者の生死が7年以上不明なときに利用できるのが「失踪宣告」という制度で、家庭裁判所に申し立てを行い、申告が認められれば配偶者は「死亡」と同じ扱いになります。
地震や津波など大きな天災が起こったときには、例外的に生死不明から1年で失踪宣告を行うことができるケースもあり、いずれの場合も配偶者は法律上死亡したとみなされるため、遺産の相続や保険金の受け取りを行えるようになるところがメリットのひとつです。
なお、死亡とみなしたところで「離婚」ではありません(もちろん、再婚は可能になります)。
籍を抜きたいなどの理由があり「離婚」をしたい場合は、また別の手続きが必要となります。
(2)失踪宣告と3年以上の生死不明の違い
失踪宣告と3年以上の生死不明では「配偶者を法律上どのように扱うか」が最も大きく異なり、失踪宣告では死亡と同じ扱いになりますが、3年以上の生死不明では配偶者との離婚が成立するだけで生死は依然として不明のままです。
また、手続き後しばらく経ってから本人が帰宅した場合など、生存が確認できたときの対応にも以下のような違いがあります。
- 失踪宣告:取消の手続きが行われ、失踪宣告により得た財産や保険金は返還が求められる
- 3年以上の生死不明:生存が判明しても離婚の成立を覆すことはできない
失踪宣告では財産の相続・保険金の受け取りなど金銭的なメリットを得られるところが大きなポイントでしたが、配偶者がまだ生きていることが分かれば、自動的にその権利も失われます。
得た利益の返還は今手元に残っている分だけで良いとされており、すでに使ってしまった分についてまで問われることはありませんが、失踪宣告は状況に応じて取り消される可能性があることも覚えておきましょう。
一方、3年以上の生死不明で成立した離婚は、たとえ帰宅した配偶者が「自分は帰ってきたのだから離婚は無効だ!」と訴えたとしても、その判決が覆ることはありません。
過去を整理してきっちりけじめをつけたいという場合はこちらを選んだほうが心穏やかに過ごせるケースもあるため、他の家族の希望も聞きながらよく考えてみましょう。
まとめ
夫・妻が突然失踪してしまい一時は途方に暮れたものの、時間が経つにつれて「このままでは良くない」「自分のためにも残された家族のためにも、結婚生活に区切りをつけて新しい未来に歩き出したい」と思い、離婚を考えるようになるケースは多いでしょう。
配偶者が失踪していて協議離婚が難しい場合も、今回ご紹介した条件を満たしていれば、裁判での離婚や失踪宣告を行うことが可能です。
特に失踪宣告では配偶者の遺産を相続できるようになるところも大きなポイントなので、ぜひみなさんも自分の状況と照らし合わせながら、どの道を選ぶのがベストなのかじっくり検討してみてください。