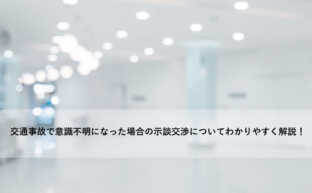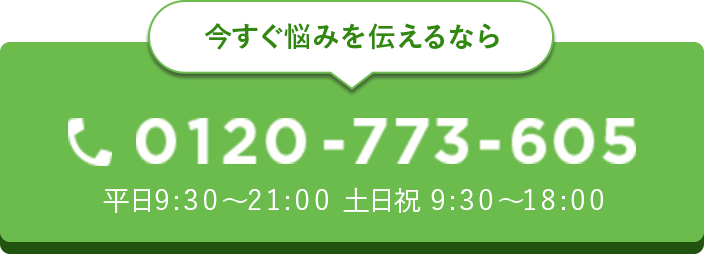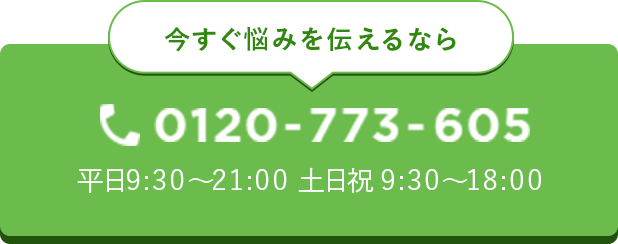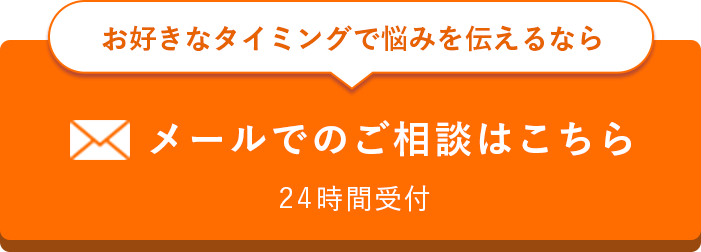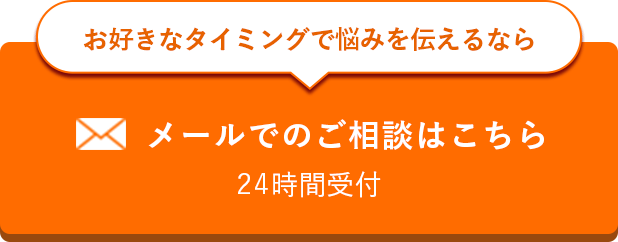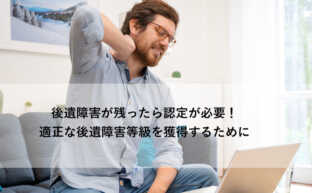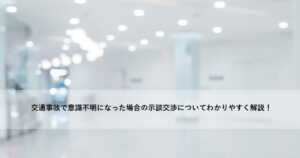
バイクや歩行者が被害者となった交通事故では、頭部に大きなダメージを受け意識不明の重体となることがあります。この場合、脳の機能に障害が生じるなどの重篤な後遺障害が残ることがあるので注意が必要です。
当然、このようなケースでは、加害者から受け取ることのできる損害賠償額も相当な額になるはずですが、事故後の対応を間違えてしまうと、被害に見合わない不当に低い賠償金額で示談させられてしまう可能性があります。
そこで、今回は、
- 交通事故の被害者が意識不明の重体になってしまった場合において特に注意すべきポイント
をまとめてみました。この記事が大事故の被害者の方や、そのご家族の方々のご参考になれば幸いです。
交通事故で負った怪我の治療に関しては以下の関連記事もご覧ください。
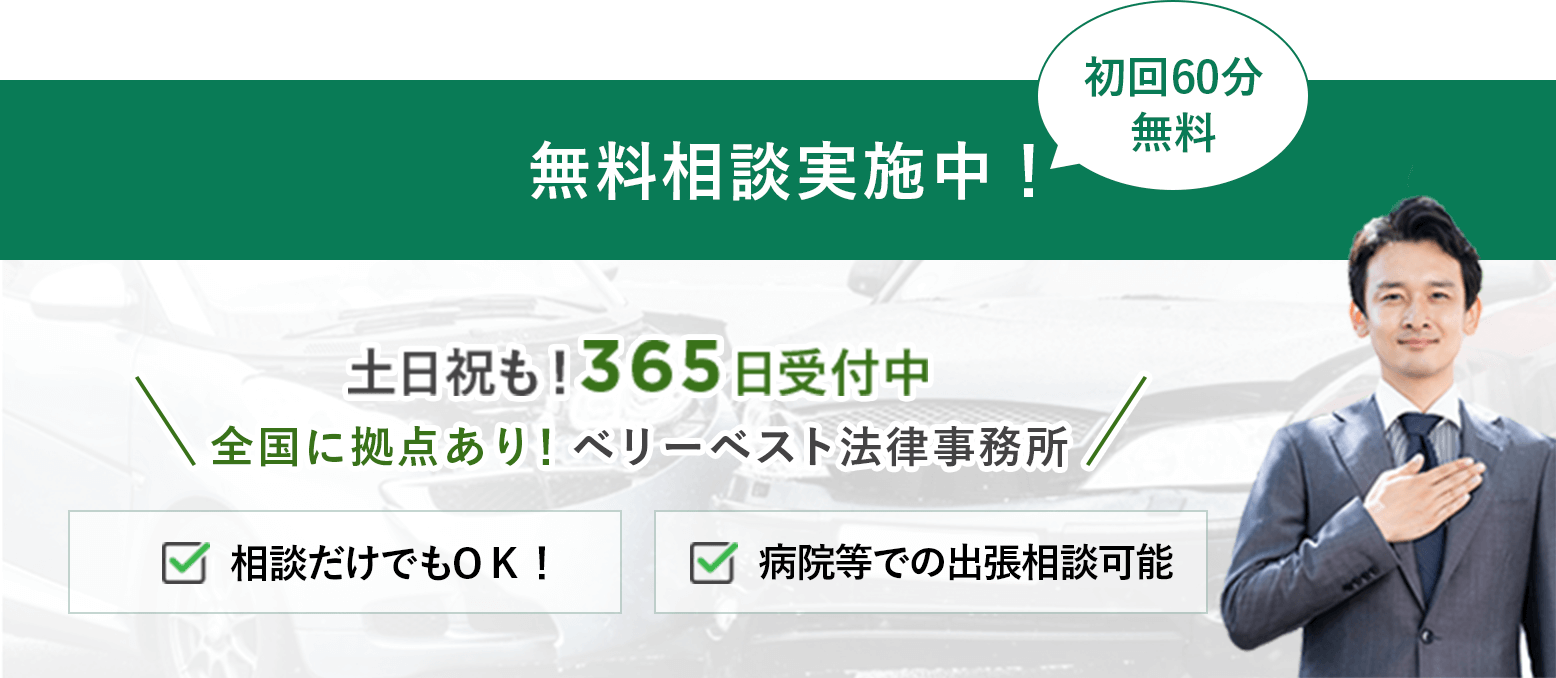

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、交通事故で意識不明の重体になってしまった場合の損害賠償の内訳

交通事故で意識不明の重体となってしまった場合、下記のような損害項目について、加害者側の保険会社に賠償を請求できる可能性があります。
- 治療に伴う医療費(診療費、投薬費、装具代など)
- 通院の交通費
- 入院した場合の入院費用(ベッド代、入院雑費など)
- 入通院に介助者の付き添いが必要な場合における付添費
- 将来的な介護が必要になる場合の将来介護費
- 被害者がケガによって、そのままの状態では生活等が困難となった場合における、自宅や自動車等の改造費
- 被害者が入通院等のせいで仕事を休む必要がある場合の休業損害(休業日数分の減収額や、休業によって減額した賞与額等)
- 入通院の手間暇や苦痛等の精神的損害に対する慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害が残ったことによる精神的損害に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)
- 後遺障害によって仕事に支障が生じ減収が生じ得る場合の逸失利益
なお、歩行中ではなく、バイクに乗っているときに事故に遭い、物的損害が生じたのであれば、その損害の賠償を請求することもできます。
交通事故やその後の手術等の際に着ていた服が損傷したり、持っていた携帯電話等が壊れてしまったりすれば、それらの物的損害について賠償を請求することもできます。
その他、交通事故と因果関係がある出費については加害者側の保険会社へ請求し得ますので、迷うことがあれば弁護士に相談してみてもいいでしょう。
2、意識不明となる交通事故において、残る可能性のある後遺障害

(1)後遺障害の種類
意識不明が生じる場合、次のような傷病名がついている可能性があります。
- 頭蓋内血腫
- 硬膜外血腫
- 硬膜下血腫
- くも膜下血腫
- 脳挫傷
- 気脳症
- 脳内血腫
- びまん性軸索損傷
そして、これらの原因疾患によって、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)や外傷性てんかん、高次脳機能障害、身体機能障害(マヒなど)などの後遺障害が残ってしまう可能性があります。
なお、意識障害が6時間以上継続するケースでは、永続的な高次脳機能障害が残ることが多いとされています。
重度の高次脳機能障害等が残った場合、被害者は不自由な生活を強いられる可能性が高く、かなり大きな損害が発生するといえ、その分加害者に対して請求できる賠償額も高額になり得ます。
(2)後遺障害が残ってしまった場合の損害賠償額
後遺障害が残ってしまったという場合には、自賠責損害調査事務所という第三者機関に対して必要書類を提出し、後遺障害の存在を認定してもらうことで、認定される後遺障害等級に応じた損害賠償(後遺障害慰謝料・逸失利益の支払い)を加害者側の保険会社に対して請求することができます。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、第1級に近づくにつれて、より重い症状ということとなり、一般的には請求し得る賠償金の額も増えていくこととなります。
意識不明が原因で生じる主な後遺障害の場合には、それぞれの障害の具体的な程度によって、以下の後遺障害等級を受けられる可能性があります。
後遺障害等級 | 自賠責基準による慰謝料上限額※ |
別表第1第1級1号(常時介護) | 1650万円 |
別表第1第2級1号(随時介護) | 1203万円 |
別表第2第3級3号 | 861万円 |
別表第2第5級2号 | 618万円 |
別表第2第7級4号 | 419万円 |
別表第2第9級10号 | 249万円 |
別表第2第12級13号 | 94万円 |
別表第2第14級9号 | 32万円 |
※令和2年4月1日以降に生じた交通事故の場合の金額
遷延性意識障害になってしまった場合は第1級の後遺障害が認定される可能性が高いです。
また、高次脳機能障害や外傷性てんかんが残ってしまった場合、神経系統の機能又は精神に残る障害の程度や、介護を要する程度、労務に服することのできる程度等によって、第1級から第9級までの後遺障害が認定される可能性があります。
他方で、高次脳機能障害等が残存するに至らない障害であったとしても脳挫傷等が生じていることが画像上確認できるのであれば、第12級の後遺障害が認定される可能性があります。
また、脳挫傷痕等の画像上の所見がなくとも、神経症状が残存しておりその原因の医学的な裏付けがある場合であれば、第14級の後遺障害に該当すると判断される可能性があります。
なお、慰謝料は治療費のように実際にかかった費用を算定すればいいわけではなく、金銭的評価が容易ではないため、実務上では、様々な基準に基づいて、一定の金額を算出するというのが通例です。
慰謝料を算出する際の基準としては、下記の3つが挙げられます。
このうち最も慰謝料が高く算出されやすいのは、弁護士基準です。
後遺障害が残った場合において、交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)掲載の弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりです。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 |
第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 |
1180万円 | 1000万円 | 830万円 | 690万円 | 550万円 |
第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
|
420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
|
例えば、遷延性意識障害や高次脳機能障害等によって常に介護を要する状態になり、第1級の後遺障害が残ったという場合、自賠責保険基準の慰謝料額は1650万円ですが、弁護士基準では2800万円となりますので、1000万円以上の増額が期待し得るということになります。
重い後遺障害が残った場合、その分弁護士をつけた場合の慰謝料等の増額の見込みは高くなりますし、増額の幅も大きくなります。
そのため、基本的にはその増額分で弁護士費用を賄える可能性が高くなります。
また、自分やご家族の保険などに弁護士費用特約が付いているのであれば、一定額を上限に、弁護士費用を保険から賄うことができます。
無料相談を実施している法律事務所もありますので、弁護士を入れるとどのようなメリットがあるのか、どのくらい賠償額の増額が見込めるのかなどについて、気軽に相談してみてもいいでしょう。
(3)後遺障害等級認定を受ける際の注意点
上の表でわかるように、後遺障害が生じてしまった場合の慰謝料の金額は、認定される等級によって、大きな差が生じてきます(本稿では触れていませんが、慰謝料とは別の逸失利益に関しては、もっと大きな差が生じ得ます)。
しかし、どのような場合に認定されるのかについての判断基準は非常に抽象的で、適切な後遺障害等級を認めてもらうのは容易なことではありません。
ポイントを意識して、しっかりと準備を進めておかなければ適切な認定はなされないでしょう。
例えば、高次脳機能障害が生じたのであれば、交通事故発生当時の意識障害と、その原因となる脳についての画像所見・検査所見等がないと、なかなか後遺障害としての認定を取得することは難しいです。
また、高次脳機能障害が生じた場合、日常生活や社会生活に制約が出ることが一般的です。
そのような制約が生じているのかどうか、医師の診断やご家族など周囲の方による報告によって裏付けていくことも重要です。
このほかにも注意を要すべき点はいくつもあります。
これらのポイントを押さえるかたちで検査や資料収集等を行い、後遺障害が残存していることを立証しつつ申請をすることが、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要となります。
なお、後遺障害の認定の申請手続きは、被害者側で行うことができます。
必ずしも加害者側の保険会社に任せなければいけないというわけではないのです。
交通事故により意識不明となるような重傷を負った場合、症状固定時に重度の後遺障害が残る可能性があります。
適切な後遺障害の認定がなされるように、早期に弁護士に相談をして、治療段階から適切なサポートを受け、後遺障害の認定申請手続を含め弁護士に依頼することをお勧めします。
3、被害者が意識不明となった交通事故における示談交渉はもめやすい

被害者が意識不明の重体となってしまう程の重大な交通事故では、示談交渉がもめてしまうことも珍しくありません。
特に、加害者側の保険会社ともめる原因になりやすい争点としては次のようなものが挙げられます。
- 被害者に不利な過失割合を主張される
- 在宅介護に必要な自宅改造の際の費用や将来的に必要となる介護費用の支払を認めてもらえない
たとえば、被害者の意識不明が継続していたり、高次脳機能障害の状況にあってうまく事故状況を説明できないという場合、加害者側の保険会社が、加害者の主張のみに基づいて事故状況や過失割合について判断をする可能性があります。
このような場合、本来の事故状況における過失割合とは異なる、被害者に不利な過失割合を主張される可能性があるのです。
もっとも、仮に被害者が事故状況を適切に説明できない状況にあったとしても、車両の損壊箇所や程度、ブレーキ痕等から事故状況を推認することは可能ですし、目撃者がいれば目撃証言が、ドライブレコーダーや防犯カメラに事故状況が記録されていればその映像等から、事故状況を把握することができます。
被害者が意識不明になるほどの重大事故であれば、通常はこれらの点について警察が捜査していますので、弁護士において刑事記録を取りよせることで、客観的な記録を基に過失割合を争っていくことができます。
また、在宅介護に必要な費用(リフォーム費用など)についても、その必要性等を争われ、減額の主張をされるかもしれません。
また、将来にわたって介護が必要となる場合でも、その点に関する費用が示談金に計上されていないかもしれません。
しかしながら、交通事故と相当因果関係のある損害については、リフォーム費用や将来介護費用等も含め賠償をしてもらうことができるのが原則です。
加害者側の保険会社が不当に争ってくる場合は、すぐに弁護士に相談をし、保険会社の主張の正当性などについて意見を聞いてみてもいいでしょう。
4、意識不明になった事故で弁護士に示談交渉等を依頼する3つのメリット

交通事故の被害者が意識不明の重体になってしまった場合の示談交渉は、弁護士に依頼した方がよい場合が多いといえます。
特に、被害者側が過失ゼロとなるもらい事故の場合には、自分が加入する自動車保険会社に示談代行を依頼することもできません。
重大な後遺障害が残ってしまった被害者の家族がすべての手続きを代行するのには、不可能とも思える負担がのしかかります。
自分で対応しようとせず、弁護士に示談交渉を依頼すれば、次のようなメリットを期待することもできます。
(1)適切な後遺障害等級の認定を受けやすくなる
交通事故事案に強い弁護士に依頼すれば、症状固定前の治療段階から、その後の後遺障害等級認定にむけて適切なサポートを期待することができます。
症状に見合った適切な後遺障害等級を認定してもらうために、必要な検査の実施や資料確保をし、また必要に応じて医師に働きかけをすることもできます。
すでに解説したように、後遺障害慰謝料等の金額は、認定された後遺障害等級に応じて大きく変わりますから、1等級でも不利な認定とならないように、細心の注意を払って対応することが重要です。
(2)慰謝料等の増額が期待できる
弁護士に示談交渉を依頼すれば、「弁護士基準」をベースに、慰謝料額の示談交渉を進めることが可能となります。
弁護士に示談交渉を依頼しなかった場合、加害者側の保険会社から提示される慰謝料額は、自賠責保険の基準額に近い金額になっていることが多く、重度な後遺障害が残ってしまったケースでは、不当に低い金額しか受け取れない可能性があります。
たとえば、上記のとおり、後遺障害等級第1級が認定されたというケースであれば、自賠責保険基準に基づけば1650万円の後遺症慰謝料しか認められませんが、弁護士基準の場合には3000万円近い慰謝料が認められる可能性があります。
その他にも、逸失利益や将来介護費用、自宅改造費等、相手方保険会社としっかりと交渉しなければ十分な額にならない費目は複数あります。
(3)示談交渉以外にもさまざまなアドバイス等を受けられる
被害者が高次脳機能障害等の障害を負った場合、加害者(が加入する任意保険会社)からの賠償のほかにも、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳や重度心身障害者医療費助成制度、障害年金、労働者災害保険等の様々な保障を受けることができる場合があります。
たとえば障害年金についていえば、年金加入者が重度の障害を負い、その障害が継続している場合に、一定の要件を満たせば、定期的に年金を受け取ることができます。
交通事故事案に詳しい弁護士に依頼すれば、治療中の加害者側の保険会社とのやりとりなどを一任することで被害者やそのご家族などの周囲の方の負担を大幅に減らすことができるのに加えて、上記の制度の概要などについてもアドバイスを受けることができます。
まとめ
被害者が意識不明の重体となってしまった交通事故の示談交渉においては、慎重な対応が必要です。
「被害も重篤だし、相手方が100%悪い事故なのだから、加害者の保険会社がちゃんと対応してくれるだろう・・・」と油断をしていると、実際の被害には到底見合わない損害賠償額を提示されてしまうこともあり得ます。
交通事故に遭われた場合、「何か不都合なことがあったら弁護士に相談すればよい」と考える人もいるかと思いますが、被害者が意識不明の重体となったようなケースでは、事故直後から弁護士に相談をしておいた方が良い結果になることが多いでしょうし、そのようにすべきでしょう。
交通事故事件を積極的に取り扱っている事務所では、無料相談を実施しているところが増えています。
また、着手金不要という事務所も増えていますし、弁護士費用特約に加入していれば、一定額を上限に弁護士費用を保険会社に負担してもらうこともできます。
被害者が意識不明になってしまうような深刻な事故は起きないことが望ましいのですが、万が一の場合には、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。