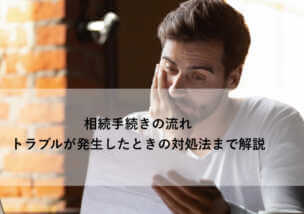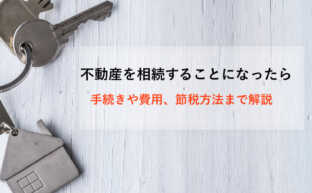相続手続きに必要な書類には、どのようなものがあるのでしょうか。
そのため、『いざ相続が始まった時に何をすればよいのかわからない…』といった状況になることもあるでしょう。
そんな状況を少しでも回避するために、どんな書類を集め、どのように手続きをするのかといったことをあらかじめしっかりと理解しておくことが大切です。
そこで今回は、
- 相続を進めていくために必要な書類
について、ケースごとに解説していきます。この記事が少しでも参考になれば幸いです。
相続の手続きの流れなどについて詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。
1、条件に関係なく必要となる相続書類

まずはじめに、条件に関係なく、必ず用意するべき相続書類は以下の2つです。
これらの書類により、『誰が亡くなったのか』をまず証明する必要があります。
(1)戸籍謄本
1つ目は、被相続人の戸籍の内容が記載されている、戸籍謄本です。
相続人を確定するためにも、この戸籍謄本は必要となります。
記載されている本籍地の役所で取得することができますが、遠い場所にお住まいの場合、郵送や、コンビニのマルチコピー機、またはパスポートセンターでも取得することができます。
(2)住民票の除票もしくは戸籍の附票
2つ目は、亡くなった被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票です。
被相続人の住所や氏名、または本籍地により、たとえ同姓同名の人がいたとしても、住民票の除票もしくは戸籍の附票により、亡くなった人が誰であるかを特定することができます。
2、ケース別で必要となる相続書類

どんな場合であっても必ず用意すべき書類は上記の通りですが、ここではケース別で必要となる書類について、ご紹介します。
(1)相続登記(不動産登記)の場合
①亡くなった人(被相続人)の出生に遡る戸籍謄本
②亡くなった人(被相続人)の住民票除票もしくは戸籍の附票
③相続人全員の戸籍謄本→相続人であることや、現在も存命であることの証明
④相続人全員の印鑑証明書→遺産分割協議書を作成する場合に添付
⑤遺産分割協議書→遺言書がない場合に作成
⑥全部事項証明書→不動産の名義や面積など、登記の記録がすべて記載された書類
⑦固定資産税評価証明書→登録免許税を算出するためにこれを取得し、不動産の価格を調査
(2)銀行などの預金相続手続きの場合
①亡くなった人(被相続人)の出生に遡る戸籍謄本
②亡くなった人(被相続人)の住民票除票もしくは戸籍の附票
③相続人全員の戸籍謄本→相続人であることや、現在も存命であることの証明
④相続人全員の印鑑証明書→遺産分割協議書を作成する場合に添付
⑤遺産分割協議書→遺言書がない場合に作成
⑥銀行等から受け取る申込書
⑦亡くなった人(被相続人)の預金通帳(キャッシュカード)
⑦相関関係説明図→戸籍謄本をもとにした、被相続人と相続人の関係を表した図
その他、
- 払戻し請求書
- 振込用紙
- 相続人の通帳
- 預貯金書
などは各金融機関に用意されていますので、そちらを利用するようにしましょう。
(3)相続税申告 の手続きの場合
<必ず必要な書類>
①亡くなった人(被相続人)の出生に遡る戸籍謄本
②亡くなった人(被相続人)の住民票除票もしくは戸籍の附票
③相続人全員の戸籍謄本→相続人であることや、現在も存命であることの証明
④相続人全員の印鑑証明書→遺産分割協議書を作成する場合に添付
⑤遺産分割協議書→遺言書がない場合に作成
<相続財産に土地がある場合>
①全部事項証明書→不動産の名義や面積など、登記の記録がすべて記載された書類
②公図→土地の大まかな形状や位置を知るための資料
③地積測量図→その土地の形状や面積、また、面積の測定方法などが記載された資料
④固定資産税評価証明書→登録免許税を算出するためにこれを取得し、不動産の価格を調査
⑤固定資産課税台帳→固定資産税の課税対象となる土地・家屋について、不動産の評価額、所在地、面積などを網羅的に確認できる資料
⑥賃貸の契約書
<相続財産に上場株式がある場合>
①証券会社等の残高証明書→被相続人が契約されていた証券会社などのもの
②登録証明書→端株などを確認
③配当金の支払通知書
④被相続人の直近5年間の取引明細→被相続人が契約されていた証券会社などのもの
<相続財産に非上場株式がある場合>
①過去3期分の決算書の写し→勘定内訳書等の添付書類、法人税、地方税、消費税等など
<相続財産に投資信託がある場合>
①残高証明書→さまざまなファンドの金融商品に関するもの
②投資信託についての信託財産留保額及び個別元本額→投資信託を解約する際、そのペナルティとして支払う金額
<相続財産に現金預金がある場合>
①預金残高証明書→被相続人の残高がわかるもの
②過去5年分の通帳・定期預金の証書→被相続人の通帳、または契約されていた金融機関
③既経過利息計算書→定期預金の利息計算書
④手元現金→相続が開始された日の手元に残っている現金
<相続財産に生命保険がある場合>
①生命保険支払通知書→被相続人が契約されていた生命保険会社のもの
②生命保険証書の写し
③火災保険などの保険証書の写し
④解約返戻金のわかる資料→被相続人が契約されていた生命保険会社のもの
<相続財産に債務・葬式費用ある場合>
①金融機関、その他からの借入金→金銭消費貸借契約書のコピー、銀行等の残高証明書
②未納租税公課等→住民税、固定資産税、事業税、国民年金、国民健康保険料、介護保険料などの納税通知書
③その他債務→医療費、公共料金の領収書や請求書
④葬式費用→葬儀にかかった費用(飲食代、お布施など)の領収書、または領収書がない場合はメモでも可
<過去3年間に贈与をされている場合>
①贈与税申告書
②贈与契約書
3、遺言書がある場合

(1)遺言書は検認を受けなければならない
遺言書がある場合、遺言書を発見した人、もしくは遺言書の保管者は、被相続人の死亡を知った後、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。
検認とは、全ての相続人に対し、遺言書を発見したことを伝えると同時に、遺言書の内容を明確にして、その偽造を防止するための手続きのことです。
以下、検認で必要となる書類を記します。
- 遺言書―開封せずそのままの状態で
- 亡くなった人(被相続人)の出生に遡る戸籍謄本
- 亡くなった人(被相続人)の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
(2)遺言書がある場合、原則遺産分割協議書は不要
遺言書がある場合は、遺言書通りの相続を行うことが原則です。
そのため、その場合、遺産分割協議書は不要です。
したがって、遺言書がある場合、上記各ケースの必要書類で「遺産分割協議書」と書かれている箇所については、これに代えて遺言書が必要となります。
しかし、全相続人が遺言内容に反対である場合は違ってきます。
この場合は遺言通りに相続が行われるメリットは少ないと考え、遺産分割協議を行うことができるケースもあります。
このようなケースとして遺言書があるにもかかわらず遺産分割協議を行う場合は、上記各ケースにおける必要書類で必要であれば、遺産分割協議書を作成しましょう。
4、必要書類を集める際の注意点

それではここで、相続の際に必要となる書類を集める時に注意する点について、ご紹介していきます。
(1)相続人に未成年者がいる場合
未成年者は、財産に関わる法律行為を自ら行うことが許されていないため、特別代理人を選任し、手続きを行う必要があります。
この際、単純に相続人である未成年者の親を選任すればよいのかというと、そういうわけではありません。
なぜなら、もしもこの未成年者の親も相続人の場合、両者に利益相反が起こるからです。
利益相反関係とは、どちらかの相続分が増えることで、どちらかの相続分が減ってしまう関係性のことです。
相続に関係しない人であれば、誰でも特別代理人になることができますが、親族を代理人にした場合は何らかの不利益が生じる可能性がありますので、専門家へ代理人を依頼することが賢明でしょう。
(2)金融機関に残高証明書の発行を依頼しておく
相続を行うには、被相続人の全ての財産を把握することが必要不可欠です。
その際、目には見えない金融資産の情報も把握する必要があるのですが、通帳に記載した残高ではそれが確実なものであるとはいえません。
金融機関に依頼し、正確な残高を証明するために、残高証明書を発行してもらいましょう。
(3)期限があるのでお早めに!
相続税の申告は、被相続人が死亡してから10ヶ月以内と定められています。
この間に、配偶者控除の申請や相続税の特例を申請をしない場合、相続人全員で相続税の支払いを分担しなくてはいけないなどのペナルティが発生する恐れがありますので、注意が必要です。
まとめ〜相続トラブルを避けるために〜
今回は、相続の際に必要となる書類について解説してきました。
全て読んでいただければわかるように、個人でこれらの書類をすべて用意するのは困難ですし、注意すべき点もたくさんあります。
その際は一人で悩むことなく、弁護士などの専門家に依頼するようにしましょう。
親族内での相続トラブルを避けるためにも、専門家へ依頼した方が賢明です。
相続が始まった際に焦ることのないように、この記事が少しでも参考になれば幸いです。